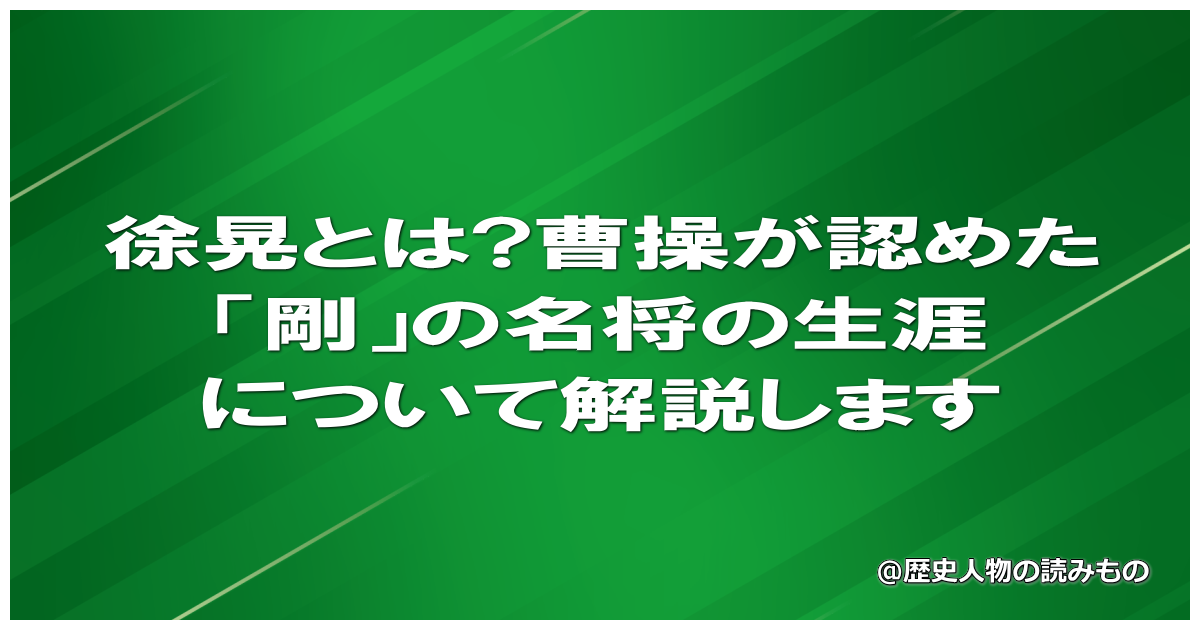歴男になりたい
歴男になりたい徐晃ってどんな人物だったのかな?



徐晃の戦歴が知りたい
この記事では、こんな疑問にお答えしますね。
- 徐晃の生い立ち
- 徐晃の主な戦歴とその能力
- 正史と演義での描かれ方の違い
- 関羽との親交の真実
- 徐晃の最期とその後の評価


- 歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き


- 歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き
徐晃と言えば、三国志の武将の中でも個性派として有名ですよね?
そして、この徐晃は生涯において無敗の将としても知られています。
ただ、無敗の将以外、その生涯を知る人は意外と少ないかもしれません。
そこで、当記事では三国志の名将!徐晃の知られざる生涯とその魅力について解説します
徐晃とは?
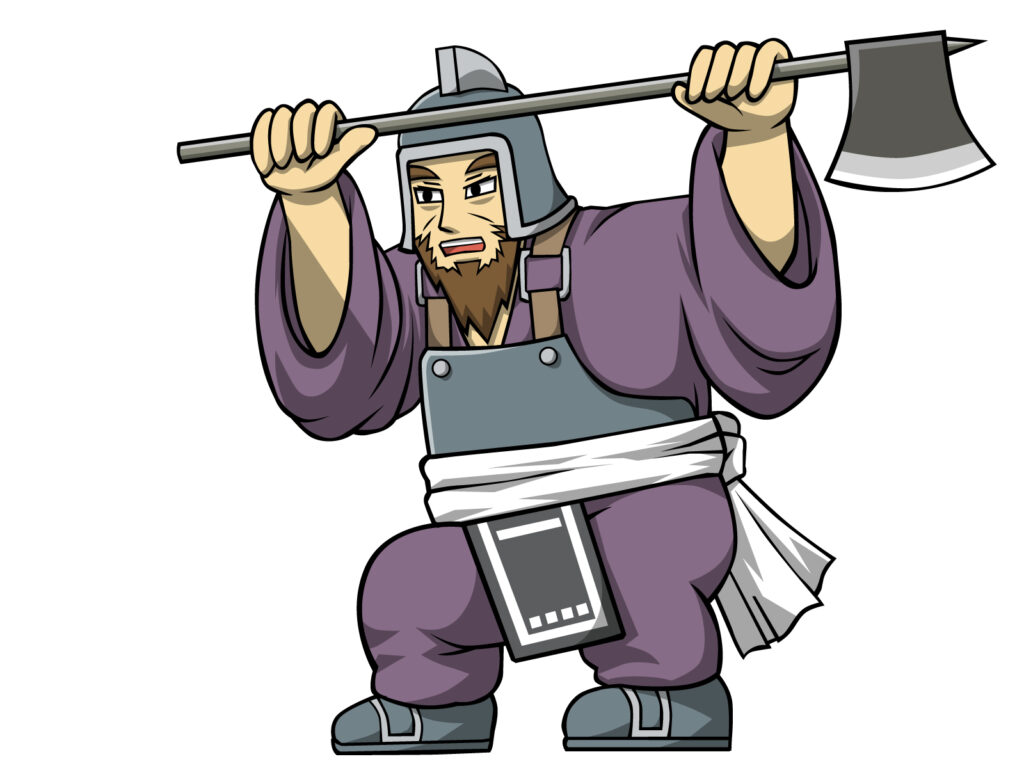
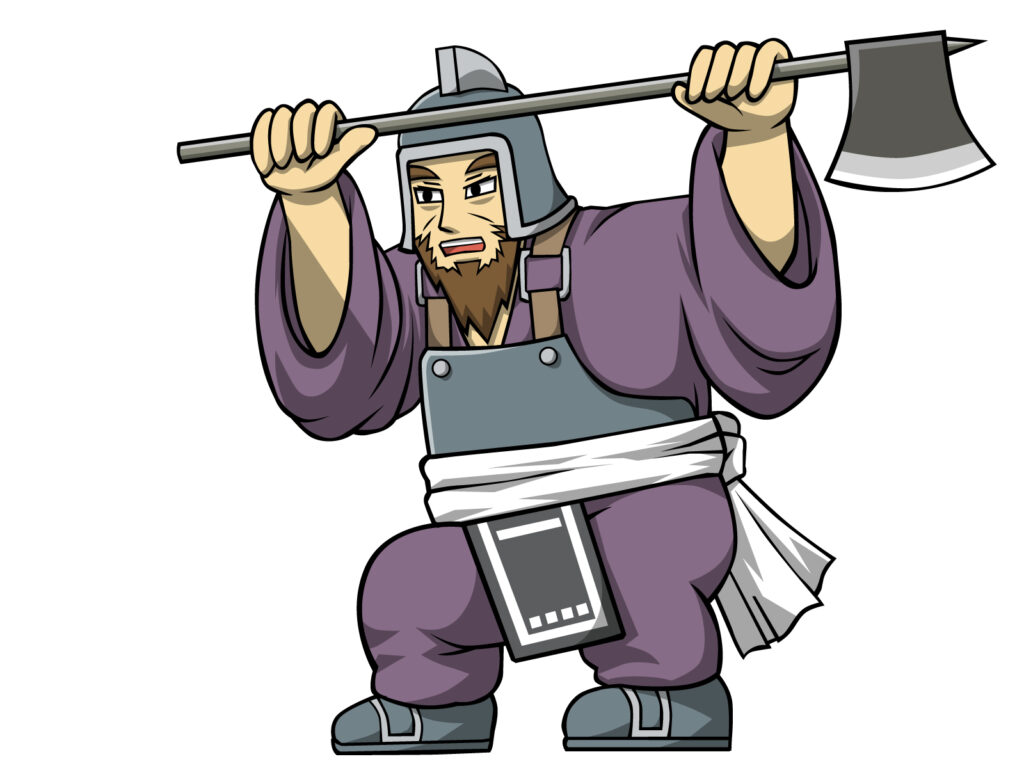
徐晃は、中国後漢末期から三国時代にかけて活躍した武将です。
字は公明といい、河東郡楊県の出身とされています。
徐晃の生年は不詳ですが、196年頃から歴史の舞台に登場し、227年に亡くなるまで約30年以上にわたって第一線で活躍しました。
そして、最終的な官位は右将軍、死後には「壮侯」という諡号を賜っています。
ちなみに、徐晃は元々、地元の郡吏として働いていました。
その後、楊奉という武将の配下となりましたが、196年から197年頃に曹操陣営に帰順します。
この選択が、彼の運命を大きく変えることになったんですね。
徐晃の生涯年表
徐晃の人生を時系列で整理すると、その長いキャリアと数々の功績が見えてきます。
| 時期 | 年齢 | 出来事 |
|---|---|---|
| 生年不詳 | – | 河東郡楊県に生まれる |
| 190年代前半 | 20代? | 河東郡の郡吏となる |
| 196年頃 | – | 楊奉の配下として活動開始 |
| 196-197年 | – | 曹操陣営に帰順 |
| 200年 | – | 官渡の戦いに従軍、顔良討伐に貢献 |
| 201-207年 | – | 河北平定戦に参加 |
| 211年 | – | 馬超討伐戦に従軍 |
| 217-219年 | – | 漢中攻防戦に参加 |
| 219年 | – | 樊城の戦い—関羽軍を撃破(最大の功績) |
| 220年 | – | 魏建国、右将軍に昇進 |
| 227年 | – | 死去、諡号「壮侯」を賜る |
この年表から分かるように、徐晃は曹操に仕えてから死ぬまで、一貫して重要な戦役に参加し続けています。
特に注目すべきは、魏建国後も曹丕から信頼され続けたという点ですね。
年表から見える徐晃の特徴
徐晃の年表を見ると、いくつかの重要な特徴が浮かび上がってきますね。
まず、曹操に30年以上仕えた忠臣であるということ。
三国時代は、裏切りや寝返りが日常茶飯事でした。
ただ、徐晃は一度曹操陣営に加わってから、最後まで忠誠を貫きました。
次に、主要な戦役のほとんどに参加していることです。
官渡の戦い、河北平定、馬超討伐、漢中攻防、樊城の戦いと、曹操軍の重要な戦いには必ず徐晃の名前があります。
これは、彼の軍事的価値と曹操からの信頼性の高さを示しています。
そして、晩年まで第一線で活躍したこと。
多くの武将が年齢とともに退いていく中、徐晃は60歳近くまで戦場に立ち続けました。
最後に、魏建国後も重用されたという点です。
曹操時代の功臣の多くは、曹丕の代になると冷遇されました。
しかし、徐晃は右将軍という高い地位を与えられています。



徐晃の長いキャリアが示すのは、武勇だけでなく人格も評価されていた証拠ですね。
徐晃の主要な戦功—官渡から樊城まで


官渡の戦いでの活躍(200年)
徐晃の名が歴史に刻まれた最初の戦いが、200年の官渡の戦いです。
この戦いは、曹操と袁紹という当時の二大勢力が激突した決戦でした。
結果は、兵力では袁紹が圧倒的に優位でしたが、曹操は巧みな戦略で勝利を収めています。
そして、徐晃はこの戦いで、袁紹軍の猛将・顔良の討伐に貢献しました。
正史『三国志』によれば、関羽が顔良を討ち取る際、徐晃も重要な役割を果たしています。
この功績により、徐晃は曹操からの信頼を確固たるものにしたようですね。
また、官渡の戦いでの活躍は、徐晃にとってキャリアの転換点となりました。
以後、彼は曹操軍の主力武将として、数々の戦役に参加することになります。
河北平定と馬超討伐(201-211年)
官渡の戦い後、曹操は袁氏一族の残党を掃討するため、河北地域の平定に乗り出します。
徐晃は、この一連の戦いにも従軍し、確実に功績を積み重ねていきました。
特に注目すべきは、211年の馬超討伐戦です。
馬超は当時、西涼地域を支配する強力な武将で、その武勇は劉備や張飛と並び称されるほどでした。
そして、曹操は自ら大軍を率いて馬超討伐に向かい、渭水のほとりで激戦を繰り広げます。
徐晃は、この戦いでも重要な役割を果たし、馬超軍の撃破に貢献したのです。
正史には詳細な記述はありませんが、曹操の信頼を受けて主力部隊の一翼を担っていたことは間違いありません。
樊城の戦い—徐晃最大の功績(219年)
徐晃の戦歴の中で、最も輝かしい功績が219年の樊城の戦いですね。
この年、関羽は荊州から北上し、樊城を守る曹仁を包囲しました。
関羽軍の勢いは凄まじく、于禁率いる7軍を水攻めで壊滅させ、于禁と龐徳を捕虜にし、樊城陥落は時間の問題と思われました。
このとき、曹操が救援に派遣したのが徐晃でした。
徐晃は慎重に進軍し、まず関羽軍の包囲網の外側に陣を構えます。
そして、関羽軍の補給線を脅かしながら、樊城との連絡路を確保する作戦に出ました。
この樊城の戦いで、徐晃の戦術は見事にはまりました。
彼は正面からの突撃を避け、関羽軍の弱点を突く形で包囲を突破します。
これに対して、関羽は徐晃軍を迎撃しますが、徐晃の堅固な陣形を崩すことが出来なかったのです。
最終的に、徐晃は樊城の包囲を解くことに成功し、曹仁を救出します。
この結果、関羽軍は撤退を余儀なくされ、関羽の北伐は失敗に終わりました。
そこで、この功績に対して曹操は徐晃を「周亜夫の風あり」と称賛したのです。
周亜夫とは、前漢時代の名将で、軍律の厳格さで知られる人物です。
これは、武将に対する最高の賛辞でした。
漢中攻防戦とその他の戦役
樊城の戦いの前、217年から219年にかけて、曹操は劉備と漢中の支配権をめぐって激しく争っていました。
そして、徐晃はこの漢中攻防戦にも参加しています。
もう、曹操の戦いにはどこでも徐晃がいるように、その信頼性は群を抜いているように思えます。
ちなみに、この戦いで漢中は劉備の手に落ちました。
しかし、徐晃は撤退戦においても冷静に任務を遂行し、曹操軍の損害を最小限に抑えたのです。



徐晃は、派手さはありませんが確実に成果を上げる将軍だったので、曹操が最も信頼を置いた理由が分かりますね。
徐晃の人物像—正史と演義で異なる姿
正史に見る実像は「剛直」な性格
正史『三国志』が伝える徐晃は、「剛直」という言葉がぴったりの人物でした。
剛直とは、心が強く正直で、曲がったことを嫌う性格です。
徐晃はまさにこの言葉通りの武将だったんですね。
その中でも、最も有名なエピソードが、故郷の知人との接し方です。
徐晃が将軍になった後、河東郡の出身者たちが彼を頼って訪ねてきました。
しかし、徐晃は公務と私事を厳格に区別し、故郷の知人だからといって特別扱いすることはありませんでした。
そして、軍律の維持においても、徐晃は一切の妥協を許しませんでした。
たとえ、親族や旧友であっても、規律を破れば容赦なく罰しています。
この厳格さが、徐晃の軍が常に高い戦闘力を維持できた理由の一つです。
また、徐晃は曲がったことを嫌う気質の持ち主でした。
不正や欺きを見逃すことができず、たとえ権力者が相手でも正論を主張しました。
もっとも、この性格は時に敵を作ることもありました。
しかし、曹操や曹丕からは「信頼できる人物」として高く評価されていたのです。
曹操・曹丕からの評価
徐晃が、魏の二代にわたる君主から信頼された理由は、彼の能力と人格の両方にありました。
曹操は、樊城の戦い後に徐晃を「周亜夫の風あり」と称賛しました。
ちなみに、周亜夫は前漢時代の名将で、呉楚七国の乱を鎮圧した功績で知られています。
彼の最大の特徴は、軍律の厳格さでした。
そして、これは皇帝が軍営を訪れた際も、規律を曲げることはありませんでした。
正式な手続きを踏むまで、皇帝の入営を許さなかったというエピソードが残っています
そこで、曹操が徐晃を周亜夫に例えたのは、徐晃もまた軍律を何より重んじる武将だったからです。
これは曹操にとって最高の賛辞でした。
その後220年、曹操が死去し、息子の曹丕が魏王朝を建国すると、多くの功臣が冷遇されました。
しかし、徐晃は右将軍に昇進し、引き続き重要な地位を与えられます。
これについて、曹丕が徐晃を重用した理由も、父・曹操と同じでした。
徐晃は権力に媚びず、常に公正な判断を下す人物でした。
新しい王朝にとって、こうした信頼できる武将の存在は不可欠だったんですね。
演義(フィクション)での描写
小説『三国志演義』における徐晃の描写は、正史とはかなり異なります。
演義では、徐晃は「開山大斧」という大きな斧を使う豪傑として描かれています。
ちなみに、正史には徐晃の武器についての記述はありません。
ただ、演義での印象的な描写により、「徐晃=大斧使い」というイメージが定着したのです。
また、正史と演義で最も大きな違いは、関羽との関係です。
演義では、徐晃と関羽は旧友という設定になっています。
樊城の戦いでは、「今日は公事、私情を挟まず」と言いながら涙ながらに戦う場面が描かれています。
しかし、これは演義における完全な創作です。
正史には、徐晃と関羽が親交があったという記述は一切無いのですから。
徐晃の武勇と実力
徐晃は、知略のみならず武勇にも優れた武将でした。
官渡の戦いでの顔良討伐、樊城での関羽軍撃破、馬超討伐での功績などなど。
徐晃は数々の強敵と戦い、勝利を収めています。
ただ、徐晃の真の強さは個人の武勇よりも、戦術眼と統率力にありました。
彼は感情に流されず、冷静に戦況を分析し、最適な作戦を立てることが出来たんですね。
さらに、厳格な軍律により部隊を統率し、確実に任務を遂行しました。
これは、張飛のような猛将とは異なるタイプの強さですが、軍事的には極めて重要な能力だったのです。



徐晃の真の魅力は、武勇だけでなく「規律」を何より重んじた点にありますね。親族であっても特別扱いしない姿勢は部下にも良い影響を与えたことでしょう。
徐晃と関羽—史実とフィクションの真実


「旧交」は本当か?
先ほども書きましたが、小説『三国志演義』では、徐晃と関羽は旧友という設定になっています。
ただ、この「旧友」設定には史料的な根拠がありません。
正史『三国志』の徐晃伝にも関羽伝にも、両者が親交を持っていたという記述は一切ないのです。
同時代の武将として、多少なりとも面識はあったかもしれません。
しかし、「旧友」と呼べるような関係だったという証拠はどこを探しても無いのです。
それでは、なぜ演義でこのような設定が生まれたのでしょうか?
これについて、いくつかの解釈が考えられますね。
一つは、物語的な悲劇性を高めるためです。
「友を斬らねばならない」という状況は、読者の感情を強く揺さぶりますよね?
この点において、徐晃が任務と義理の間で苦悩する姿は、人間ドラマとしてとてもに魅力的に映ります。
もう一つは、関羽という英雄を倒した徐晃の功績を、より印象的に描くためです。
ただの敵ではなく、かつての友を倒したという設定であれば、徐晃の軍人としてより強い覚悟を強調することが出来ます。
いずれにせよ、「旧友」設定は演義作者の創作であり、史実ではないということを理解しておきましょう。
史実の徐晃の評価
演義の描写はともかく、史実において徐晃が関羽を撃破したことは、当時は大きな衝撃を与えたことでしょう。
関羽は、「万人の敵」と称されるほどの強将でした。
その関羽が率いる軍を撃破したことで、徐晃の名声は一気に高まったのですから。
そして、曹操は徐晃を「周亜夫の風あり」と称賛しました。
これは、徐晃の軍事的才能、特に規律正しい用兵を評価したものなんです。
感情に流されず、冷静に戦況を分析し、確実に勝利を収める。
それが、徐晃という武将の真価と言えますね。



正史と演義、両方を知ることで徐晃の多面的な魅力が分かりますね。史実の徐晃は「規律の人」、演義の徐晃は「義理の人」。どちらもとても魅力的です。
徐晃の晩年と後世への影響
魏建国後の活躍(220-227年)
220年、曹操が死去します。
そして、息子の曹丕が後を継ぎ、同年、漢の献帝から禅譲を受けて魏王朝を建国しました。
この政権交代の時期には、多くの曹操時代の功臣が冷遇されました。
曹丕は新しい臣下を求め、古い世代の武将たちは徐々に影響力を失っていったのです。
しかし、この中でも徐晃は例外でした。
曹丕は、徐晃を右将軍に昇進させ、引き続き重要な地位を与えています。
これは、徐晃の能力と人格が、世代を超えて評価されていたことを示していますね。
その後、徐晃は220年から227年まで、約7年間にわたって曹丕に仕えました。
この間、具体的にどのような任務に就いていたかは史料に詳しく記されていません。
おそらく、魏の国境防衛や地方統治において重要な役割を果たしていたと考えられます。
また、晩年の徐晃は、おそらく60歳前後だったと推測されます。
当時としてはかなりの高齢ですが、彼は最後まで第一線で任務を遂行し続けました。
徐晃の最期と諡号
227年、徐晃は死去しました。
享年は不明ですが、30年以上にわたる軍歴を全うした生涯でした。
そして、徐晃の死後、魏朝廷は彼に「壮侯」という諡号を贈りました。
諡号とは、死後にその人物の生涯を評価して贈られる称号です。
「壮」という字には、「勇猛果敢」「功績著しい」という意味があります。
この諡号は、徐晃の軍歴と功績を高く評価したものでした。
歴代の評価
正史『三国志』を著した陳寿は、徐晃を「剛」の評価で記しています。
陳寿は、徐晃伝の最後に、張遼、楽進、于禁、張郃と並べて徐晃を評価しました。
「これら五将は、時代の優れた将軍であった」と記し、特に徐晃については「剛」という言葉で評価しています。
「剛」とは、心が強く、揺るがない意志を持つことを意味します。
これは、徐晃の性格と軍歴を的確に表現した評価と言えますね。
また、後世の歴史家たちも、徐晃を高く評価しています。
特に軍事史の研究者たちは、徐晃の用兵の巧みさと規律の厳格さを、理想的な将軍像として取り上げていますね。
曹魏の五大将軍として、張遼、楽進、于禁、張郃、徐晃の五人が挙げられることがあります。
この中で、徐晃は最も長く第一線で活躍した武将の一人だったのです。
現代での人気
現代において、徐晃は三国志ファンの間で一定の人気を持つ武将です。
ゲームやマンガなど、様々な媒体で徐晃は登場していますよね?
コーエーテクモゲームスの「真・三國無双」シリーズでは、大斧を振るう豪快な武将として描かれています。
そして、横山光輝の漫画『三国志』では、樊城の戦いでの活躍が印象的に描かれています。
関羽との一騎打ちの場面は、多くの読者の記憶に残っていることでしょう。
また、王欣太の『蒼天航路』では、より人間味のある徐晃が描かれています。
規律を重んじながらも、内面に葛藤を抱える武将として表現されており、新しい徐晃像を提案していますね。



徐晃って地味な印象があるけど、結構人気が高いんですね。



徐晃の魅力は、「地味だが堅実」という日本人好みの武将像にあります。派手さはないものの、確実に仕事をこなす姿は、現代人にも共感されていますね。
まとめ
徐晃は、曹操・曹丕二代にわたって仕えた「剛直」な名将でした。
官渡の戦いから樊城の戦いまで、30年以上にわたり第一線で活躍し、数々の功績を残しています。
特に、219年の樊城の戦いで関羽を撃破した際には、曹操から「周亜夫の風あり」という最高の賛辞を受けたのです。
また、正史『三国志』が伝える徐晃は、厳格な軍律と公私混同しない姿勢で知られる武将です。
その一方で、小説『三国志演義』では、関羽との「旧友」という設定で「友を斬る」という悲劇が描かれています。
もっとも、これは史実ではありませんが、物語として非常に魅力的であり、徐晃の人気を支える要因の一つです。
このように、史実とフィクションは異なりますが、どちらも徐晃の魅力を伝えています。
正史の徐晃からは、「規律の重要性」であり、演義の徐晃からは、「義理と任務の葛藤」を学ぶことが出来ますね。



徐晃は、派手さはないものの剛直であり、曹操・曹丕からともに信頼されていた武将でしたね。