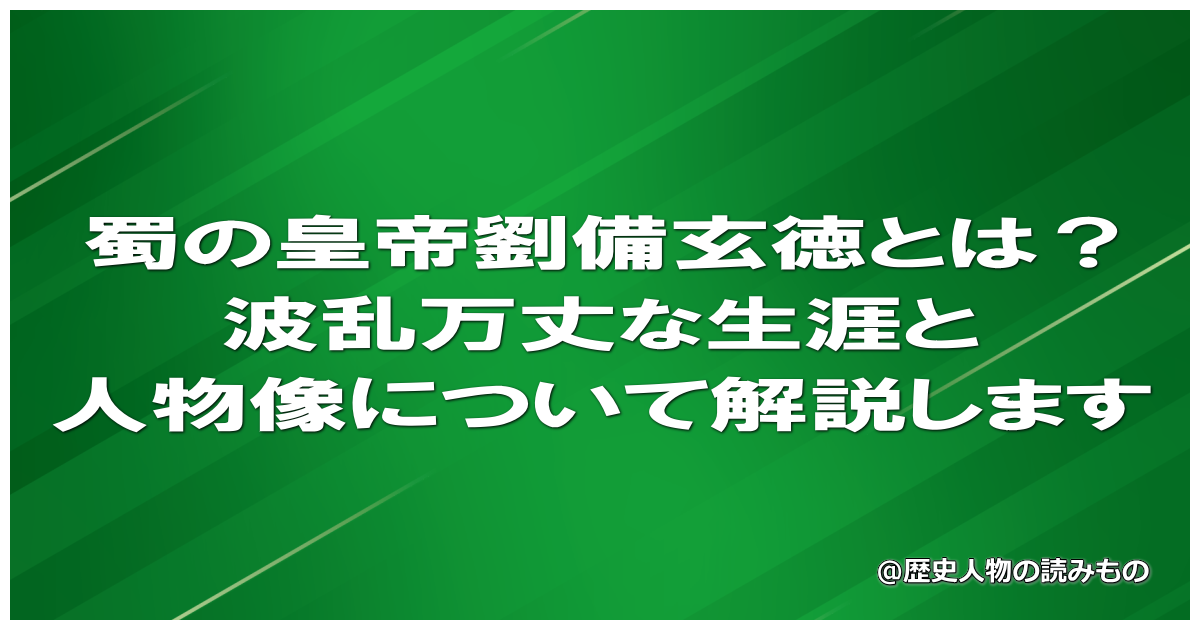歴男になりたい
歴男になりたい劉備の波乱万丈な人生ってどういうこと?



劉備の最期ってどうなったのか知りたい
この記事では、こんな疑問にお答えしますね。
- 幼少期の劉備の生活
- 劉備の生涯年表(時系列で解説)
- 劉備と諸葛亮との出会い
- 劉備の性格と人物像
- 劉備の有名なエピソード
- 正史と演義での描き方の違い


- 歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き


- 歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き
三国志ファンなら誰もが知る劉備玄徳(りゅうびげんとく)。
彼は161年に生まれ、223年に62歳で亡くなるまで、まさに「波瀾万丈」という言葉がぴったりの人生を歩みました。
劉備の最大の魅力は、そのドラマチックな生涯にあります。
漢王朝の末裔でありながら、幼少期は母親と草履を売って生計を立てるほどの貧しさ。
そこから這い上がり、最終的には蜀漢の初代皇帝にまで上り詰めたのです。
そこで、当記事では蜀の皇帝劉備玄徳とは?波乱万丈な生涯と人物像について解説します。
劉備玄徳とは?


三国志を語る上で欠かせない劉備玄徳。彼は一体どんな人物だったのでしょうか?
まずは、基本的なプロフィールから見ていきましょう。
生没年と出身地
劉備は161年に生まれ、223年に亡くなりました。
享年62歳という、当時としては比較的長命な生涯を送っています。
出身は涿郡涿県(たくぐんたくけん、現在の河北省)。
この地は漢王朝の発祥地にも近く、劉備が「漢の皇族の末裔」を名乗る上で重要な意味を持つ土地でした。
劉備のプロフィールで最も重要なのは、彼が「中山靖王・劉勝の子孫」を自称していたこと。
つまり、漢王朝の創始者・劉邦の血を引く皇族の一員というわけです。
ただし、何代も前の傍系であり、実際には貧しい家庭に生まれ育ちました。
「玄徳」の意味
劉備の字(あざな)は「玄徳(げんとく)」といいます。
字とは成人した男性が本名とは別に名乗る名前のこと。
「玄」は奥深い、「徳」は人徳を意味し、合わせて「深い徳を持つ者」という意味になります。
この字は劉備の人物像を表すのにぴったりですね。
また、三国志演義では特に、劉備玄徳は「仁徳の人」として描かれています。
民を思いやる心、義兄弟への厚い情、部下への信頼。
こうした「徳」の高さこそが、劉備の最大の武器だったのです。
劉備の外見的特徴(史書の記述より)
史書『三国志』によると、劉備の容姿には非常に特徴的な記述があります。
- 身長は七尺五寸(約173cm)当時としては平均的な高さ
- 腕が膝まで届いたという驚異的な記録
- 耳が大きく、自分の耳を見ることができた
- 口数が少なく、喜怒を表に出さない性格
特に「腕が膝まで届く」という記述は印象的ですね。
これは、実際の身体的特徴というより、劉備が「尋常ではない人物」であることを表現するための誇張とも考えられています。
同様に、「自分の耳が見える」というのも、英雄らしさを強調する表現でしょう。
こうした外見の記録は、劉備とは何者かを理解する上で興味深い手がかりとなります。
蜀漢の初代皇帝となる劉備玄徳、その人物像は、史実と伝説が入り混じった魅力的なものなのです。



腕が膝まで届くって?すごいね。



英雄は誇張表現される場合が多いからね。
劉備玄徳の生涯年表
まずは、劉備玄徳の年表を時系列でみてみましょう。
| 年代 | 年齢 | 出来事 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 161年 | 誕生 | 涿郡涿県に誕生 | 漢の皇族の末裔だが貧しく、母と草履売りで生計を立てる |
| 184年 | 23歳 | 黄巾の乱で挙兵 | 関羽・張飛と出会う(演義では「桃園の誓い」) |
| 194年 | 33歳 | 徐州を譲り受ける | 陶謙から徐州を譲り受け、初めて領地を持つ |
| 196年 | 35歳 | 呂布に徐州を奪われる | 再び放浪の身に |
| 200年 | 39歳 | 袁紹のもとへ | 曹操の元から脱出し、袁紹のもとへ逃れる |
| 201年 | 40歳 | 劉表に身を寄せる | 荊州の新野に身を寄せる |
| 207年 | 46歳 | 三顧の礼 | 諸葛亮を軍師に迎える(人生最大の転機) |
| 208年 | 47歳 | 赤壁の戦い | 孫権と同盟し、曹操の大軍を撃破 |
| 214年 | 53歳 | 益州平定 | 成都を本拠地とする。ようやく確固たる勢力基盤を築く |
| 219年 | 58歳 | 漢中王に即位 | しかし同年、関羽が荊州で戦死 |
| 221年 | 60歳 | 蜀漢皇帝に即位 | 草履売りから皇帝へ、ついに頂点に立つ |
| 222年 | 61歳 | 夷陵の戦いで大敗 | 関羽の復讐に燃えた戦いが致命的な失敗に |
| 223年 | 62歳 | 白帝城で崩御 | 諸葛亮に後事を託し、崩御 |
人生の主要転機
| 転機 | 内容 | 影響 |
|---|---|---|
| 🔴 207年(46歳) | 三顧の礼で諸葛亮を迎える | 人生最大の転機。天下三分の計を得る |
| 🟢 208年(47歳) | 赤壁の戦いで勝利 | 勢力拡大の契機 |
| 🟡 221年(60歳) | 蜀漢皇帝即位 | 人生の頂点 |
| 🔴 222年(61歳) | 夷陵の戦いで大敗 | 致命的な失敗、死期を早める |
劉備の生涯を時系列で解説


劉備玄徳の62年間の人生は、まさに波瀾万丈という言葉がぴったりです。
ここでは、彼の生涯を3つの時期に分けて、詳しく見ていきましょう。
前半生:流浪の時代(161年~207年)
劉備の人生は、決して順風満帆なスタートではありませんでした。
漢王朝の末裔とはいえ、父を早くに亡くし、母親と二人で草履やむしろを売って生計を立てる貧しい日々。
この幼少期の苦労が、後の劉備の「民を思う心」の原点となったのかもしれませんね。
184年、劉備23歳のとき、中国全土を揺るがす「黄巾の乱」が勃発。
劉備は、この乱の鎮圧に義勇軍として参加し、ここで関羽と張飛という生涯の盟友と出会います。
ちなみに、三国志演義では、「桃園の誓い」として描かれていますが、これはフィクションです。
194年、劉備33歳。徐州の太守・陶謙が病の床で劉備に後を託し、劉備は徐州牧となります。
しかし196年、劉備が袁術討伐に出陣している隙に、武将・呂布が徐州を占領。
その結果、劉備は拠点を失い、再び流浪の身となり、曹操や袁紹のもとを転々とする不安定な日々が続きました。
207年、劉備46歳のとき、人生最大の転機が訪れます。
若き天才軍師・諸葛亮(しょかつりょう、字は孔明)を三度も訪ねて迎え入れる「三顧の礼」です。
諸葛亮は、劉備に「天下三分の計」という壮大な戦略を提示し、劉備の運命は大きく動き始めたのです。
中期:勢力拡大期(208年~219年)
208年、劉備47歳。曹操が大軍を率いて南下してきます。
劉備は諸葛亮の献策により、江東の孫権と同盟を結び、中国史上屈指の名戦「赤壁の戦い」で曹操の大軍を撃破。
この勝利により、天下三分の構図が現実味を帯びてきます。
214年、劉備53歳のとき、同族の劉璋から益州を奪取。
益州の成都を都として、確固たる勢力基盤を築きました。
そして、219年には漢中を攻略し、「漢中王(かんちゅうおう)」を自称します。
しかし同じ年、荊州を守っていた義弟・関羽が呉の呂蒙の策略にはまり、捕らえらてしまいます。
劉備にとって、関羽の逝去は人生最大の痛手となりました。
晩年:栄光と挫折(221年~223年)
221年、劉備60歳のとき、成都で皇帝に即位。
国号を「蜀漢(しょくかん)」とし、漢王朝の正統な後継者であることを宣言しました。
最初は草履売りから始めた少年が、ついに皇帝にまで登り詰めたのです。
しかし、劉備は関羽の仇を討つため、222年に大軍を率いて呉への遠征を開始します。
諸葛亮は反対しましたが、劉備の決意は固いものでした。
ところが「夷陵の戦い(いりょうのたたかい)」で、若き呉の将軍・陸遜(りくそん)の火計によって大敗。
劉備軍は壊滅的な打撃を受けます。
その後、劉備は白帝城(はくていじょう)に退却し、病に倒れます。
223年、劉備62歳。臨終の床で諸葛亮を枕元に呼び、息子の劉禅(りゅうぜん)を託します。
こうして劉備玄徳の波瀾万丈の生涯は幕を閉じたのです。
劉備の生涯を振り返ると、何度も挫折しながらも決して諦めず、最後には皇帝にまで上り詰めた不屈の精神が印象的ですよね。
黄巾の乱から始まり、三顧の礼、赤壁の戦い、そして夷陵の戦い。
その人生は、まさに三国志という時代そのものだったと言えるでしょう。



諸葛亮を三度も訪ねるなんて、それほど重要だったんですね。



諸葛亮がいなければ、劉備の蜀漢建国は無かったかも知れないね。
劉備の性格と人物像
劉備玄徳という人物を理解するには、史実と演義での描かれ方の違いを知ることが重要です。
実像と理想像、その両面から劉備の人物像に迫ってみましょう。
史実の劉備:計算高い政治家
正史『三国志』に描かれる劉備は、「仁徳の君主」というイメージとは少し異なります。
確かに人材登用の才能に優れ、多くの人物を引きつける魅力がありました。
ただ、同時に非常に計算高く、したたかな政治家でもありました。
史書には「劉備は喜怒を表に出さず、人の心を掴むのが巧みだった」と記されています。
これは単なる温厚さではなく、感情をコントロールして人心掌握に利用する政治的手腕を示しています。
また、徐州を陶謙から譲り受けた際も、益州を劉璋から奪った際も、表面的には謙虚に振る舞っています。
しかし、最終的には領地を手に入れる巧妙さを見せました。
そして、劉備の性格の中核にあったのは、圧倒的な「忍耐力」です。
何度も敗北し、各地を転々としながらも決して諦めず、機会を待ち続けた不屈の精神。
この粘り強さこそが、劉備を最終的に皇帝の座へと導いた最大の武器でした。
演義の劉備:仁徳の君主
一方、小説『三国志演義』で描かれる劉備は、「仁徳」を体現する理想的な君主像です。
民を思いやり、涙もろく人情深い人物として描かれています。
演義の劉備は、常に「義」を重んじ、困っている人を見過ごせない性格として表現されているのです。
ただし、演義でも劉備の「人たらし」的な才能はしっかり描かれており、単なる善人というわけではありません。
むしろ、人間味あふれる魅力的なリーダーとして表現されていますね。
劉備の強みと弱み
劉備の人物像を整理すると、以下のような強みと弱みが見えてきます。
強み:
- 人材を見抜き、登用する才能(関羽、張飛、諸葛亮など)
- 人心掌握の巧みさと人間的魅力
- 逆境に負けない忍耐力と不屈の精神
- 時機を待つ我慢強さ
弱み:
- 感情に流されやすい面(夷陵の戦いでの判断ミス)
- 義理人情を重視しすぎて戦略的判断を誤ることも
- 関羽の死後、復讐心に駆られて国力を消耗させた
特に、晩年の夷陵の戦いは、劉備の性格における最大の弱点が表れた戦いでした。
諸葛亮の反対を押し切り、関羽の仇討ちに固執した結果、蜀漢は致命的な打撃を受けます。
この感情的な判断が、劉備という人物の人間臭さを物語っているとも言えるでしょう。
劉備玄徳の性格は、完璧な聖人でも冷酷な権力者でもありません。
強い信念と人間的な弱さを併せ持つ、極めて人間味あふれるものだったのです。



劉備は、仁徳あふれる人物として有名ですね。
劉備の有名なエピソード


劉備玄徳の人生には、彼の人柄や魅力を物語る数々のエピソードが残されています。
ここでは特に有名な4つのエピソードを紹介しましょう。
三顧の礼
劉備のエピソードで最も有名なのが「三顧の礼」です。
207年、当時46歳だった劉備は、27歳の若き天才・諸葛亮を軍師として迎えるため、三度も彼の庵を訪れました。
一度目と二度目は諸葛亮が不在で会えず、三度目にようやく面会が叶います。
しかも、三度目の訪問では、諸葛亮が昼寝をしてたのです。
そこで、劉備は彼が目を覚ますまで静かに待ち続けたとされています。
46歳の主君が27歳の若者を三度も訪ね、しかも昼寝が終わるまで待つ。
この謙虚さと人材への敬意が、劉備という人物の本質を表しています。
ちなみに、このエピソードは史実として記録されています。
「人材を得るためには地位も年齢も関係ない」という劉備の姿勢を示す代表的な逸話ですね。
劉備の涙
劉備は「涙もろい人物」としても知られています。
特に演義では、民衆を思って涙を流す場面が数多く描かれており、「劉備の涙」は彼の仁徳を象徴するエピソードです。
そして、最も有名なのが、曹操の大軍に追われて新野(しんや)を離れる際のエピソードです。
劉備は、自分に従う数万の民衆を連れて逃げることを選びます。
民衆を連れていくことで行軍速度は遅くなり、軍事的には極めて不利な状況になってしまいます。
しかし、劉備は「民を見捨てることはできない」と涙ながらに語ったとされています。
この涙は、劉備が単なる権力者ではなく、民を思う仁徳の心を持った君主であることを示していますね。
阿斗を投げ捨てた逸話
劉備のエピソードの中で、特に印象的なのが「阿斗を投げ捨てた」という逸話です。
ちなみに、阿斗とは劉備の息子・劉禅の幼名です。
曹操軍に追われる中、趙雲が命がけで劉備の息子・阿斗を救い出しました。
赤ちゃんを抱いて戻ってきた趙雲に対し、劉備は阿斗を地面に投げ捨てて言います。
「子供のために趙雲のような名将を危険にさらすところだった」と涙を流したとされています。
この行動は、「子供は代わりができるが、趙雲のような人材は代わりがいない」という劉備の人材重視の表れですね。
ただし、このエピソードは演義の創作であり、史実ではありません。
劉備の人材登用の才能を強調するための創作と考えられています。
白帝城での遺言
劉備のエピソードで最も感動的なのが、白帝城(はくていじょう)での遺言の場面です。
223年、夷陵の戦いで大敗した劉備は白帝城で病に倒れ、臨終を悟ります。
劉備は諸葛亮を枕元に呼び、息子の劉禅を託す「託孤(たくこ)」を行います。
そしてこの時、劉禅に向けて残した言葉が、今も名言として語り継がれています。
「勿以悪小而為之、勿以善小而不為(小さな悪でもするな、小さな善でも怠るな)」
この言葉は、「どんなに小さな悪事でも行ってはならず、どんなに小さな善行でも疎かにしてはならない」という教えです。
劉備が息子に託した人生哲学であり、現代でも通じる普遍的な教訓として多くの人に影響を与えています。
この白帝城での劉備の遺言は、草履売りから皇帝にまで上り詰めた男の、最後の言葉として深い感動を呼ぶのです。



阿斗を投げたエピソードは実在しないんですか?



このエピソードは結構有名だけど、史実には記述がないんですね。
史実と演義の違い
劉備玄徳には2つの顔があります。それは歴史書と小説で描かれる姿の違いです。
三国志を楽しむなら、この違いを知っておくと面白さが倍増しますよ。
正史『三国志』での劉備
陳寿(ちんじゅ)が編纂した正史『三国志』。
ここでの劉備は、現実的な政治家として描かれています。
劉備は、感情的になることもあり、時に冷酷な判断も下しました。
配下を上手く使い分ける統率力を持っていました。民衆への配慮は確かにありましたが、神格化されてはいません。
そのため、正史の劉備は、生き残るために奔走した実在の人物像です。
小説『三国志演義』での劉備
一方、明代に羅貫中(らかんちゅう)が著した『三国志演義』。
フィクションでは、劉備は完璧な君主として描かれます。
常に仁徳(じんとく)を重んじ、民を愛し、涙もろく情に厚い。
演義の劉備は、まさに理想化された英雄像となっているのです。
主な創作エピソード
演義で創作された有名なエピソード:
- 桃園の誓い:関羽・張飛との義兄弟の契り。史実では単なる部下関係でした
- 三顧の礼:諸葛亮を三度訪ねた話。実際の回数は不明です
- 長坂坡での趙雲の活躍:劉備の子を救う場面は演義で脚色されています
- 涙で民を思う描写:感情表現は演義で誇張されました
これらは、三国志の物語を面白くするための創作となっており、史実にはありません。
ただ、完全な嘘ではなく、史実の内容を基にして描かれています。
どちらも一面の真実
正史の冷静な政治家と、演義の理想的な君主。
果たして、どちらが本当の劉備でしょうか?
答えは「両方とも」です。
陳寿は功績を記録しましたが、性格描写は控えめです。
一方、羅貫中は民衆が求める英雄像を描きました。
そして、実際の劉備は、その中間にいたはずです。
人徳もあり、計算もできる人物、それが劉備の魅力を生んでいるんですね。
史実と創作、両方を知ることで劉備の本当の姿が見えてきます。



創作中心の三国志演義では、読者に楽しく読んでもらうことが重要なのでしょう。
まとめ
劉備玄徳は、草履売りから皇帝へと駆け上がった人物です。
161年に貧しい家に生まれ、223年に62歳で崩御するまで波乱の人生を送りました。
徐州を奪われ、各地を転々とする浮草のような日々。
しかし、諸葛亮(しょかつりょう)を得て、ついに蜀漢(しょくかん)皇帝に即位するのです。
そして、劉備の魅力は、何度倒れても立ち上がる不屈の精神です。
呂布に裏切られ、曹操に追われ、居場所を失っても諦めませんでした。
46歳で諸葛亮と出会い、人生が変わります。遅咲きの成功者として、三国志 劉備は希望の象徴なのです。
また、劉備から学べることは3つあります。
- 人を大切にする姿勢が最大の武器になること
- 失敗を恐れず挑戦し続ける勇気
- そして謙虚に学ぶ姿勢
現代のビジネスにも通じる、人間力の重要性を教えてくれますね。



劉備の人生は波乱万丈でしたけど、その仁徳は後世に語り継がれていますね。