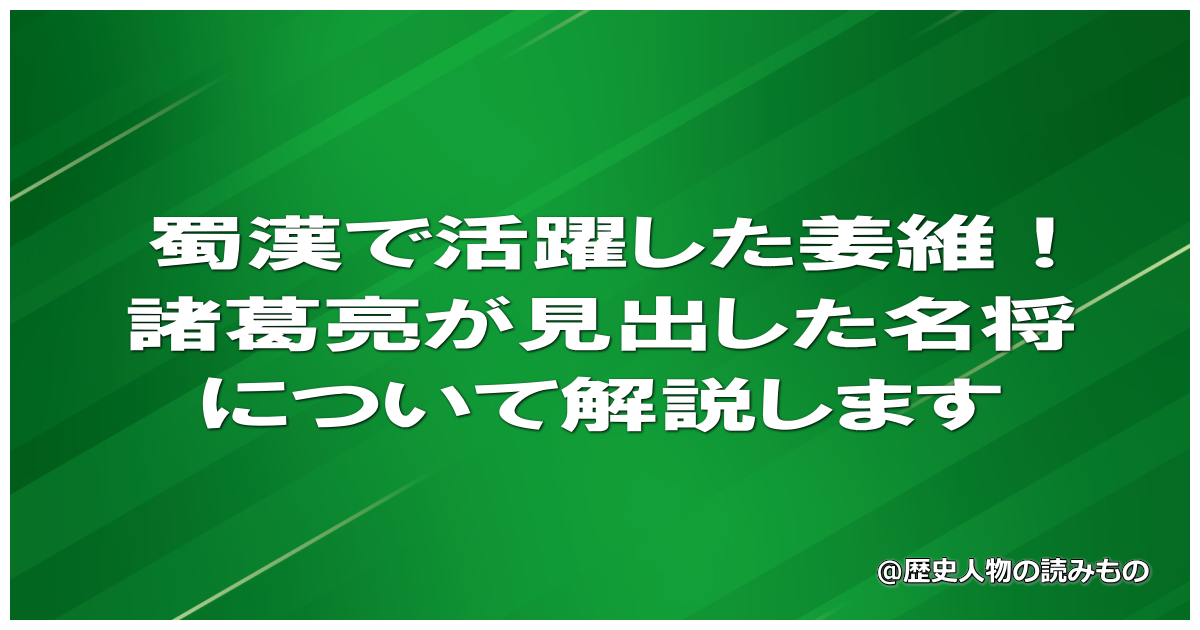歴男になりたい
歴男になりたい姜維ってあまり知らないんだけど、なにした人なの?



姜維が活躍した時代が知りたい
この記事では、こんな疑問にお答えしますね。
- 姜維の生涯年表(時系列)
- 姜維と諸葛亮との関係
- 北伐における姜維の戦略
- 姜維の最後と蜀漢滅亡との関係
- 姜維の歴史的評価


- 歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き


- 歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き
三国志には、多数の武将が登場しており、その中には諸葛孔明のような有名武将も多くいますよね?
その一方で、今回の記事で紹介する姜維のような、ちょっとマイナーだけど優れた才能を持った武将もいます。
そして、この姜維ですが、マイナーだけど文武両道でかなり優秀な武将だったのです。
そこで、当記事では蜀漢で活躍した姜維!諸葛亮が見出した名将について解説します。
姜維とは?諸葛亮が見出した蜀漢最後の名将


姜維は、三国志の時代に活躍した蜀漢の武将です。
涼州天水郡の出身で、元は魏に仕えていました。
しかし、運命的な出会いが、その後の彼の人生を変えます。
228年、諸葛亮の北伐によって蜀に降り、そこから蜀漢を支える柱となったんですね。
そして、諸葛亮亡き後は、大将軍として11回もの北伐を敢行し、蜀漢滅亡まで戦い続けました。
その忠義の心は、今なお多くの三国志ファンを魅了しています。
魏の官吏から蜀の将軍へ
姜維は若い頃、魏の天水郡で官吏として働いていました。
父を早くに亡くし、母に孝行を尽くす真面目な青年だったと伝えられています。
そして228年、諸葛亮が第一次北伐を開始すると、姜維の運命は大きく変わります。
諸葛亮の巧みな計略によって、姜維は上司から疑われ、やむなく蜀に降伏することになったのです。
ちなみに、この場面は正史と演義では描写が異なります。
演義では、姜維が自ら進んで蜀に帰順したように描かれますが、正史ではやむを得ない状況での降伏でした。
この違いを知ると、姜維という人物の難しさが見えてきますね。
諸葛亮が姜維を高く評価した理由
諸葛亮は、姜維を「涼州の上士(じょうし)」と呼びました。
これは、「涼州で最も優れた人物」という最高の賛辞です。
それでは、なぜ諸葛亮はそこまで姜維を評価したのでしょうか?
その理由は、姜維の多彩な才能にありました。
姜維という人物、兵法に通じ戦略眼があり、さらに学問的素養も高かったんです。
そして、諸葛亮は自分の死後、蜀漢を支える人材として姜維に期待をかけました。
「この者ならば、私の遺志を継いでくれる」という思いがあったのでしょう。



諸葛亮は、その知略だけではなく人の能力を見抜く力もありました。
姜維の生涯年表
姜維の63年間の人生を、時系列で振り返ってみましょう。
| 年代 | 年齢 | 出来事 |
|---|---|---|
| 202年 | 0歳 | 涼州天水郡に生まれる |
| 210年代 | 10代 | 父が戦死、母に孝養を尽くす |
| 220年代 | 20代 | 魏の天水郡で官吏として勤務 |
| 228年 | 27歳 | 諸葛亮の第一次北伐で蜀に降る |
| 229年 | 28歳 | 蜀で中監軍・征西将軍に任命される |
| 230-234年 | 29-33歳 | 諸葛亮の北伐に従軍、兵法を学ぶ |
| 234年 | 33歳 | 諸葛亮が五丈原で病没 |
| 238年 | 37歳 | 初の独自北伐を開始 |
| 244年 | 43歳 | 費禕と共に魏の侵攻を撃退 |
| 247年 | 46歳 | 洮西の戦いで魏軍を破る |
| 253年 | 52歳 | 費禕暗殺後、大将軍に昇進 |
| 255年 | 54歳 | 狄道を一時占領 |
| 256年 | 55歳 | 段谷の戦いで大敗 |
| 262年 | 61歳 | 最後の北伐、鄧艾と交戦 |
| 262年 | 61歳 | 宦官黄皓を避けて沓中に屯田 |
| 263年8月 | 62歳 | 魏軍侵攻、剣閣で鍾会を防ぐ |
| 263年11月 | 62歳 | 劉禅降伏、姜維も降る |
| 264年1月 | 63歳 | 鍾会と反乱計画、発覚し戦死 |
この年表を見ると、姜維の人生は228年の諸葛亮との出会いで完全に変わったことが分かりますね。
27歳で蜀に降ってから亡くなるまでの36年間、ほぼ全てを蜀漢のために捧げた生涯でした。
特に、234年の諸葛亮の死後、30年間も北伐を続けた執念には驚かされます。



諸葛亮亡き後30年間も蜀漢を守ったなんて、姜維はすごい人物ですね。



諸葛亮が後を頼んだわけなので、その能力は疑いようがないですね。
姜維の11回に及ぶ北伐と権力闘争


諸葛亮の死後、姜維は238年から262年まで、実に11回もの北伐を行いました。
なぜそこまで戦い続けたのでしょうか?
その第一の理由は、諸葛亮の遺志を継ぐという使命感です。
師が果たせなかった中原回復の夢を、自分が実現させたいという強い思いがあったんですね。
そして、第二に北伐は蜀漢の国是だったことが挙げられます。
攻撃こそ最大の防御という考えで、魏に圧力をかけ続けることで蜀の安全を守ろうとしたんです。
主な北伐の戦績
姜維の北伐は一進一退の連続でした。主な戦いを見てみましょう。
- 洮西(とうせい)の戦い(247年):魏の将軍郭淮を破り、勝利を収める
- 狄道(てきどう)攻略(255年):一時的に魏の領土を占領するも維持できず
- 段谷(だんこく)の戦い(256年):大敗を喫し、多くの兵を失う
- 侯和(こうわ)の戦い(262年):宿敵鄧艾と互角に戦う
これらの戦果を冷静に見ると、決定的な勝利は得られませんでした。
小規模な勝利はあっても、魏の根幹を揺るがすには至らなかったんです。
ちなみに、『三国志演義』では、姜維は諸葛亮の忠実な継承者として英雄的に描かれています。
しかし、正史では評価は厳しいものでした。
当時から「国力を考えない無謀な戦い」と批判されていたんですね。
戦場における武勇と知略
姜維が優れた武将として知られる理由の一つは、戦場での武勇と知略にあります。
彼は、若い頃から学問に優れており、その知識を戦術に生かしていました。
そして、諸葛亮の影響を受けたことで、戦局の全体を見渡す広い視野を持つようになりました。
その結果、それを基にした大胆な采配を行うことが出来たのです。
また、戦場での姜維は、知略のみならず自身の剣術や武力でも敵を圧倒しました。
有名な逸話では、姜維が自ら先陣に立ち、敵陣を切り崩したことが記録されています。
さらに、兵士たちからも高い信頼を受けており、彼の士気を高める能力は蜀軍にとって欠かせないものでした。
彼の特筆すべき戦略として「石兵八陣」や「胆力による威圧」が挙げられます。
この戦略は、敵を幻惑し戦場を混乱させる巧妙な戦略であり、限られた資源の中で大きな効果を発揮しました。
大将軍への出世と宦官黄皓との対立
253年、費禕が暗殺されると、姜維は蜀漢の軍権を完全に掌握しました。
大将軍に昇進し、軍事面での最高責任者となったんです。
しかし、宮廷内の状況は複雑でした。
その最大の敵は、宦官の黄皓だったんですね。
黄皓は劉禅の寵愛を受け、宮廷で専横を極めていたのです。
姜維は、黄皓の専横を批判し、何度も劉禅に排除を進言しました。
しかし、劉禅は黄皓を手放しませんでした。
結局、姜維は身の危険を感じて、沓中という辺境の地に屯田することを選びます。
都から離れて、農耕と軍備に専念したんです。
この決断が、後に蜀漢滅亡の一因となってしまいました。
姜維が都にいなかったことで、魏の侵攻に対する初動が遅れたのです。



中国史って、いつの時代も宦官の影響力が高いですよね?



宦官は悪知恵が働くイメージが強いですね。
蜀漢滅亡と姜維の最期
263年、魏は蜀漢を滅ぼすため大軍を送り込みました。
鍾会と鄧艾という二人の名将が、それぞれ別ルートから侵攻する作戦です。
これに対して、姜維は剣閣という要衝で鍾会の大軍を食い止めました。
この剣閣は、とても険しい山道で、少数でも守れる天然の要塞です。
姜維の防衛戦は見事で、鍾会は進めなかったんですね。
しかし、もう一方の将軍鄧艾が奇策に出ます。
険しい山道を強行突破し、成都の背後に回り込んだのです。
この予想外の奇襲に、蜀漢は全く対応することが出来ず、結果劉禅は降伏を決断してしまいました。
姜維の計略と壮絶な最期
降伏後も、姜維は諦めておらず、蜀漢復興の最後の賭けに出ます。
それは、鍾会を利用した反乱計画でした。
鍾会は野心家で、魏からの独立を考えていました。
姜維はこれを利用し、鍾会と共に反乱を起こして蜀漢を復活させようとしたんです。
しかし、計画は事前に発覚してしまいます。
魏軍の兵士たちがこの反乱を鎮圧して、鍾会も姜維も殺されました。
結果、姜維は妻子とともに討たれ、63年の生涯を閉じたのです。
姜維の忠義あふれる行動力
姜維は、鍾会の反乱失敗とともに命を落としましたが、その最期については詳しい記録が残されていません。
自然死であったとも、戦乱の中で悲劇的な最後を迎えたとも言われています。
確かなことは、彼が生涯を通じて蜀漢への忠誠を貫き、「漢の復興」を最終目標として戦い抜いたことです。
また、姜維の死は、蜀漢の最期を象徴する出来事とも言えます。
蜀の滅亡後、かつての蜀の将軍だった者たちの多くは魏によって寛大に処遇されました。
しかし、姜維はその道を選ばず、最後まで戦い抜いたのです。
姜維のこの強い忠義心は、後世においても語り継がれています。
このように、彼の生涯は、最期の時まで蜀のために奮闘し続けた英雄の姿そのものでした。



蜀漢の国力が弱くなっているにも関わらず、姜維は最後まで奮闘していたんですね。
姜維の歴史的評価について


姜維は、蜀漢の中でも才能あふれた武将だったことは疑う余地はありません。
ただ、その後の評価では、人によって異なっていることが分かります。
陳寿『正史三国志』での評価
『正史三国志』を書いた陳寿(ちんじゅ)は、姜維について微妙な評価を下しています。
「才能があり、軍事に優れていたが、時勢を読む力に欠けていた」という評価です。
つまり、能力は認めるが、戦略判断は間違っていたということですね。
特に、北伐政策については厳しい批判をしています。
「小国が大国に無謀な戦いを挑み続けた結果、国力を消耗させた」と指摘しているんです。
ただ、それでも陳寿は姜維の忠義の心は認めています。
主君への忠誠心、師への敬愛、これらは間違いなく本物だったと評価しました。
後世の歴史家たちの見解
後世の歴史家たちの評価は分かれています。
肯定的な評価をする人たちは、「姜維がいなければ蜀漢はもっと早く滅んでいた」と主張していますね。
姜維が、20年間蜀漢を支え続けた功績は大きいということです。
その一方で、否定的な評価をする人たちは、「姜維の無謀な北伐が蜀漢を滅ぼした」と批判しています。
もっと守りを固めていれば、蜀漢は生き延びられたかもしれないと考えるんです。
そして、現代の研究ではより客観的な評価が進んでいます。
姜維個人の責任というより、蜀漢という小国の構造的な問題が原因だったという見方が強まっているのです。
創作物での姜維像とは?
『三国志演義』では、姜維は理想化された武将として描かれています。
諸葛亮の忠実な弟子で、最後まで義を貫いた英雄というイメージですね。
そして、現代の漫画やゲームでも、姜維は人気キャラクターの一人です。
『三国志』のゲームでは高い能力値を持つ武将として登場することが多くなっています。



正史では微妙な評価ですが、三国志演義では英雄扱いされているんですよね。
姜維に関する疑問について
姜維については、後世の研究でも色々と疑問があるようです。
よくある疑問
- 姜維が蜀漢を滅ぼしたというのは本当?
-
部分的には事実ですね。姜維の北伐が国力を消耗させたのは確かですが、黄皓の専横、劉禅の政治的無能力、魏との国力差など、様々な要因が重なっていました。
- 諸葛亮と姜維、どちらが優秀だった?
-
総合的には諸葛亮の方が上です。政治・軍事・人材育成すべてで諸葛亮は卓越していました。ただ、姜維も優秀な武将で、諸葛亮が後継者として認めた実力は本物でした。
- 姜維の北伐は全て失敗だったの?
-
いいえ。小規模な勝利はいくつかありました。ただ、決定的な戦果は得られず、戦略目標の達成には至りませんでした。
まとめ
三国志に登場する姜維ですが、元々魏に仕えていた武将です。
それが、蜀漢の北伐により投降した結果、蜀漢の臣下となりその後諸葛亮と行動を共にします。
そして、諸葛亮との出会いが、その後の姜維の運命を変えて、最後まで武力や知略を駆使して蜀漢のために尽力しました。
姜維がいなければ、もっと早く蜀漢は滅亡していたと言われるほど、その功績は大きかったのです。



姜維は蜀漢の時代に登場し、最後まで蜀漢のために尽くした忠義心あふれる武将だったのです。