 歴史探偵女
歴史探偵女三国志演義ってよく聞くけど、中身はどうなっているの?



三国志演義には何が書かれているのか?
この記事では、こんな疑問にお答えしますね。
- 三国志演義とは何か(定義と基本情報)
- 正史『三国志』と三国志演義の決定的な違い
- 三国志演義が描く物語の全体像と流れ
- 三国志演義の成立背景と作者羅貫中について
- 物語の主要な登場人物とそれぞれの魅力
- 日本における三国志演義の受容と影響


- 歴史研究20年の歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き


- 歴史研究20年の歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き
三国志演義(さんごくしえんぎ)は、中国の明代に成立した歴史小説で、四大奇書のひとつに数えられる名作です。
劉備や諸葛亮の活躍を描いた物語として、日本でも江戸時代から親しまれてきました。
しかし「正史三国志との違いは?」「なぜこんなに人気なのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか?
そこで、当記事では、三国志演義の魅力を初心者にもわかりやすく解説していきますね。
三国志演義とは?基本情報を押さえよう
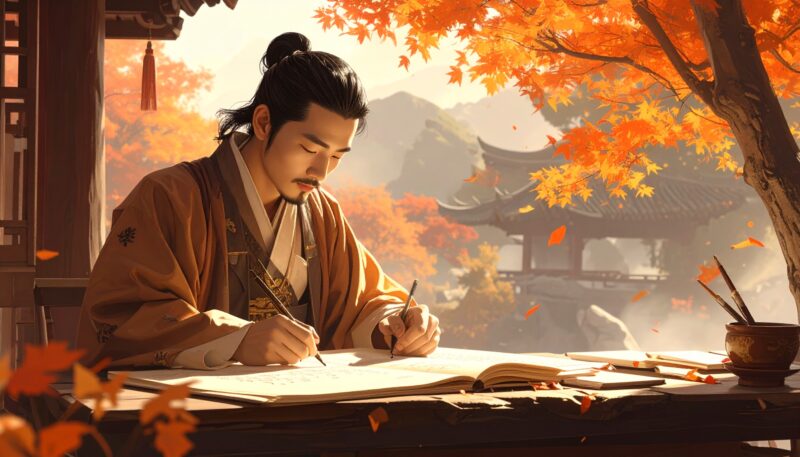
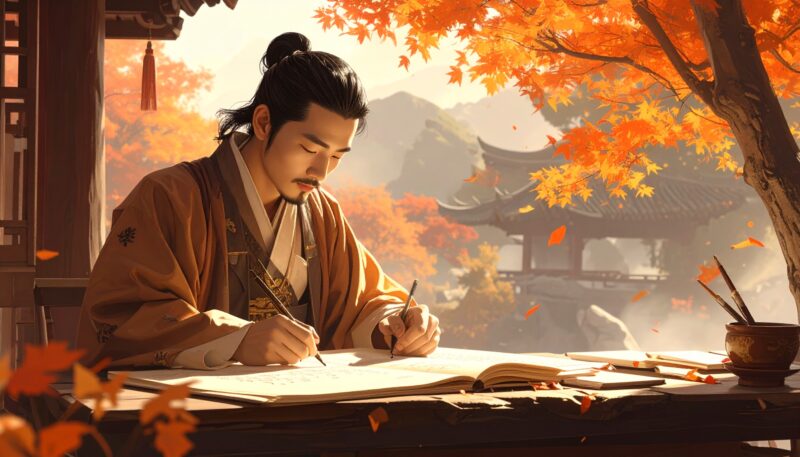
三国志演義は、中国の明代に成立した長編歴史小説であり、後漢末から三国時代を舞台に群雄たちの戦いを描いています。
そこで、まずはこの作品の基本的な情報から見ていきましょう。
四大奇書のひとつである歴史小説
三国志演義は、中国文学における「四大奇書(しだいきしょ)」のひとつです。
ちなみに、この四大奇書とは、明代から清代にかけて特に優れた作品として評価された4つの小説を指します。
四大奇書の作品
- 『三国志演義』(さんごくしえんぎ)
- 『水滸伝』(すいこでん)
- 『西遊記』(さいゆうき)
- 『金瓶梅』(きんぺいばい)
このうち三国志演義は、最も古く、最も多くの人々に愛された作品です。
また、現代の中国では金瓶梅の代わりに『紅楼夢(こうろうむ)』を加えて「四大名著」とも呼びます。
しかし、伝統的には『金瓶梅』を含めた分類が一般的ですね。
全120回の長編白話小説
三国志演義は、全120回(かい)から構成される長編小説です。
ちなみに、この「回」とは、章のようなもので、それぞれに見出しがついています。
例えば、第1回は「桃園に豪傑三人義を結び、黄巾賊を破って功を立てる」となっていますよ。
このように、各回の見出しを読むだけでも、物語の流れがわかる構成になっているのです。
また、三国志演義は「白話小説(はくわしょうせつ)」に分類されます。
この白話ですが、これは口語のことで、当時の庶民が話していた言葉で書かれているのです。
それまでの文学作品の多くは文語で書かれ、教養のある人しか読めませんでした。
しかし、三国志演義は庶民も楽しめる形で書かれた書物となっているのです。
「七分実事、三分虚構」の物語
清代の学者・章学誠(しょうがくせい)は、三国志演義の特徴を次のように評しました。
「七分実事、三分虚構(しちぶじつじ、さんぶきょこう)」、つまり7割が史実で3割が創作だというのです。
つまり、この絶妙なバランスこそが、三国志演義の最大の魅力と言えるでしょう。
その理由は、完全な史実では退屈になりがちですし、完全な創作では説得力を欠いてしまうからです。
三国志演義の構成要素
- 史実部分:正史『三国志』に基づく歴史的事実
- 虚構部分:民間伝承や作者の創作による脚色
- 文学性:洗練された文章と詩の引用
作者の羅貫中(らかんちゅう)は、歴史書を深く研究しながらも物語性を重視しました。
そのため、重要な戦いの結果や人物の生涯は史実通りですが、細かいエピソードは脚色されていますね。



三国志演義は娯楽小説でありながら、正史を基礎とした「七分実事、三分虚構」の絶妙なバランスが人気の秘密です。史実を知る読者も、初めて触れる読者も、それぞれの楽しみ方ができる作品と言えるでしょう。
正史『三国志』と三国志演義の決定的な違い
「三国志」という言葉には、実は2つの異なる作品が存在しています。
その一つが歴史書である正史『三国志』で、もうひとつが小説の三国志演義です。
そして、この違いを理解することが、三国志の世界を楽しむ第一歩となります。
正史は歴史書、演義は小説
まず、最も基本的な違いから見ていきましょう。
正史『三国志』
- 著者:陳寿(ちんじゅ)
- 成立時期:西暦280年以降(西晋時代)
- 性質:歴史書(記録)
- 立場:魏を正統王朝とする
正史『三国志』は、西晋の官僚だった陳寿が著した歴史書です。
「魏書」30巻、「蜀書」15巻、「呉書」20巻の全65巻から構成されています。
ちなみに、陳寿は蜀の出身でしたが、晋に仕えていたため魏を正統としました。
また、正史は人物の伝記形式で書かれており、客観的な記述を心がけて執筆されています。
ただし、陳寿は信憑性の低い史料を徹底的に排除したため、かなり簡潔な内容なんです。
そのため、後に裴松之(はいしょうし)が膨大な注釈をつけて内容を補いました。


三国志演義
- 著者:羅貫中(作者については諸説あり)
- 成立時期:元末明初(14世紀末~15世紀初)
- 性質:歴史小説(娯楽作品)
- 立場:蜀を正統王朝とする
一方、三国志演義は正史の約1000年後に成立した歴史小説です。
正史を基礎としながらも、民間伝承や作者の創作を大胆に取り入れています。
また、演義は娯楽作品として書かれているため、ドラマチックな展開が特徴ですね。
劉備を主人公とする「蜀漢正統論」
両者の最も大きな違いは、どの国を正統とするかという立場です。
正史は、魏を正統王朝として扱っているため、魏の歴代皇帝には「帝紀(ていき)」という項目が設けられています。
一方、演義は蜀漢(しょくかん)を正統とする立場を取っており、これを「蜀漢正統論(しょくかんせいとうろん)」と呼びます。
それでは、なぜ蜀を正統としたのか?その理由は、劉備が漢王朝の血筋を引いていたからです。
民衆にとって、400年続いた漢王朝は特別な存在でした。
そして、その血を引く劉備が正義の主人公として描かれることは、自然な流れだったのです。
そこで、この立場の違いにより、物語の描き方が大きく変わることになります。
三国志演義では劉備が善玉、曹操が悪玉として描かれているんですね。
キャラクター描写の違い
正史と演義では、同じ人物でも描かれ方が大きく異なります。
ここでは、代表的な例をいくつか見てみましょう。
劉備のイメージ
- 正史:野心家で、時には冷酷な判断も下す現実的な人物
- 演義:仁徳に満ちた理想的なリーダー、涙もろく優しい
曹操のイメージ
- 正史:優れた政治家・軍事家、文学にも秀でた才人
- 演義:権謀術数に長けた奸雄(かんゆう)、悪役として描かれる
諸葛亮のイメージ
- 正史:優れた政治家、軍事面では慎重派
- 演義:超人的な知謀を持つ天才軍師、神がかり的な活躍
例えば、演義で有名な「関羽が華雄を斬る」というエピソードがあります。
これは、「酒がまだ温かいうちに華雄を討ち取った」という劇的な場面です。
しかし、正史では華雄を討ったのは関羽ではなく、孫堅(そんけん)の軍でした。
また、演義では張飛(ちょうひ)が横暴な督郵(とくゆう)を鞭打つ場面があります。
これは、劉備の義侠心を示すための脚色であり、実際に督郵を打ったのは劉備自身でした。
演義では、劉備は理性的に張飛を止める役割になっているのです。
このように、演義では各キャラクターの役割を明確にするため、史実を大幅にに改変して描かれています。
比較表:正史と演義の主な違い
| 項目 | 正史『三国志』 | 三国志演義 |
|---|---|---|
| 性質 | 歴史書 | 歴史小説 |
| 著者 | 陳寿 | 羅貫中 |
| 成立時期 | 280年頃 | 14世紀末~15世紀初 |
| 正統性 | 魏を正統とする | 蜀を正統とする |
| 劉備 | 野心家・現実主義者 | 仁徳の理想的リーダー |
| 曹操 | 有能な政治家 | 権謀術数の奸雄 |
| 文体 | 簡潔な文語 | 読みやすい口語 |



演義が蜀を正統とした背景には、漢王朝の血を引く劉備への民衆の共感がありました。一方、正史は魏を継いだ晋の視点で書かれており、この立場の違いが両者の最大の相違点となっています。
三国志演義が描く壮大な物語


三国志演義は全120回という長大な物語ですが、大きく前半と後半に分けられます。
まず前半は、劉備たち義兄弟の活躍であり、次に後半は、諸葛亮の北伐が中心となっているのです。
劉備・関羽・張飛の義兄弟の活躍(第1回~第80回頃)
物語は、後漢末の混乱から始まり、西暦184年に張角(ちょうかく)率いる黄巾の乱が勃発しました。
この時、劉備・関羽・張飛の三人が桃園で義兄弟の契りを結びます。
「同年、同月、同日に生まれることを願わず、ただ同年、同月、同日に死なんことを願う」という有名な誓いですね。
演義では、この三人の絆が物語の根幹となっていますよ。
その後、劉備は徐州(じょしゅう)の牧となりますが、曹操に敗れて放浪します。
そして、この時期に劉備は諸葛亮という若き天才と出会うのです。
劉備は諸葛亮の庵を三度訪ねて、ようやく軍師として迎えることに成功します。
そして、この時に諸葛亮が示した「天下三分の計」が後の展開を決定づけました。
これは、天下を魏・呉・蜀の三国に分けて対抗するという、いわゆる天下三分の計という戦略ですね。
その後西暦208年、曹操は大軍を率いて南下し孫権の呉を攻めますが、劉備と孫権の連合軍が、赤壁の戦いで曹操を破りました。
演義では、諸葛亮の知謀が大活躍する場面として描かれていますよね?
東南の風を呼び寄せたという「借東風(しゃくとうふう)」のエピソードは特に有名です。
ただし、これは演義の創作で、正史にはこのような記録は一切ありません。
そして、赤壁の勝利後、劉備は益州(えきしゅう)を攻め取り、ついに蜀を建国します。
その後西暦221年、劉備は皇帝に即位し、漢王朝の復興を宣言したのです。
しかし、この頃から劉備の運命は暗転していくことになります。
関羽が呉の呂蒙(りょもう)に敗れて戦死し、張飛も部下に殺されてしまうのです。
そこで、義兄弟の死に激怒した劉備は、呉への復讐戦を開始します。
諸葛亮の反対を押し切って出陣した劉備ですが、陸遜(りくそん)に大敗します。
そして西暦223年、劉備は白帝城(はくていじょう)で病に倒れました。
そして、臨終の際に劉備は諸葛亮に後事を託し、息を引き取ります。
後半部分:諸葛亮の北伐と三国の統一(第81回~第120回)
劉備の死後、物語の主役は諸葛亮に移ります。
そして、諸葛亮は幼い皇帝・劉禅(りゅうぜん)を補佐し、蜀の国政を担いました。
そのために、まず諸葛亮は、南方の異民族・南蛮(なんばん)を平定します。


南蛮の王・孟獲(もうかく)を七度捕らえ、七度許すという逸話ですね。
そして、演義では諸葛亮の徳と知略を示す重要なエピソードとなっています。
ただし、正史では諸葛亮自身が南征に行った記録は明確ではありません。
その後、南方を平定した諸葛亮は、北伐を開始することになります。
これは、魏を討ち、漢王朝を復興させるという劉備の遺志を継ぐためです。
西暦228年から234年まで、諸葛亮は五度にわたり魏に侵攻しました。
この場面、演義では諸葛亮と魏の司馬懿(しばい)との知謀の戦いが描かれます。
空城の計や木牛流馬(もくぎゅうりゅうば)など、有名なエピソードが登場するのです。
しかし、西暦234年、五度目の北伐の最中に諸葛亮は五丈原の陣中にて病に倒れます。
「出師の表(すいしのひょう)」を残し、諸葛亮は54歳で世を去りました。
この場面は、三国志演義の中でも最も感動的な場面として知られていますよ。
そして、諸葛亮の死後、蜀は徐々に衰退していきます。
すると西暦263年、魏の将軍・鄧艾(とうがい)が蜀を攻め、劉禅は降伏しました。
その後、魏では司馬懿の一族が実権を握り、西暦265年に司馬炎(しばえん)が魏から禅譲を受けて晋を建国しました。
そして西暦280年、晋は三国の中で最後まで残っていた呉を滅ぼし、天下を統一したのです。
そこで、この物語は、「話説天下大勢、分久必合、合久必分(天下の大勢は、分かれること久しければ必ず合し、合すること久しければ必ず分かる)」という言葉で締めくくられます。



演義は劉備の仁徳と諸葛亮の智謀を軸に展開します。前半は義兄弟の絆、後半は天才軍師の奮闘という二部構成が、読者を最後まで引き込む構造になっていますね。壮大な時代の流れを感じさせる名作ですよ。
三国志演義はどのように生まれたのか?
三国志演義は、一人の作家が生み出した作品ではありません。
数百年にわたる民間伝承が積み重なり、最終的に羅貫中が完成させたのです。
そこで、ここでは演義成立の歴史的背景を一緒に見ていきましょう。
唐代から続く「説三分」の伝統
三国時代が終わった後も、人々は英雄たちの物語を語り継ぎました。
唐代(618年~907年)には、すでに三国志の物語が語られていた記録がありますよ。
当時の詩人、杜牧(とぼく)や李商隠(りしょういん)の詩には、三国志を題材とした作品が見られます。
また、杜甫(とほ)は諸葛亮を讃える漢詩を残しています。
つまり、当時から三国志の英雄たちは人々の憧れの対象だったのです。
そして、宋代(960年~1279年)になると、都市が発展し庶民文化が花開きました。
首都の開封(かいほう)や臨安(りんあん)には「瓦子(がし)」と呼ばれる盛り場ができます。
ちなみに、そこでは「勾欄(こうらん)」という寄席で、講釈師が物語を語っていました。
また、三国志の物語は「説三分(せつさんぶん)」と呼ばれ、特に人気があったようです。
宋の文人・蘇東坡(そとうば)は、その様子を記録していますね。
「講釈師が三国志を語ると、子供たちは劉備が負けると涙を流し、曹操が負けると大喜びする」というのです。
このように、すでに宋代には「劉備=善玉、曹操=悪玉」というイメージが定着していたことが分かりますよね。
元代の『三国志平話』から演義へ
元代(1271年~1368年)には、講談の内容を本にまとめた作品が登場します。
それが『全相三国志平話(ぜんそうさんごくしへいわ)』です。
ちなみに、「全相」とは「全ページ絵入り」という意味で、挿絵が豊富な本でした。
そして、元の至治年間(1321年~1323年)に刊行されたこの本は、演義の原型と言えます。
しかし、内容は荒唐無稽な部分が多く、史実との矛盾も目立ちました。
例えば、冒頭には冥界での裁判という怪談めいた話が入っていますね。
また、史実では劉備の孫の代で蜀は滅びますが、平話では劉備の子孫が敵討ちをする話が付け加えられていました。
こうした部分は、講談師が場を盛り上げるために創作したものと言えますね。
羅貫中による集大成
元末明初に登場したのが、羅貫中(らかんちゅう)という人物です。
彼は、『三国志平話』をもとに、正史を参考にしながら大幅に書き直しました。
ちなみに、この羅貫中については、詳しいことが分かっていません。
また、施耐庵(しないあん)という人物との関係も指摘されていますが、確証はありません。
ただ、膨大な歴史書を読み込んでいたことは確かと言えますね。
そこで、羅貫中は平話の荒唐無稽な部分を削除して、正史『三国志』だけでなく、『後漢書』『晋書』なども参考にしたのです。
また、裴松之の注釈から多くのエピソードを取り入れた結果、生まれたのが最初の『三国志演義』になります。
この三国志演義、平話と比べると分量は約10倍に増えましたが、物語としての整合性が保たれていたのです。
それと、現存する最古の版本ですが、明の嘉靖元年(1522年)の「嘉靖本」になります。
その後、多くの版本が登場しますが、現在広く読まれているのは「毛宗崗本(もうそうこうぼん)」です。
清の康熙年間(1662年~1722年)、毛綸(もうりん)・毛宗崗父子が校訂を行っています。
これは、文章をさらに洗練させ、120回の構成に整えたのです。
そして、現在日本で翻訳されているのも、その多くがこの毛宗崗本となっていますね。



三国志演義は、数百年にわたる民間伝承の集大成なんです。羅貫中は講談の荒唐無稽な部分を削り、正史で補強することで、エンターテインメントと史実のバランスを実現しました。世代を超えた集団創作の結晶と言えますね。
魅力あふれる登場人物たち


三国志演義には、約400人を超える人物が登場します。
しかし、その中でも特に印象的なのが、劉備・関羽・張飛の義兄弟と諸葛亮、そして曹操です。
そこで、ここでは、これら主要人物の魅力を掘り下げていきましょう。
義兄弟の絆・劉備・関羽・張飛
物語の中心となるのが、桃園の誓いで結ばれた三人の義兄弟です。
字(あざな)は玄徳(げんとく)。演義では、仁徳に満ちた理想的なリーダーとして描かれていますね。
漢王朝の皇族の血を引くとされ、その正統性が物語の軸となります。
そこで、劉備の特徴ですが、人を惹きつける魅力であり、関羽や張飛、諸葛亮といった優れた人材が、彼のもとに集まりました。
また、演義では涙もろく優しい性格として描かれていますが、正史ではもっと野心的な人物だったのです。
しかし、演義でも劉備は完璧な聖人ではありませんでした。
関羽の死後、復讐心に駆られて無謀な戦争を始めるなど、人間的な弱さも描かれています。
字は雲長(うんちょう)。武勇に優れた豪傑で、「義」を体現する人物として描かれます。
そこで、演義の関羽は、ほぼ完璧な武人として登場しますよ。
長い髭を持つ堂々とした姿で、青龍偃月刀(せいりゅうえんげつとう)を振るいます。
また、曹操に一時的に身を寄せた際も、劉備への忠義を貫き通したことは有名です。
ただ、正史では関羽の記述はそれほど多くありません。
しかし、羅貫中は関羽を理想の武人像として作り上げたのです。
その後、関羽は神格化され、関帝(かんてい)として祀られるようになりました。
字は益徳(えきとく)。豪快で一本気な性格の猛将です。
そして演義では、大声で敵を威嚇する場面が印象的となっています。
長坂橋(ちょうはんきょう)で曹操の大軍を一喝して退けたエピソードはかなり有名です。
ただし、酒癖が悪く、部下に厳しすぎるという欠点も描かれています。
また、正史によると、張飛は実は教養もあり、字も上手だったようです。
つまり、演義では荒っぽい武人として描かれていますが、実像はもう少し複雑だったのです。
天才軍師・諸葛亮(諸葛孔明)
諸葛亮(しょかつりょう)、字は孔明(こうめい)。
三国志演義における最大のヒーローといっても過言ではありませんね。
そこで、演義の諸葛亮は、ほぼ神がかり的な知謀を持つ天才として描かれています。
天文を読み、風を呼び、敵の罠を見抜き、完璧な戦略を立てる。
その活躍は、時に現実離れしていると思えるほどなんです。
諸葛亮の主な活躍
- 天下三分の計を提案
- 赤壁の戦いで東南の風を呼ぶ
- 空城の計で司馬懿を退ける
- 木牛流馬という兵器を発明
しかし、正史の諸葛亮はもう少し地に足のついた人物です。
優れた政治家でしたが、軍事面では慎重派であり、北伐でも大きな戦果を上げられず、志半ばで病死しています。
それでも、劉備への忠義と献身は正史でも高く評価されているのです。
また、「出師の表」という上奏文は、後世まで名文として伝えられました。
演義では、諸葛亮の活躍を大幅に脚色することで、理想的な忠臣像を作り上げたのです。
奸雄か英雄か・曹操
曹操(そうそう)、字は孟徳(もうとく)。
演義では悪役として描かれますが、実は最も複雑な魅力を持つ人物です。
そして、演義の曹操は「奸雄(かんゆう)」として登場しており、権謀術数に長け、目的のためには手段を選びません。
漢王朝を操り、献帝(けんてい)を傀儡とした人物として描かれますね。
しかし、演義でも曹操の能力の高さは否定されていません。
優れた軍事的才能や人材登用の巧みさ、決断力は正当に評価されています。
また、演義には曹操の人間的な魅力を示す場面もあり、部下への情の深さや文学への造詣の深さなどが描かれています。
そのため、単純な悪役ではなく、魅力的な敵役として描かれているのです。
ちなみに、正史の曹操はさらに評価が高くなっており、優れた政治家・軍事家であり、詩人としても一流でした。
特に、「短歌行(たんかこう)」という詩は、今でも名作として知られていますね。
主要人物の対比
| 人物 | 演義での描写 | 正史での実像 |
|---|---|---|
| 劉備 | 仁徳の理想的リーダー | 野心的で現実的な君主 |
| 関羽 | 完璧な武人、義の体現者 | 優れた武将だが記述は少ない |
| 張飛 | 豪快な猛将、荒っぽい性格 | 武勇に優れ、教養もあった |
| 諸葛亮 | 神がかり的な天才軍師 | 優れた政治家、軍事は慎重派 |
| 曹操 | 権謀術数の奸雄、悪役 | 卓越した政治家・軍事家・詩人 |



演義の登場人物は、単純な善悪二元論ではありません。劉備にも人間的な弱さがあり、曹操にも英雄としての魅力が描かれています。この複雑さこそが、千年以上愛される理由でしょう。各人物に共感できる余地があるのです。
日本における三国志演義の受容と影響
三国志演義は、中国だけでなく日本でも長く愛されてきました。
江戸時代から現代まで、時代ごとに新しい形で受け入れられていますよ。
そこで、ここでは日本における三国志演義の歴史を追っていきましょう。
江戸時代の『通俗三国志』
正史『三国志』は、遣唐使の時代にはすでに日本に伝わっていました。
『日本書紀』にも「魏志」からの引用があり、卑弥呼についての記述が見られます。
しかし、小説の三国志演義が日本に広まったのは江戸時代です。
江戸時代初期の儒学者・林羅山(はやしらざん)も、若い頃に三国志演義を読んでいました。
そして、元禄2年から5年(1689年~1692年)にかけて、『通俗三国志』全50巻という画期的な本が発行されます。
『通俗三国志』の特徴
- 訳者:湖南文山(こなんぶんざん)
- 実際は京都・天竜寺の僧、義轍(ぎてつ)と月堂(げつどう)兄弟のペンネーム
- 李卓吾本と呼ばれる版本を底本とした日本語訳
- 日本初の翻訳書のベストセラー
この『通俗三国志』は大ヒットし、近代まで読み継がれました。
講談、歌舞伎、浮世絵など、様々な形で三国志が広まっていったのです。
また、江戸後期には、歌川国芳(うたがわくによし)が三国志の錦絵を描きました。
さらに、1836年から刊行された『絵本通俗三国志』は、絵入りの決定版として大ブームを巻き起こします。
このように、三国志は日本の大衆文化に深く根付いていったのです。
吉川英治から横山光輝へ
戦後日本で最も影響力のあった三国志は、吉川英治(よしかわえいじ)の小説です。
昭和14年(1939年)から昭和18年(1943年)まで、新聞に連載されました。
この吉川英治ですが、『通俗三国志』を基に、自由な翻案で物語を再構築したのです。
吉川英治『三国志』の特徴
- 読みやすい日本語で書かれた歴史小説
- 演義を比較的忠実に翻案
- 人物描写に深みを持たせた
- 戦後も多くの読者に愛された
このように、吉川版『三国志』は、日本人の三国志イメージを決定づけました。
そして、この吉川版を原作とした作品が次々と生まれることになります。
その中でも、最も有名なのが、横山光輝(よこやまみつてる)の漫画『三国志』です。
これは、1971年から1987年まで連載され、全60巻という大作となりました。
横山光輝『三国志』の影響
- 漫画で三国志を知った世代を生み出す
- わかりやすい絵柄で歴史への入門書に
- 現在でも新装版が刊行され続けている
この2つの作品により、三国志は日本で不動の人気を確立したのです。



日本では江戸時代から三国志演義が愛され、時代ごとに新しい形で受容されてきました。現代でも親しまれており、演義の物語は今なお日本文化に深く根付いています。その普遍的な魅力は色褪せませんね。
まとめ
三国志演義は、正史『三国志』を基にしながらも、民間伝承を取り入れて大胆に脚色された歴史小説です。
元末明初に羅貫中によって完成され、劉備・関羽・張飛の義兄弟と諸葛亮の活躍を中心に、後漢末から三国時代の群雄割拠を描いています。
そこで、演義最大の特徴は、蜀を正統とする立場で劉備を善玉、曹操を悪玉として描いた点です。
しかし、単純な勧善懲悪ではなく、各人物に複雑な人間性を持たせることで、千年以上にわたって世界中で愛される作品となりました。
また、日本でも江戸時代から親しまれ、現代まで様々な形で受容されています。
このように、三国志演義は史実とフィクションが織りなす壮大な物語として、これからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。



三国志演義の真の価値は、歴史の正確さではなく、人間ドラマの普遍性にあります。忠義、友情、野心、挫折などなど、時代を超えて共感できるテーマが、この作品を不朽の名作たらしめているのです。
