 歴史探偵女
歴史探偵女三国志にはどんな武将がいたんだろう?



三国志の武将ランキングを教えて!
この記事では、こんな疑問にお答えしますね。
- 蜀の主要な武将
- 魏の主要な武将
- 呉の主要な武将
- 武将人気ランキングTOP10


- 歴史研究20年の歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き


- 歴史研究20年の歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き
三国志は、今から約1800年前の中国で起きた壮大な歴史ドラマです。
当時の英雄たちが、天下統一を目指して戦った時代が描かれています。
武力に優れた武将や知力を備えた武将など、各武将にはそれぞれ特徴があるんですよね。
そこで、当記事では三国志武将一覧完全ガイドと題して、蜀・魏・呉の名将を読み方付きで解説します。
三国志とは?武将たちが活躍した時代背景


後漢末期から三国時代への流れ
時は西暦184年、中国を支配していた後漢王朝が大きく揺らぐ事件が発生します。
それは、黄巾の乱(こうきんのらん)と呼ばれる農民反乱が発生したからです。
そして、この反乱をきっかけに、各地で群雄が割拠する時代が始まります。
その結果、後漢の皇帝は権力を失い、実権は有力な武将たちに移っていくのでした。
まずは、董卓(とうたく)という暴君が宮廷を掌握します。
すると、民衆の混乱はさらに深まり、 各地の武将たちは自分の勢力を拡大するために戦い続けたんですね。
そこで、この混乱の中から、かの有名な曹操、劉備、孫権という三人の英雄が現れます。
彼らは、徐々に仲間を増やしていき、約40年にわたる戦いの末、中国は三つの国に分かれることになったのです。
魏・呉・蜀の三国はどう生まれたか
西暦220年、曹操の息子である曹丕(そうひ)が魏を建国しました。
この魏は、中国北部の広大な領土を支配する、三国志の時代において最大の勢力だったのです。
首都は洛陽(らくよう)に置かれ、中華全土の約70%の領土を有していました。
そして、その翌年には劉備が蜀(しょく)の皇帝として即位します。
場所は、現在の四川省を中心とした地域で、中華全体の約10%の領土を保有していたのです。
首都は成都(せいと)に置かれ、周りを険しい山に守られた天然の要塞国家でした。
その後、孫権は西暦229年に呉(ご)を建国し、自らを皇帝として名乗ります。
長江流域の豊かな地域を支配し、中華全土の約20%の領土を持っていました。
首都は建業(けんぎょう、現在の南京)で、長江周辺の国家という事もあり、水軍の強さが特徴でしたね。



三国時代は、中国史上初めて三人の皇帝が並び立った異例とも言える時代でした。それぞれの国が異なる特徴と戦略を持ち、約40年間にわたって激しい外交戦と軍事衝突を繰り広げていたのです。
蜀(しょく)の主要武将一覧【劉備と五虎大将軍】


蜀は、三国の中で最も小さな国でしたが、とても魅力的な武将が揃っていました。
仁義を重んじる劉備のもとに、義に厚い豪傑たちが集まったんです。
そこで、ここでは蜀を代表する名将たちをご紹介していきますね。
君主・劉備玄徳とその特徴
劉備は、蜀漢(しょくかん)の初代皇帝となった人物です。
三国志の中でも義に熱い人物として有名なので、知らない人はいないでしょう。
そして、劉備は漢王室の末裔(まつえい)を名乗り、正統性を主張しました。
彼は、人徳と義理を重んじる性格で、多くの人材を惹きつけていたのです。
また、若い頃は貧しく、草履(ぞうり)売りをしていたとされます。
ちなみに、演義では、関羽と張飛と義兄弟の契りを結ぶ「桃園の誓い」が有名。
ただし、正史には桃園の誓いの記録はありませんが、三人の絆は本物だったようですね。


さらに、諸葛亮を三度訪ねた「三顧の礼(さんこのれい)」も有名なエピソードですよね。
劉備の謙虚な姿勢が、天才軍師諸葛亮を味方につけることに成功したのです。




しかし、最期は関羽の仇討ちに失敗し、失意のうちに63歳で亡くなっています。
劉備の生涯年表
- 161年:涿郡(たくぐん)で誕生
- 184年:黄巾の乱で関羽・張飛と挙兵
- 201年:荊州の劉表のもとに身を寄せる
- 208年:赤壁の戦いで曹操を破る
- 214年:益州を平定し、勢力を拡大
- 221年:蜀漢の皇帝として即位
- 222年:夷陵の戦いで呉に大敗
- 223年:白帝城で病死(63歳)


五虎大将軍(関羽・張飛・趙雲・馬超・黄忠)
関羽は、劉備の義弟として生涯忠誠を尽くした武将として有名です。
演義では、「武神」として描かれており、後世には神格化されています。
美しい髭(ひげ)を持ち、武勇と義理を兼ね備えた理想的な武将像として物語の中に君臨しています。
ちなみに、正史でも優れた武将として記録されており、単独で軍を率いていたようです。
そして、樊城(はんじょう)の戦いでは、魏の于禁(うきん)を降伏させる大戦果を挙げています。
しかし、呉の呂蒙(りょもう)の策略により、219年に捕らえられ処刑されてしまうのです。
関羽を失ったことは、蜀にとって致命的な損失となり、荊州(けいしゅう)という重要拠点も無くしてしまいます。
張飛は、豪快かつ勇猛な武将として知られています。
演義では、粗暴な性格として描かれますが、実際は書画にも優れていたようです。
大きな声と、その圧倒的な武力で、敵を震え上がらせたと伝えられます。
そして、長坂橋(ちょうはんきょう)の戦いでは、一人で曹操軍を退けたとされます。
演義では、「張飛ここにあり!」と一喝し、敵将が恐怖で落馬したという逸話があります。
ただし、この場面は演義の創作ですが、張飛の勇猛さを示す象徴的なエピソードとして有名ですね。
しかし、最期は配下に裏切られて亡くなってしまうのです。
関羽の仇討ちを急ぐあまり、部下に厳しくしすぎたことが原因で、享年は56歳前後と推定されています。
趙雲は、蜀の五虎大将軍の一人に数えられる名将ですね。
冷静沈着で、劉備の護衛として長年活躍しています。
演義では、完璧な武将として描かれおり、最後まで敗北知らずだったようです。
そして、長坂の戦いでは、劉備の子である阿斗(あと、後の劉禅)を救出したエピソードがありますね。
この功績により、劉備の絶大な信頼を得ることになりました。
ちなみに、正史でも勇敢でかつ慎重な将軍として高く評価されています。
また、演義では90歳近くまで現役で戦ったとされますが、これはあきらかに誇張と思われます。
実際の享年は不明ですが、おそらく70歳前後だったと考えられているようです。
趙雲は、最期まで品行方正な人物として、後世の模範とされました。
馬超は、西涼(せいりょう)の名門武将の出身です。
彼は、若い頃から武勇に優れ、「錦馬超(きんばちょう)」と称されました。
また、演義では、曹操と激しく戦った勇猛な武将として描かれています。
この馬超ですが、父である馬騰(ばとう)が曹操に斬られると、復讐のため挙兵します。
そして、馬超は快進撃を続けて、一時は曹操を追い詰めるほどの活躍を見せました。
しかし、最終的に敗れてしまい、劉備のもとに身を寄せることになります。
その後、蜀に加わった後は、主に名声による威圧効果で貢献していたようです。
正史でも、実際の戦闘での活躍は限定的だったとされており、47歳の若さで病死しています。
黄忠は、高齢でありながら、驚異的な武勇を発揮した武将として有名です。
演義では、60歳を超えても第一線で活躍する老将として描かれていますね。
また、黄忠は弓の名手としても知られ、百発百中の腕前を誇りました。
そして、定軍山(ていぐんざん)の戦いでは、魏の名将・夏侯淵(かこうえん)を討ち取りました。
この戦功により、五虎大将軍の一人に列せられており、正史でも勇猛な将軍として評価されています。
ちなみに、演義では75歳で戦場にて亡くなったとされますが、実際の年齢は不明です。
恐らく、60代後半から70代前半だったと推測されており、老いてなお衰えぬ武勇は多くの人々に勇気を与えました。
軍師・諸葛亮孔明と蜀の文官たち
諸葛亮は、三国志で最も有名な軍師と言えますよね?
劉備に「三顧の礼」で迎えられ、天下三分の計を献策しています。
また、赤壁の戦いでは、呉との同盟を成功させ、曹操を破りました。
そして、劉備亡き後は、息子の劉禅(りゅうぜん)を支えて国政を取り仕切ります。
蜀漢を守るために、北伐(ほくばつ)と呼ばれる魏への攻撃を何度も行いました。
しかし、北伐の途中、五丈原(ごじょうげん)の戦いにおいて、54歳で亡くなっています。
ちなみに、「出師の表(すいしのひょう)」という文章は、忠義の象徴として有名ですよね。
それと、演義では、様々な奇策を用いる天才軍師として描かれています。
ただし、木牛流馬(もくぎゅうりゅうば)や八陣図などは演義の誇張なんです。
龐統は、諸葛亮と並び称された天才軍師ですね。
当時、龐統は「鳳雛(ほうすう)」という異名で知られていました。
ただ、あまり容姿が優れなかったため、最初は劉備に重用されなかったんです。
しかし、徐々にその才能が認められると、軍師中郎将に任命されます。
そして、益州攻略戦で重要な献策を行いましたが、 36歳の若さで亡くなりました。
ちなみに、演義では諸葛亮と対比される形で登場していますね。
「伏龍(ふくりゅう)と鳳雛、一人を得れば天下を安んず」という言葉が有名ですよ。
法正は、蜀の重要な策士として活躍しました。
元々は、劉璋(りゅうしょう)に仕えていましたが、それを見限って劉備に仕官します。
そして、益州平定と漢中攻略で重要な役割を果たしました。
また、定軍山の戦いでは、黄忠とともに夏侯淵を討つ作戦を立てています。
劉備からの信頼は非常に厚く、諸葛亮と並ぶ扱いを受けました。
その後、45歳で病死しますが、その才能は高く評価されていたんですね。
ちなみに、後に諸葛亮は「法正が生きていれば、夷陵の敗戦は防げた」と述懐しています。
この言葉からも、いかに法正が重要な人物だったのかが分かりますよね。
蜀の主要武将一覧(読み方・特徴)
蜀の武将たちの特徴を一覧でご紹介します。
- 劉備(りゅうび):蜀の初代皇帝、仁徳の人
- 諸葛亮(しょかつりょう):天才軍師、忠義の象徴
- 関羽(かんう):義の武将、後に神格化
- 張飛(ちょうひ):豪傑、勇猛果敢な武将
- 趙雲(ちょううん):完璧な武将、劉備の護衛
- 馬超(ばちょう):西涼の猛将、錦馬超
- 黄忠(こうちゅう):老いてなお盛んな勇将
- 龐統(ほうとう):鳳雛、諸葛亮に並ぶ軍師
- 魏延(ぎえん):勇猛な将軍、反骨の相
- 姜維(きょうい):諸葛亮の後継者、北伐を継承



蜀の武将たちは、義理と忠義を重んじる気風で統一されていますね。五虎大将軍に代表される武将たちは、それぞれ異なる個性を持ちながらも、劉備への忠誠で結ばれていましたのです。
魏(ぎ)の主要武将一覧【曹操と最強軍団】


魏は、蜀や呉も合わせた三国の中で、最大の勢力を誇っていた国です。
曹操のもとに、多くの優秀な人材が集まり、武将も軍師も粒揃いの、まさに最強軍団だったのです。
覇王・曹操孟徳の魅力
曹操は、魏の実質的な建国者とも言えます。
ただ、彼は宦官(かんがん)の孫という出自のため、若い頃は軽んじられていたんです。
しかし、彼はその卓越した才能で、乱世を勝ち抜いていくことになります。
まずは、三国志の始まりとも言える黄巾の乱の鎮圧で頭角を現し、その後勢力を拡大していきます。
そして、かの有名な官渡(かんと)の戦いでは、10倍の兵力を持つ袁紹(えんしょう)を破りました。
また、荀彧の提言により献帝(けんてい)を保護し、「天子を奉じて諸侯に号令す」という戦略を取ります。
ちなみに、演義では悪役として描かれますが、実際は優れた政治家だったのです。
彼は、人材登用に長けており、能力さえあれば出自を問わず採用していました。
曹操の生涯年表
- 155年:沛国譙県(はいこくしょうけん)で誕生
- 184年:黄巾の乱で活躍
- 192年:兗州(えんしゅう)を平定
- 196年:献帝を迎え入れる
- 200年:官渡の戦いで袁紹を破る
- 208年:赤壁の戦いで敗北
- 216年:魏王となる
- 220年:洛陽で病死(66歳)
魏の五将軍と猛将たち
張遼は、魏の五将軍の筆頭とされる名将です。
元々は呂布(りょふ)に仕えていましたが、呂布が捕らえられた後に曹操に降りました。
そして、合肥(ごうひ)の戦いでは、800の兵で孫権の10万の軍を撃退しています。
800しかいない兵力で10万の軍を退けたのですから、それはもはや神がかっていますよね。
そのため、この戦いで「江東の子供たちは張遼の名を聞いて泣き止む」と言われました。
また、正史でも演義でも、張遼は一貫して高く評価されています。
その後も病を押して最後まで戦い続け、54歳で亡くなりました。
ちなみに、曹操は張遼を「古の召虎(しょうこ)のごとし」と称賛しています。
彼は武勇だけでなく、冷静な判断力も兼ね備えた理想的な将軍だったのです。
徐晃は、堅実な戦いぶりで知られる名将です。
関羽が樊城を包囲した際、これを撃退するという、大きな功勲をあげています。
そのため、曹操から「徐将軍は孫子・呉起(ごき)の再来だ」と絶賛されました。
ちなみに、徐晃は派手さはありませんが、確実に戦果を挙げる、曹操にとって理想的な武将だったのです。
規律を重んじ、私情を挟まずに任務を遂行し、長年にわたり魏に貢献しています。
また、演義でも関羽と互角に戦える実力者として描かれていますね。
地味ですが、とても信頼できる、まさに職業軍人の鏡のような人物だったのです。
張郃は、元々袁紹に仕えていた武将です。
ただ、官渡の戦いで袁紹を見限って曹操に降りました。
そして、彼は諸葛亮の北伐に対して、何度も防衛戦を戦い抜きます。
特に、街亭(がいてい)の戦いでは、蜀の馬謖(ばしょく)を破る大勝利を収めます。
そのため、諸葛亮が最も警戒した魏の将軍の一人でした。
しかし231年、諸葛亮の撤退を追撃中、伏兵に遭い亡くなりました。
ちなみに、曹操は張郃を「韓信(かんしん)、彭越(ほうえつ)の輩だ」と評価しています。
これは、漢の名将に例えた最高級の賛辞と言えますね。
夏侯惇は、曹操の従兄弟で最も信頼された武将の一人です。
若い頃から曹操に従い、生涯忠誠を尽くしました。
そして、戦闘で片目を失うという負傷を負いますが、最前線で戦い続けた勇猛な武将です。
ちなみに、演義では矢で射抜かれた目を自ら食べたという逸話があります。
しかし、この話は演義の創作ですが、彼の豪胆さを象徴していると言えますね。
また、曹操からは特別な待遇を受けており、自由に出入りできる特権がありました。
武将としてより、信頼できる一族として重宝されたのが伺えますよね。
許褚は曹操の護衛を務めた、かなりの怪力の持ち主です。
身長は八尺(約184cm)で、虎のような風貌だったと伝えられており 「虎痴(こち)」という名称で呼ばれていました。
そして、彼は赤壁の戦い前、馬超が曹操に会見を求めた際に同席します。
その席で、馬超の暗殺計画を察知し、睨みつけて阻止したとされます。
また、戦場においては曹操の命を何度も救った、忠実な護衛だったのです。
ちなみに、演義では、関羽や馬超と互角に戦う豪傑として描かれます。
知略よりも、純粋な武力と忠誠心で貢献した武将でしたね。
荀彧・郭嘉ら天才軍師たち
荀彧は、曹操の覇業を支えた天才軍師です。
「王佐の才(おうさのさい)」と称され、戦略面で大きく貢献しました。
そして、官渡の戦いでは、曹操に籠城を勧めて大勝利に導いています。
また、彼は人材推薦にも優れ、多くの優秀な人材を曹操に紹介しました。
郭嘉、鍾繇(しょうよう)、荀攸(じゅんゆう)などがその良い例です。
まさに、荀彧は魏の人材集団を作った立役者と言えるでしょう。
しかし、曹操が魏公になることに反対し、その関係が悪化していきます。
その結果、最期は謎に包まれて亡くなっていますが、これには色々な諸説があります。
とにかく、荀彧は漢王朝への忠義を最後まで貫いた、気高い知識人だったのです。
漢王朝ということであれば、曹操よりも劉備が良かったと思いますが、これも運命だったのでしょう。
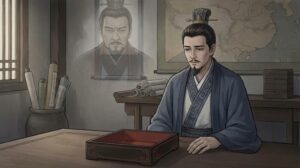
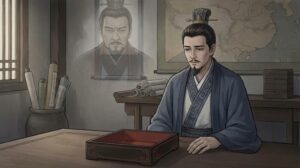
郭嘉は、曹操が最も信頼した軍師の一人です。
彼は「鬼才」と呼ばれており、敵の心理を見抜く洞察力にとても優れていました。
それは、官渡の戦いでも発揮され、袁紹軍の弱点を的確に指摘しています。
また、北方の烏丸(うがん)討伐にも従軍し、見事に平定したのです。
しかし、彼はこの遠征で体調を崩し、38歳の若さで病死しています。
当時、曹操は郭嘉の死を深く悲しみ、何度も彼を惜しんだと記録されています。
「郭嘉が生きていれば、赤壁の敗北はなかった」と曹操は嘆いたのです。
これは、曹操にとって郭嘉の存在がいかに大きかったのかが分かりますね。


司馬懿は、魏の後期を支えた名軍師ですね。
蜀漢の諸葛亮と何度も対峙しており、持久戦で相手を疲弊させました。
そして、五丈原の戦いでは、諸葛亮の挑発に乗らず徹底的に守りを固めます。
その結果、諸葛亮の死後には蜀の侵攻を完全に防ぎ切ったのです。
その後は、魏の政治の実権を握って、重臣として君臨することになります。
後に、その孫である司馬炎(しばえん)が、晋(しん)王朝を建国しました。
ちなみに、演義では、諸葛亮の引き立て役として描かれがちですが、実際は極めて優秀で慎重な戦略家でした。
「死せる孔明、生ける仲達を走らす」という言葉は有名ですよね。
魏の主要武将一覧(読み方・特徴)
魏の武将たちの特徴を一覧でご紹介します。
- 曹操(そうそう):魏の実質的建国者、覇王
- 司馬懿(しばい):諸葛亮と対峙した名軍師
- 張遼(ちょうりょう):合肥の英雄、五将軍筆頭
- 徐晃(じょこう):堅実な名将、関羽を破る
- 張郃(ちょうこう):諸葛亮が警戒した武将
- 夏侯惇(かこうとん):曹操の従兄弟、隻眼の将
- 許褚(きょちょ):怪力の護衛、虎痴
- 荀彧(じゅんいく):王佐の才、人材発掘の達人
- 郭嘉(かくか):鬼才の軍師、曹操の懐刀
- 夏侯淵(かこうえん):曹操の従弟、勇猛な将軍



魏の武将たちは、実力主義で選ばれた精鋭揃いでした。曹操が「唯才是挙(ゆいさいぜきょ)」という方針で、出自に関わらず有能な人材を登用したため、多様な才能が集まったんですね。
呉(ご)の主要武将一覧【孫権と江東の虎】


呉は、長江流域を支配した水軍の強国であり、孫一族三代にわたる建国の物語が魅力的ですね。
そして、呉では個性的で勇猛な武将たちが多く活躍しました。
孫一族の歴史(孫堅・孫策・孫権)
孫堅は、呉の基礎を築いた武将です。
その存在は、「江東の虎」と恐れられ、勇猛果敢な戦いぶりで知られました。
彼は、黄巾の乱や董卓討伐で大きな功績を挙げています。
特に、反董卓連合では最も積極的に戦い、洛陽に一番乗りしたのです。
ちなみに、演義では、皇帝の璽(じ、印鑑)を密かに手に入れたとされます。
ただ、この話は演義の創作で、正史には記録がありません。
そして、孫堅は37歳の若さで戦場にて亡くなってしまいます。
もし彼が長生きしていれば、天下の情勢も変わっていたかもしれませんが、これも運命なのでしょう。
しかし、その勇猛さは、確実に息子たちに受け継がれていきました。


孫策は「小覇王(しょうはおう)」と称された名将ですね。
父の孫堅が亡くなると、その配下を率いてすぐに独立します。
そして、わずか数年で江東(こうとう)地域を平定したのです。
また、孫策は勇猛さと人望を兼ね備え、その元には数多くの人材が集まります。
特に、周瑜(しゅうゆ)とは幼なじみで、生涯の親友だったのです。
しかし、順調に勢力を拡大していた孫策でしたが、26歳という若さで亡くなってしまいます。
ちなみに、演義では刺客から受けた傷が原因で若くして亡くなったとされます。
これは、正史でも刺客によるものと記されていますが、詳細は不明です。
「死するとき、孫策の帳中の人、皆号泣せり」と記されています。
孫権は、呉の初代皇帝となった人物です。
兄の孫策から19歳という若さで家督を継ぎ、70歳まで長期間統治しました。
そして、赤壁の戦いでは劉備と同盟し、曹操を破る大勝利を収めています。
また、彼は人材登用に優れ、周瑜、魯粛(ろしゅく)、呂蒙、陸遜と続く名将を育てました。
内政面でも手腕を発揮しており、江南地域の開発に尽力して呉を安定させました。
しかし、晩年は後継者問題で宮廷が混乱してしまい、結果多くの人材を失います。
結局、71歳で崩御するまで激動の時代を生き抜いたのです。
周瑜・陸遜ら名将たち
周瑜は、呉の大都督として活躍した名将です。
孫策とは幼なじみで、「断金の交わり」と称される親友でした。
また、彼は美男子で音楽にも造詣が深く、「曲に誤りあれば、周郎顧みる」という言葉があります。
そして、赤壁の戦いでは、火攻めの計を立案し大勝利を収めています。
この時の黄蓋(こうがい)の苦肉の策や、龐統の連環の計も彼の作戦でした。
ちなみに、演義では諸葛亮の活躍が強調されますが、実際は周瑜が主導しています。
その後、益州攻略を計画中、36歳の若さで亡くなっています。
呉にとって、周瑜の損失は大きな痛手であり、多くの人が悲しんだと言われています。
陸遜は、呉の後期を支えた名将ですね。
若い頃は、文官として活躍していましたが、武将としても徐々に頭角を現します。
そして、夷陵(いりょう)の戦いで、劉備の大軍を火攻めで破りました。
結果、この勝利により、呉は蜀の侵攻を完全に退けたのです。
これは、陸遜の戦略眼と冷静な判断が光った重要な一戦になりました。
彼は、その後も北方の魏と対峙し、長期にわたって国境を守り続けます。
しかし、晩年は孫権と対立してしまい、失意のうちに63歳で亡くなったのです。
陸遜は、冷静沈着で知略に優れており、三国志の中でも名将中の名将でした。
魯粛は、呉の外交を担った重要な人物です。
曹操が南下してきた際には、劉備との同盟を主張し、赤壁の戦いでの連合を実現させます。
そして、周瑜が亡くなった後には、大都督として呉を支えました。
ちなみに、演義では間抜けな人物として描かれることがありますが、これは大きな誤りです。
実際には、優れた戦略家であり、「天下二分の計」を献策しています。
また、孫権からの信頼も厚く、重要な決定に関与しました。
生存中は、劉備との関係維持に努めており、結果蜀呉同盟を保ちました。
その後、46歳で病死しますが、その功績はとても大きなものでした。


太史慈・甘寧ら個性派武将
太史慈は、武勇に優れた呉の将軍です。
弓の名手として知られ、黄忠と同じく百発百中の腕前を誇りました。
また、孫策と一騎討ちを行い、互角に渡り合ったことは有名は話ですね。
この戦いの後、太史慈は孫策に心酔して配下となります。
その後は、生涯を通じて忠誠を尽くし、各地で武勲を挙げました。
そして、41歳で病死する際には、「大丈夫、馬革に屍を包むべし」と言い残します。
ちなみに、太史慈は演義でも正史でも、一貫して勇猛な武将として描かれています。
最期まで戦場で活躍したいという思いを持ち続けており、武人としての矜持を貫いた、気高い人物だったのです。
甘寧は、「呉に甘寧あり」と恐れられた猛将ですね。
若い頃には、盗賊のような生活をして生計を立てていたとされています。
そして、呉に仕えてからは、その勇猛さで多くの戦果を挙げました。
百騎での夜襲を得意とし、敵陣に混乱を招いたこともあります。
また、曹操軍との戦いでも、大胆な奇襲で勝利を収めています。
ちなみに、その性格は荒々しく、部下に対しても厳しかったとされます。
しかし、義理堅い一面もあり、とても仲間を大切にしました。
彼の最期の詳細は不明ですが、おそらく50代で亡くなったと推測されます。
とにかく豪快で勇敢な、典型的な武将と言えますね。
黄蓋は、呉の古参武将で、孫堅の時代から仕え、三代にわたって忠誠を尽くしました。
特に、赤壁の戦いでの「苦肉の策」が有名ですよね。
ちなみに、演義では、周瑜に殴打されて曹操を欺く役を演じました。
しかし、正史では、黄蓋が自ら降伏を偽装する策を提案したとされます。
そして、火船で曹操軍に突入し、大勝利に貢献したんですね。
かれは、長年の経験と功績から、多くの人々に尊敬されていました。
若い時から高齢まで、現役で活躍した叩き上げの武将であり、地道な努力と忠誠心で、呉を支え続けたのです。
呉の主要武将一覧(読み方・特徴)
呉の武将たちの特徴を一覧でご紹介します。
- 孫堅(そんけん):江東の虎、呉の基礎を築く
- 孫策(そんさく):小覇王、江東を平定
- 孫権(そんけん):呉の初代皇帝、長期統治
- 周瑜(しゅうゆ):赤壁の英雄、美男の名将
- 陸遜(りくそん):夷陵の戦いで劉備を破る
- 魯粛(ろしゅく):外交の達人、蜀呉同盟の立役者
- 太史慈(たいしじ):弓の名手、孫策と互角に戦う
- 甘寧(かんねい):呉に甘寧あり、猛将
- 黄蓋(こうがい):苦肉の策、赤壁の功労者
- 呂蒙(りょもう):関羽を討った武将、学問に励む



呉の武将たちは、個性豊かで勇猛な人物が多いのが特徴です。孫一族三代が築き上げた人材ネットワークは強固で、周瑜から陸遜へと続く名将の系譜は見事ですね。
三国志人気武将ランキングTOP10


ここで、三国志の武将たちの中で、特に人気が高い人物をご紹介しますね。
各サイトやブログによる評価や、歴史的な評価を基にした独自のランキングとなっています。
このランキング内に、あなたのお気に入りの武将は入っているでしょうか?
武将ランキング
第1位:諸葛亮(しょかつりょう)
圧倒的な人気を誇る天才軍師で、劉備への忠義と数々の奇策が人々を魅了し続けています。
また、演義では、ほぼ完璧な人物として描かれていることが分かります。
ちなみに、諸葛亮は、「三顧の礼」や「出師の表」などのエピソードが有名ですね。
第2位:関羽(かんう)
義理と武勇を兼ね備えた理想的な武将であり、 劉備への忠誠心と、「義」を貫く姿勢が多くの共感を呼んでいます。
また、演義では、ほぼ無敗の最強武将として登場しますね。
ちなみに、関羽は「千里行(せんりこう)」や「単騎駆け」などのエピソードが有名です。
第3位:曹操(そうそう)
曹操は、複雑かつ魅力的な人物として、現在でも人気の高い武将です。
演義では、悪役として描かれますが、実際は優れた政治家だったようです。
ちなみに、「乱世の奸雄(かんゆう)」という評価が有名ですが、詩人としての一面もあります。
第4位:趙雲(ちょううん)
三国志武将の中でも完璧な武将として、特に若い世代に人気がある趙雲。
長坂の戦いでの阿斗救出が、最も有名なエピソードであり、 演義では最後まで敗北知らずの名将として描かれています。
冷静沈着かつ品行方正な人物像が魅力で、 劉備への忠誠心も厚く理想的な武将と言えます。
第5位:劉備(りゅうび)
仁徳の君主として根強い人気があり、人々を思いやる優しさと、諦めない姿勢が感動を呼んでいます。
「桃園の誓い」や「三顧の礼」など、有名なエピソードも数多くあります。
また、演義では完璧な善人として描かれていますが、実際はもっと複雑かつ魅力的な人物だったと考えられています。
第6位:呂布(りょふ)
「飛将」と称された、三国志の中でも最強の武将と言えます。
演義でも正史でも、その強さは一貫して描かれていますが、裏切りを繰り返したため、その評価は複雑なんです。
また、「人中の呂布、馬中の赤兎」という言葉が有名であり、その圧倒的な武力は多くの人を魅了し続けています。
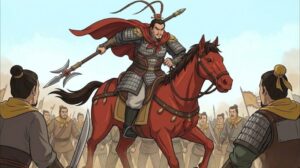
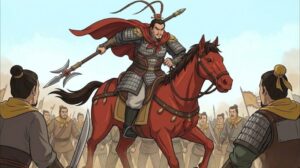
第7位:張飛(ちょうひ)
豪快で人間味があふれており、個性派ランキングでも上位に来そうな武将です。
演義での粗暴なキャラクターが、かえって親しみを生んでいますが、実際は書画にも優れた教養ある人物でした。
そして、張飛は関羽とともに劉備の義弟として活躍し、「虎髭(こしゅ)将軍」という異名でも知られていました。
第8位:姜維(きょうい)
諸葛亮の後継者として蜀を支えた武将で、最後まで北伐を続けて理想を追い求めました。
元々は魏の武将でしたが、諸葛亮に見出されて蜀に降っています。
彼は、武勇と知略を兼ね備えた優秀な人材であり、その献身的な姿勢が多くのファンの心を掴んでいます。
第9位:張遼(ちょうりょう)
魏の名将として人気があり、合肥の戦いでの大活躍が有名ですね。
また、正史でも演義でも、張遼は一貫して高評価を受けており、「江東の子供たちは張遼の名を聞いて泣き止む」という言葉が象徴的です。
そして、戦場では着実に戦果を挙げる、武勇と冷静さを兼ね備えた理想的な将軍と言えますね。
第10位:周瑜(しゅうゆ)
美男の名将として人気があり、赤壁の戦いでの活躍が最も有名ですね。
また、演義では諸葛亮に嫉妬する役回りですが、実際はかなり優れた戦略家でした。
文武両道の人物であり、孫策との友情も美しく描かれています。



人気ランキングを見ると、義理や忠誠心を重んじる武将が上位を占めていますね。諸葛亮や関羽のような「完璧な人物」への憧れと、曹操のような「多方面な人間」への共感が入り混じっているのが興味深いです。
まとめ
三国志の武将たちは、それぞれに個性と魅力があふれています。
蜀の義理堅い武将たち、魏の実力主義の精鋭、呉の個性的な猛将たち。
当時は、これら三つの国が異なる特徴を持ちながら、激しく競い合いました。
また、正史と演義では描写が異なる部分もありますが、どちらも魅力的に映りますね。
歴史の真実と、物語としての面白さ、両方を楽しめるのが三国志の醍醐味と言えます。
この記事で、あなたのお気に入りの武将は見つかりましたか?



三国志に登場する武将には、それぞれ個性がありとても魅力的ですよね?特に、諸葛亮や関羽、劉備や曹操など、この時代を彩った武将はとても印象深いです。
