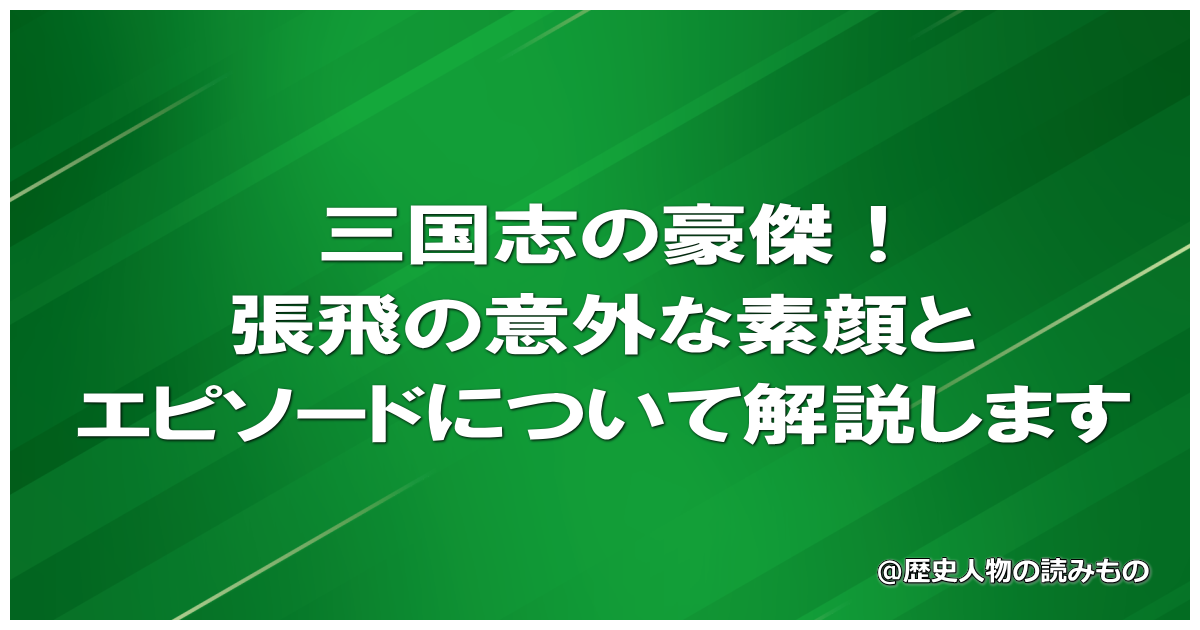歴男になりたい
歴男になりたい張飛って結局どんな人物だったの?



張飛の武勇伝が知りたい
この記事では、こんな疑問にお答えしますね。
- 張飛と桃園の誓い
- 三国志正史と三国志演義での描写の違い
- 張飛の主な武勇伝
- 実際の張飛の人物像
- 張飛の最期


- 歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き


- 歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き
三国志の張飛と言えば、劉備や関羽とともに、桃園の誓いを行った人物として有名です。
また、その武力はもちろん酒豪としても知られる張飛。
ただ、その素顔については、あまり知られていないようですね。
そこで、当記事では三国志の豪傑!張飛の意外な素顔とエピソードについて解説します。
張飛とはどんな人物だったのか?


張飛は、幽州涿郡(現在の河北省)出身で、字(あざな)を益徳といいます。
彼の生年は正確に伝わっていませんが、乱世の中でその武勇を示し、蜀漢の将軍として大きな役割を果たしました。
ちなみに、家系や出生について、詳細な記録は多く残されていません。
ただ、生まれた環境が戦乱の中にあったことから、早い段階で武術や格闘術に触れていたのではないかと考えられています。
そして、張飛は二人の息子(張苞・張紹)と二人の娘をもうけ、彼らもまた蜀漢の歴史に深く関与することになります。
桃園の誓いに見る兄弟関係
三国志において、欠かせないエピソードの一つが、「桃園の誓い」です。
この誓いは、劉備と関羽、そして張飛が義兄弟の契りを結んだ出来事として知られています。
張飛は、三兄弟の中で最年少でありながら、兄弟関係において非常に強い絆を持っていた人物です。
ただ、正史において「桃園の誓い」の具体的な記述は見られません。
しかし、『三国志演義』で描かれるこのエピソードが、以降の物語で三兄弟の結束を象徴するものとなりました。
そして、張飛は劉備を兄として尊敬し、関羽を家族同然に慕いました。
その純粋で実直な性格が、三人の間に強い信頼関係を築かせたのです。
特に戦場では、兄である劉備を守るため、あるいは関羽と共に敵陣を駆け抜け、数多くの勝利に貢献しました。
この義兄弟の関係性は、三国志全体の重要なテーマとも言えるでしょう。
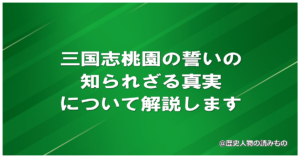
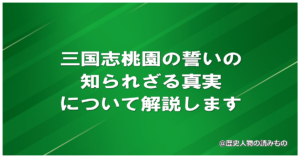
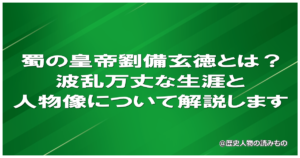
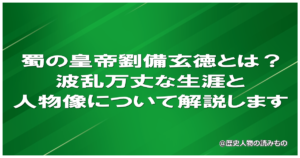
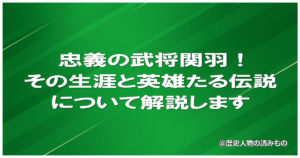
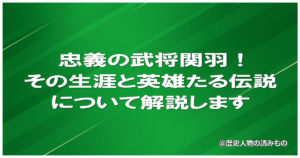
豪傑のイメージとその実像
張飛という人物は、豪傑としてのイメージが非常に強くなっています。
三国志演義では、虎のようなヒゲ、豹のような堂々たる頭、雷鳴のごとき声といった容姿や性格の特徴がかなり強調されています。
このような表現の影響もあって、世間では「猛々しい英雄」という印象が強いです。
しかし、正史の『三国志』では、彼は単なる豪傑ではなく、知略にも長けた人物であったことが分かります。
例えば、勇猛果敢なだけでなく、敵将の厳顔を説得して自陣に取り込むというエピソードがあります。
また、張飛は酒好きで短気とされていますが、その裏には忠義心や深い家族愛があったことも指摘されています。
正史と『三国志演義』の違い
正史である『三国志』と、物語として脚色された『三国志演義』では、張飛に対する描写に違いが見られます。
三国志演義では、張飛は勇ましさが際立ち、一騎当千の武将として描かれています。
特に「長坂橋の戦い」での孤高の戦いぶりなど、豪傑としての張飛像がかなり強く強調されています。
また、正史では、彼が厳格で几帳面な性格を持っていたことや、部下への態度が厳しすぎたことが記録されています。
実際、彼の最後は部下の恨みを買ったことによるものなので、豪傑であるが故の欠点や弱点も記されています。
これらのことから、張飛という人物像には多面的な解釈が可能であることが分かります。
民衆に愛された張飛
張飛は、数多くの民衆からも愛された英雄の一人です。
その理由の一つとして、彼の率直で親しみやすい性格が挙げられます。
彼の行動や言動は、時に乱暴に映ることもありました。
ただ、それがかえって人間らしさを感じさせ、多くの人々に親近感を抱かせました。
例えば、張飛を題材にした民間伝承や京劇などが生まれた背景には、彼の人間味豊かなエピソードがあったからだとも言われています。
また、彼の生い立ちや豪快さは、当時の庶民の心を掴んでいたと記録されています。
劉備や関羽と共に苦難を乗り越えた姿は、乱世において励ましとなり、後の世にも語り継がれることとなったのです。



桃園の誓いでの劉備、関羽、張飛のエピソードは有名ですよね。
戦場で輝いた張飛の武勇伝
張飛は、武力のイメージが強く、数々の戦場で大きな成果を挙げています。
長坂橋の戦いで曹操軍を退ける
三国志における張飛の代表的なエピソードとして語られるのが、長坂橋での壮絶な戦いです。
この戦いは、蜀の劉備が曹操軍から逃走する際、劉備の家族や民衆を守るために張飛が単騎で橋を守った場面として知られています。
この時、張飛はわずか二十数騎の兵士を引き連れ、数千もの曹操軍に立ち向かいました。
彼は橋の上に立ち、敵に向かって怒声を上げると、雷のようなその声と気迫だけで曹操軍を怯ませたのです。
その結果、曹操軍の追撃を食い止めることに成功したと伝えられています。
このエピソードは、『三国志演義』に強調されて描かれています。
ただ、正史である『三国志』でも、長坂坡の戦いにおける張飛の活躍は記録されています。
この長坂橋の戦いを通じて、張飛の勇猛さと冷静な判断力が広く知られるようになりました。
そして、この時の彼の行動は、武将としての誇りと兄弟を守る強い意思を象徴しています。
戦略家としての巴中の戦い
張飛といえば、豪傑としてのイメージが強く語られますが、彼は戦略家としても有能な一面を持っていました。
その一例として挙げられるのが、巴中の戦いです。
巴中は、現在の四川省のあたりに位置し、蜀漢にとって重要な地域でした。
そして、張飛はこの戦いで巧妙な戦略を駆使し、大きな勝利を収めています。
この戦闘で張飛は、敵軍の隊列を見極め、的確なタイミングで攻撃を仕掛けることで、最小限の被害で大軍を打ち破りました。
張飛は、その豪快な武勇だけではなく、冷静な判断力と知略によって蜀漢の防衛に大きな役割を果たしたのです。



張飛に策略が使えたなんて、びっくりです。



張飛は武力だけではなく、ちょっとした策略も使えたようですね!
意外な素顔、張飛の人物像とは?


張飛は豪傑として有名ですが、実は意外な素顔を持っていたと言われています。
張飛は実はマジメで几帳面だった?
三国志の豪傑として知られる張飛は、乱暴で怒りっぽい性格が強調されがちです。
ただ、実は几帳面でマジメな一面もあった人物と言われています。
正史や伝承によれば、張飛は書をよくたしなみ、部下の指導や軍隊の規律にも細やかな気配りを見せていたようです。
そのため、酒癖が悪いという評判とは裏腹に、戦場や普段の統治の場では整然とした組織運営を行っていたことが分かります。
また、彼は武人としてだけでなく、芸術を愛する気質も持ち合わせていたと言われています。
特に、書の才能に秀でており、その筆遣いは非常に力強く、張飛がただの武人的な豪傑ではなかったことを物語っています。
酒癖の悪さとそのエピソード
張飛は、三国志の中でも酒好きとして有名な人物であり、その酒癖の悪さがしばしばエピソードとして語られています。
特に、小説『三国志演義』の中では、酒に酔った勢いで部下を厳しく叱責したり、無茶苦茶な命令を下したりする姿が描かれています。
その中で最も有名なのが、張飛が大失態を犯してしまった下邳城での出来事です。
この時、張飛は酒に溺れて職務をおろそかにした隙を呂布に突かれ、城を奪われてしまうのです。
このように、酒が張飛の短所となる場合もありましたが、それでも張飛は部下たちに恐れられながらも慕われる存在でもありました。
家族や部下に対する接し方
家族や部下に対する張飛の接し方にも、彼の意外な一面を垣間見ることが出来ます。
彼が家族に対しては非常に優しく、特に娘の敬哀皇后をとても大切にしていたと言われています。
また、息子である張苞や張紹にも、戦乱の中で生きる覚悟を教えながら愛情を注いだとされています。
また、部下に対しては規律を重んじて厳しく接したこともありました。
飲酒の影響で、時に怒りに任せた言動が記録されていますが、それでも張飛の本心は部下を大切に思う気持ちに溢れていたとされています。
そのため、張飛が統率する兵士たちは常に秩序正しく動き、そのリーダーシップに従っていました。
このことからも、彼が単なる武人ではなく、統治者としての素質も備えていたことが分かります。



張飛に几帳面な一面があったことに驚きです。



武力だけでは部下を率いることは出来ませんからね。
張飛の最期とは?
大酒豪として知られる張飛ですが、彼の最後はこの酒が原因だったのです。
部下に裏切られた豪傑の悲劇
張飛の生涯は、数々の豪傑エピソードに彩られていますが、彼の最期はとても悲劇的なものでした。
221年、張飛は孫権率いる呉を討伐する準備を進めていました。
この時、彼の暴虐な振る舞いや気が短い性格が引き起こした悲劇が待ち受けていました。
張飛は、部下である張達と范彊に「三日以内に白装束を用意しろ」という命令を出します。
これに対して、張達と范彊は何とか延期してもらえないかと張飛に懇願したのです。
しかし、張飛はこの時酒に酔っており、二人に暴行を加えた上で、「間に合わせることができなかったら斬る」と脅されました。
そこで、張達と范彊はこの仕打ちに耐え切れず、なんと張飛の首をはねてしまったのです。
その後、張飛の首は孫権のもとへ送られるという結果を迎えました。
この事件は、豪傑・張飛が自らの性格の影響によって落命してしまった悲劇として語り継がれています。
張飛の死が蜀に与えた影響
この張飛の死は、蜀漢に大きな影響を与えました。
劉備にとっては、最も信頼してきた義兄弟の一人を失うこととなり、その後の呉への討伐計画にも多大な影響を与えることとなります。
そして、この一件により蜀陣営の結束力が削がれ、劉備自身も後の夷陵の戦いで大きな敗北を喫することに繋がったと言われています。
また、張飛の死によって蜀漢は優れた武将だけでなく、彼の持つ威圧的な存在感や軍勢の士気を高める象徴をも失ったのです。
どのように後世で語り継がれているのか
張飛の存在は、後世に至るまでさまざまな形で語り継がれています。
三国志演義では、彼の勇猛果敢な姿や豪放な性格が強調され、大衆の記憶に深く刻み込まれています。
また、正史においては、張飛はただの豪傑ではなく策略も持ち合わせた将として記録されています。
このような二面性が、張飛を物語のキャラクターとして非常に魅力的なものにしているのです。



最後は酒に酔って部下に裏切られるなんて、悲惨な最後でしたね。
まとめ
三国志の張飛ですが、豪傑でありながらも几帳面という一面を持っていた武将です。
桃園の誓いで、劉備や関羽と義兄弟になってからは、ともに戦場を駆け抜けて大きな戦果を挙げました。
ただ、大酒豪で酒癖の悪さから、数々の失敗をしており、その最後も酒に酔っての乱暴なふるまいが原因となったのです。
とは言え、張飛は三国志ファンからは親しみやすいキャラクターとして存在しています。



張飛は、数々の戦場で大きな戦果を挙げており、蜀漢には欠かせない人物だったのです!