 歴史探偵女
歴史探偵女正史三国志ってなに?



演義と正史って何が違うの?
この記事では、こんな疑問にお答えしますね。
- 正史三国志が「正しい歴史」ではない衝撃的理由
- 陳寿が蜀出身なのに魏を正統とした複雑な事情
- 演義と正史で全く異なる10大エピソード比較
- 劉備・関羽・張飛・曹操・諸葛亮の実像と虚像
- 裴松之の注釈が正史を変えた理由
- 日本だけの三国志(吉川英治の創作)
- 初心者が読むべき順番とおすすめ版本


- 歴史研究20年の歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き


- 歴史研究20年の歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き
三国志といえば、劉備・関羽・張飛の義兄弟が活躍する物語を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、それはあくまでも、小説『三国志演義』の世界なんです。
その一方で、陳寿が著した『正史三国志』は史実を重視した歴史書で、演義とは全く異なります。
さらに言えば、この正史三国志も完全に正確な記録ではないのです。
そこで、当記事では、正史の特徴や演義との違いや10の具体的エピソード比較、人物像の徹底分析まで初心者にも分かりやすく解説しますね。
正史三国志と三国志演義の基本的な違い


三国志には「正史」と「演義」という二つの顔があります。
まずは、それぞれの基本的な特徴を理解していきましょう。
陳寿と羅貫中という二人の著者
正史三国志は、西晋(せいしん)の官僚だった陳寿(ちんじゅ)が280年以降に編纂した歴史書です。
陳寿は元々、蜀(しょく)に仕えていた人物でしたが、蜀が滅亡した後、晋に仕えることになります。
そして、この立場の変化が、正史三国志の内容に大きな影響を与えることになるのです。
その一方、三国志演義は明代(14世紀)に羅貫中(らかんちゅう)がまとめた歴史小説です。
これは、陳寿の正史から約1000年も後に書かれました。
そして羅貫中は、それまで民間で語り継がれていた三国志の物語を集め、洗練された小説として完成させたのです。
つまり、正史は三国時代直後の記録、演義は1000年後の創作物ということになります。
「正史=正しい」ではない?
「正史」という言葉を聞くと、「正しい歴史」と思われがちですが、実際には「正統な歴史書」という意味なんです。
中国では王朝が交代すると、前王朝の歴史を編纂する習慣がありました。
そしてこれが、「正史」と呼ばれる公式の歴史書というわけです。
しかし、正史だからといって全てが史実というわけではありません。
ちなみに、陳寿は史実を重視する姿勢で知られていました。
彼は、信憑性の薄い史料を徹底的に排除し、確かな記録だけを残そうとしたのです。
そのため、正史三国志は非常に簡潔な内容となっています。
ただし、当時陳寿にも政治的な立場がありました。
晋に仕える官僚として、晋の前身である魏(ぎ)を正統な王朝として描く必要があったのです。
このため、呉(ご)や蜀に対しては、やや冷淡な記述も見られますね。
「70%史実、30%虚構」という評価の根拠
三国志演義は、清代の史家から「七分の史実に、三分の虚構」と評されています。
これは演義が、大筋では史実に基づきながらも、巧みに創作を織り交ぜているという意味なんです。
ちなみに、演義の基本的なストーリーは正史に沿って描かれています。
官渡(かんと)の戦いや赤壁(せきへき)の戦いといった大きな出来事は、実際に起こったことです。
しかし、その戦いの詳細な描写や人物のエピソードには、多くの創作が含まれていますよ。
特に、諸葛亮(しょかつりょう)の神算鬼謀(しんさんきぼう)を描いた場面や、関羽(かんう)の義の物語は、演義で大きく脚色されています。
つまり、羅貫中は物語として面白くするために、史実を土台にしながらドラマチックな展開を加えたんですね。



正史と演義は対立するものではなく、相補う関係にあります。正史は骨格を提供し、演義は血肉を与えました。これら両方を知ることで、三国志の世界はより立体的に見えてきますよ。
陳寿の複雑な立場—蜀出身者が魏を正統とした理由
陳寿という人物を理解することは、正史三国志を読み解く鍵となります。
それは、彼の複雑な立場が、この歴史書の特徴を形作っているからです。
蜀滅亡と晋への仕官という矛盾
陳寿は233年、蜀の巴西郡(はせいぐん)で生まれました。
若い頃は蜀に仕え、歴史編纂の仕事に携わっていたとされていますよ。
ただ、263年に蜀は魏に滅ぼされてしまい、陳寿はその後、魏を継いだ晋の官僚となりました。
つまり、今までは蜀に仕えていた人物が、蜀を滅ぼした側の歴史書を書く。
この矛盾した状況が、正史三国志の微妙なバランスを生み出していますね。
そして、陳寿は正史三国志を書くにあたり、魏を正統な王朝として扱う必要がありました。
それは、晋が魏から禅譲(ぜんじょう)を受けて成立した王朝だったからです。
しかし、それと同時に、陳寿は蜀への思い入れも持っていたはずなんですよね。
そのため、正史には蜀の人物に対する温かい視線も随所に見られていますよ。
特に、諸葛亮に対する評価は、非常に高いものとなっているのです。
魏書・呉書・蜀書の扱いの微妙な違い
正史三国志は、魏書(ぎしょ)・呉書(ごしょ)・蜀書(しょくしょ)の三部構成です。
しかし、この三つの扱いには明確な違いがありますね。
それは、魏書だけが「帝紀(ていき)」という皇帝の記録を持っているんです。
これは、魏だけを正統な王朝と認めているという意味であり、呉や蜀の君主は、正式な皇帝としては扱われていません。
そのため、正史では孫権(そんけん)や劉備(りゅうび)は、魏の臣下という位置づけなのです。
ただし、陳寿は魏・呉・蜀の三国をそれぞれ独立した書として記述しました。
これは、当時としてはかなり画期的なことであり、陳寿の工夫が見て取れますね。
ちなみに、通常であれば、正史は勝者の記録だけを詳しく書き、敗者は簡単に触れる程度になります。
ですが、陳寿は三国の歴史を比較的公平に記録しようとしたのです。
そこで、正史三国志の構成ですが、魏書30巻、呉書は20巻、蜀書は15巻という分量になっています。
魏が最も詳しく、蜀が最も簡潔であり、これは各国の存続期間や記録の多さを反映していると考えらますね。
裴松之の注釈が補った重要な史実
正史三国志を語る上で欠かせないのが、裴松之(はいしょうし)の注釈です。
裴松之は、南朝宋の官僚で、429年に詳細な注釈を正史に加えました。
この理由としては、陳寿の簡潔すぎる記述を補うためです。
ちなみに、裴松之の注釈は、正史本文の3倍以上の分量があります。
彼は200以上の史料を引用し、陳寿が省略した逸話やエピソードを大量に追加しました。
そのため、現在私たちが知っている三国志の多くの話は、実は裴松之の注釈から来ているのです。
例えば、三国志の有名なエピソードの一つに「三顧の礼(さんこのれい)」がありますよね?
これは、劉備が諸葛亮の草庵(そうあん)を三度訪ねたという話です。
そして、陳寿の本文ではこの話は非常に簡潔にしか書かれていません。
しかし、裴松之の注には、より詳しい描写が含まれているのです。
また、裴松之は陳寿の記述に対して批判的なコメントも加えています。
これにより、正史の内容を多角的に検討できるようになったんですね。



陳寿の立場の複雑さは、正史三国志に独特の深みを与えています。蜀への愛着と魏への忠誠、この二つのバランスが、公平さを目指す姿勢につながったのかもしれません。裴松之の注釈がなければ、私たちの知る三国志は随分と違ったものになっていた可能性が高いですね。
衝撃!演義と正史で全く異なる10大エピソード


ここからは、演義と正史で大きく異なる具体的なエピソードを見ていきますね。
実は、この両者では驚くべき違いがたくさんあるのです。
諸葛亮の「藁船で矢を借りる」は孫権の功績
演義での最も有名な場面の一つが「藁船借箭(わらぶねしゃくせん)」です。
赤壁の戦い直前、周瑜(しゅうゆ)が諸葛亮に10日以内に10万本の矢を用意せよとの無謀な命令をします。
しかし諸葛亮は、「10日もいりません、3日でやります」と答えます。
そして諸葛亮は、藁束を積んだ船で曹操軍に近づき、霧に紛れて矢を射させることで10万本の矢を手に入れました。
この神がかった知略が、諸葛亮の天才性を象徴する場面とされていますね。
ところが、正史を見ると驚くべき事実が分かりますよ。
このエピソードの元となった出来事は、実は孫権がやったことだったのです。
正史によれば、赤壁の戦いの後、濡須(じゅしゅ)で孫権と曹操が対峙していました。
そこで、孫権が船で偵察に出たところ、曹操軍から激しく矢を射掛けられます。
その結果、矢の重みで船が傾きそうになった孫権は、船を反転させて反対側でも矢を受け、バランスを取って帰還したのです。
つまり演義では、この孫権の機転を諸葛亮の計略として描き直していますよ。
その上、時期も人物も変更されているのです。
このように、羅貫中は諸葛亮を「智絶」として際立たせるため、様々なエピソードを諸葛亮に集約させました。
張飛の酒癖は創作
張飛(ちょうひ)といえば、酒好きで酒癖が悪いというイメージが定着していますよね?
そして演義では、張飛の酒による失敗が何度も描かれます。
徐州(じょしゅう)を呂布(りょふ)に奪われたのも、張飛が酒を飲んで部下に乱暴したことが原因でした。
また、張飛の死因も酒と関係していますね。
演義では、関羽の仇討ちで出陣する直前、酒に酔いつぶれていた張飛が、部下の范彊(はんきょう)と張達(ちょうたつ)に暗殺されます。
そのため、これらのエピソードから、「張飛=酒好きの粗暴な武将」というイメージが出来たのです。
しかし、正史には張飛の酒癖に関する記述は一切ありません。
ちなみに、正史の「張飛伝」には、確かに張飛の欠点が記されています。
それは「身分の高い者には敬意を払うが、身分の低い者には厳しく当たった」というもの。
このため、劉備は張飛に「部下に厳罰を与えすぎると、いつか災いを招く」と忠告していました。
実際には、この予言通りに張飛は部下に暗殺されています。
ただし、それは酒のせいではありませんでした。
演義は、張飛のキャラクターをより分かりやすく描くために、「酒癖が悪い」という設定を追加したんです。
この理由は、豪快で単純、憎めない人物という張飛像を強調するためでした。
劉備が督郵を鞭打った?
演義の序盤、劉備・関羽・張飛の三兄弟が黄巾(こうきん)の乱を平定した後のエピソードがあります。
功績を認められない劉備たちの前に、横暴な督郵(とくゆう)という官吏が現れ、劉備を侮辱しました。
そこで、これに怒った張飛が、督郵を縛り上げて鞭で打つという痛快な場面です。
この時、劉備は止めようとしますが、張飛の怒りは収まりません。
このように、このエピソードは張飛の義に厚い性格と、理不尽な権力への抵抗を象徴する名場面とされています。
ですが、正史を見ると、鞭を打ったのは張飛ではなく劉備本人でした。
正史によれば、劉備は平原相(へいげんそう)という官職についており、上司の督郵が視察に来た際、劉備は何らかの理由で督郵に不満を持ちます。
そして、劉備自身が督郵を縛り上げ、鞭で打ち据えた後、官職を捨てて逃亡したのです。
つまり、演義ではこの行動を張飛に移し替えており、その理由は明白です。
演義における劉備は「仁徳の人」として描かれており、そのような人物が、自ら暴力を振るうのは相応しくありませんよね?
その一方、張飛は行動派の武将という設定になっています。
そのため、張飛に督郵を鞭打たせることで、劉備の人格を守りつつ、痛快な場面を作り出したんですね。
その他7つの驚きの違い
以下に、演義と正史で異なる主要なエピソードを表にまとめました。
| エピソード | 演義での描写 | 正史での真実 |
|---|---|---|
| 桃園の誓い | 劉備・関羽・張飛が義兄弟の契りを結ぶ感動的な場面 | 正史には桃園の誓いの記述なし。三人の強い絆は事実だが、義兄弟の儀式は創作 |
| 三顧の礼 | 劉備が雪の中を三度訪ね、諸葛亮が天下三分の計を語る | 正史にも三顧の記述はあるが非常に簡潔。天下三分の計の詳細は裴松之の注による |
| 関羽の千里行 | 曹操の元を離れ、劉備を探して千里を旅する壮大な物語 | 正史には「劉備の元に帰った」とあるのみ。千里行の詳細な描写は創作 |
| 長坂坡の戦い | 張飛が一人で橋に立ち、曹操軍を威嚇して退却させる | 正史でも張飛が少数で殿軍(しんがり)を務めたとあるが、演義ほど劇的ではない |
| 赤壁の戦い | 諸葛亮が風を呼び、連環の計で大勝利 | 正史では周瑜の功績が中心。諸葛亮の役割は限定的で、借東風(しゃくとうふう)は創作 |
| 華容道 | 関羽が曹操を見逃す義理の場面 | 正史には華容道のエピソードなし。完全な創作 |
| 空城の計 | 諸葛亮が城門を開けて琴を弾き、司馬懿を退却させる | 正史にはこのエピソードなし。元は別の人物(趙雲など諸説あり)の逸話か |
これらの違いを見ると、演義がいかに創作を巧みに織り交ぜているかが分かりますよね。
演義は史実を土台にしながら、物語性を大幅に高めているのです。



演義の創作は、歴史の本質を歪めるものではありません。むしろ、人物の性格や時代の雰囲気を分かりやすく伝える役割を果たしています。諸葛亮に知略を、張飛に豪快さを集約することで、読者は各人物の特徴を理解しやすくなっていますね。
五大英雄の実像と虚像—人物別徹底比較
演義と正史では、主要人物の描かれ方も大きく異なります。
そこで、ここでは五大英雄の実像に迫りますよ。
劉備・関羽・張飛の真実の姿
演義では、劉備は常に仁徳の人として描かれます。
部下思いで、民を愛し、決して卑怯な手段を使いません。
また、涙もろくて優柔不断な面もありますが、それも人間味として好意的に描かれています。
しかし、正史の劉備は、もっと複雑な人物なんです。
正史によれば、劉備は確かにカリスマ性のある指導者でした。
人を惹きつける魅力があり、多くの有能な人材が劉備の元に集まりました。
しかし、これと同時に政治的な野心も強く持っていました。
劉表(りゅうひょう)の息子から荊州を奪ったことなど、必ずしも仁徳だけで動いていたわけではありません。
そのため、陳寿は劉備を「英雄の器を持つ人物」と評価しながらも、「度量は大きいが詳細には疎い」とも記しています。
つまり、大局的な判断はできるが、細かい統治は苦手だったということであり、演義のイメージとは少し異なります。
演義での関羽は「義絶」、つまり義の化身ですね。
劉備への忠誠は絶対で、千里行や華容道など、義理を重んじる数々のエピソードが描かれています。
また、武芸も超人的で、華雄(かゆう)を斬り、顔良(がんりょう)・文醜(ぶんしゅう)を討ち取っているんです。
そして、正史の関羽も確かに優れた武将であり、「関羽伝」には彼の武勇と軍事的才能が記されています。
特に、樊城(はんじょう)の戦いで于禁(うきん)の軍勢を破った功績は高く評価されているのです。
しかし、関羽には重大な欠点もあり、それは傲慢さです。
正史には「関羽は同僚や部下を見下す傾向があった」と記されています。
特に、孫権からの婚姻の申し出を侮辱的に断ったことが、呉との関係悪化を招きました。
そして、これが最終的に関羽の敗北と死に繋がったのです。
つまり、演義では関羽の傲慢さは義理と結びつけられていますが、正史ではより批判的となっています。
演義の張飛は、豪快で単純、酒好きという分かりやすいキャラクターですが、正史の張飛には意外な一面があります。
正史によれば、張飛は「君子や学者を敬った」とあり、これは教養のある人物に対しては丁重に接していたのです。
また、張飛は書や絵にも優れていたという記録もありますよ。
つまり、演義の粗野なイメージとは異なり、文化的素養も持っていた可能性があるのです。
ただし、身分の低い者への態度は厳しく、それが暗殺に繋がっており、この点は演義と共通しています。
曹操と諸葛亮はその評価が180度逆転している
演義での曹操は「奸絶」、つまり悪の権化として描かれています。
漢王朝の簒奪を目論む野心家で、残虐で狡猾な人物という設定となっていますよ。
呂伯奢(りょはくしゃ)一家を殺害し、「我、人に負くとも、人をして我に負かしむること莫(な)からん」という台詞が有名です。
しかし、正史の曹操は全く異なっており、陳寿は曹操を「非常の人、超世の傑」と最大級の賛辞で評価しています。
曹操は、優れた軍事指導者であり、詩人であり、改革者でした。
彼は屯田制(とんでんせい)を実施して農業生産を回復させ、能力主義の人材登用を行ったのです。
また、後漢末の混乱を収拾した功績は計り知れません。
ただ、曹操が「悪役」になったのは、演義が蜀を正統としていたことにあります。
つまり、蜀の劉備を主人公にするためには、曹操を敵役にする必要があったのです。
さらに、明代の朱子学(しゅしがく)の影響もあります。
この朱子学では、漢王朝への忠誠が重視されていたのです。
そのため、曹操の簒奪的行為は、朱子学の価値観では許されないものだったのです。
演義の諸葛亮は「智絶」、神のような知略家ですね。
天文を読み、風を呼び、あらゆる計略を完璧に遂行します。
また、赤壁の戦いから北伐まで、蜀の全ての軍事作戦を指揮したかのように描かれています。
そして、正史の諸葛亮は、確かに優れた政治家であり、陳寿は彼を「治国の才」と評価しています。
実際に、内政運営や法制度の整備において、諸葛亮の能力は抜きん出ていました。
そのため、蜀が小国ながら長く存続できたのは、諸葛亮の行政手腕によるところが大きいのです。
しかし軍事面では、陳寿は「応変の将略には及ばず」と評しています。
つまり、諸葛亮は計画的な戦略は得意でしたが、臨機応変な戦術は苦手だったということです。
実際、五度の北伐はいずれも大きな成果を上げられませんでした。
また、劉備存命中、諸葛亮は主に内政を担当し、軍事作戦への関与は限定的でした。
さらに、赤壁の戦いでの活躍は、ほとんど演義の創作なのです。
人物比較一覧表(正史vs演義)
| 人物 | 演義でのイメージ | 正史での評価 | 主な違い |
|---|---|---|---|
| 劉備 | 仁徳の人、涙もろい理想の君主 | カリスマ的指導者だが政治的野心も強い | 演義は仁徳を強調、正史はより現実的 |
| 関羽 | 義の化身、完璧な武将 | 優れた武将だが傲慢で協調性に欠ける | 演義は義を強調、正史は欠点も指摘 |
| 張飛 | 豪快で酒好き、粗野だが義理堅い | 学者を敬う文化人の一面も持つ武将 | 酒癖は創作、教養ある面は省略 |
| 曹操 | 奸雄、悪の権化、簒奪者 | 非常の人、超世の傑、優れた改革者 | 評価が180度逆転 |
| 諸葛亮 | 神算鬼謀の天才軍師、万能の智者 | 優れた政治家だが軍事は得意でない | 軍事面の評価が大きく異なる |
この表を見ると、演義がいかに人物像を単純化・理想化しているかが分かりますね。
正史は人物の長所も短所も記録していますが、演義は物語として分かりやすくするため、特徴を強調しているのです。



人物評価の違いは、それぞれの著作の目的を反映していますね。正史は歴史的評価を、演義は物語の面白さを優先しました。正史で人物の複雑さを知り、演義でその魅力を味わう。この両面性こそが、三国志が時代を超えて愛される理由なのです。
日本独自の三国志—吉川英治が加えた創作
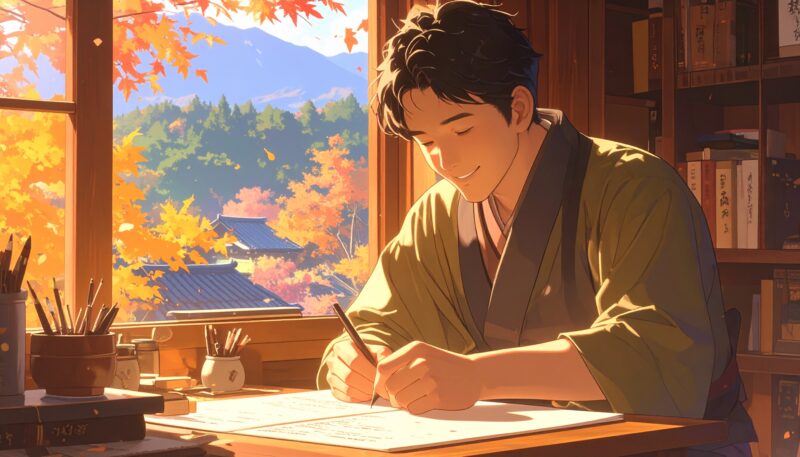
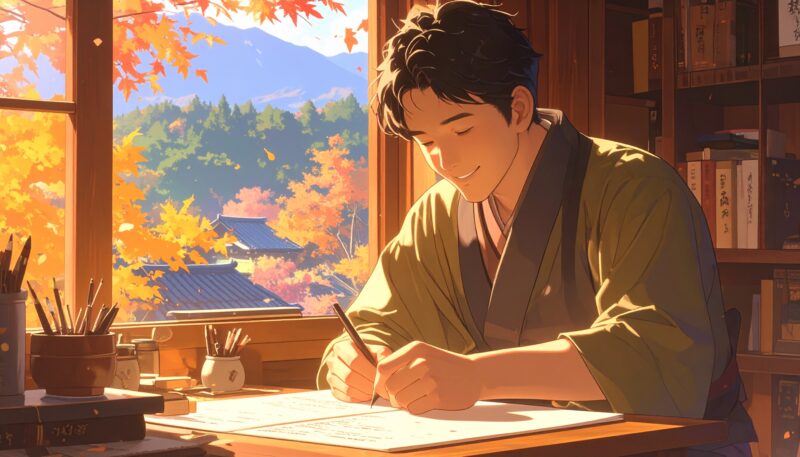
日本で「三国志」といえば、多くの人が吉川英治(よしかわえいじ)の小説を思い浮かべますよね?
しかし、実は日本独自の創作もあるのです。
「茶を買う場面」は日本だけ?
吉川英治の『三国志』に、印象的な場面があります。
それは、劉備・関羽・張飛が初めて出会う場面で、三人が茶を買う描写です。
このシーンは、多くの日本人読者の記憶に残っていますが、実は本場の演義には存在しません。
つまり、これは完全に吉川英治の創作なのです。
かつて、吉川版を読んだ読者が演義の翻訳を読み、「茶を買う場面がない」と翻訳者にクレームを入れた逸話があります。
それほど、吉川版は日本に浸透していたんですね。
ちなみに、吉川英治は演義を底本としながらも、日本人読者により親しみやすい描写を多数加えています。
これらの描写が、その後日本独自の三国志像を作り上げたのです。
また、吉川版の特徴は、人物の内面描写の深さにあります。
演義よりも心理描写が丁寧で、登場人物の葛藤や成長が詳しく描かれていますね。
日本人が抱く三国志イメージの源流
実は、日本における三国志の歴史は結構古いです。
それは、江戸時代の元禄年間(1688-1704年)に湖南文山(こなんぶんざん)が『通俗三国志』を出版してからです。
ちなみに、この通俗三国志ですが、三国志演義の翻訳版になります。
その後、絵草紙や歌舞伎、講談などで三国志は広まっていきます。
明治から大正期にかけては、多くの作家が三国志を題材にしました。
幸田露伴(こうだろはん)、久保天随(くぼてんずい)らが演義を翻訳・翻案しています。
そして、昭和に入り、吉川英治が決定版ともいえる作品を発表しました。
1939年から1943年にかけて新聞連載された吉川版は、戦時中の読者を熱狂させました。
また、戦後も柴田錬三郎(しばたれんざぶろう)、陳舜臣(ちんしゅんしん)、北方謙三(きたかたけんぞう)など、多くの作家が三国志を書いています。
さらに、横山光輝(よこやまみつてる)の漫画『三国志』(1971-1987年)も大きな影響を与えました。
それと、光栄(現コーエーテクモ)のゲーム『三国志』シリーズも、日本人の三国志イメージ形成に貢献しています。
これらの作品の多くは、演義を底本としながらも、独自の解釈や創作を加えています。
例えば、北方謙三版では曹操が主人公として描かれ、従来の「悪役」イメージとは異なる英雄像が提示されました。
このように、日本の三国志作品は、時代ごとの価値観や美意識を反映しながら、変化し続けているのです。



日本における三国志は、単なる翻訳や紹介にとどまりません。日本の文化や価値観と融合し、独自の発展を遂げてきました。吉川英治の創作も、その一環ですね。
初心者のための読書ガイド—どちらから読むべきか
三国志に興味を持った初心者の方は、まず何から読めばよいのでしょうか?
楽しむなら演義、史実なら正史
初めて三国志に触れる方には、断然演義をおすすめします。
理由は明確で、演義は物語として非常によくできており、読みやすく、面白いからです。
登場人物のキャラクターが明確で、物語の展開もドラマチックになっていますよ。
そして、演義を読めば、三国志の全体的な流れが理解することが出来ます。
「どんな時代で、どんな人物がいて、どんな出来事が起こったのか?」
こうした基本的な知識を、楽しみながら得ることが出来るのです。
また、演義は後の様々な作品の元ネタにもなっていますよ。
日本の小説、漫画、ゲーム、映画など、多くの三国志作品は演義をベースにしています。
そのため、演義を読んでおけば、これらの作品をより深く楽しめるようになりますよ。
さらに、演義を読んだ後に正史を読むと、「実はこうだったのか」という発見があり、二倍楽しむことが出来ます。
正史は、演義をある程度理解してから読むことをおすすめします。
何故なら、正史は列伝形式で書かれているため、時系列が分かりにくいからです。
人物ごとに章が分かれているので、全体の流れを把握するのが難しくなっています。
そのため、演義で流れを理解していれば、正史の記述がどの時期のことかの判断が可能です。
また、正史は簡潔な文体で書かれており、詳しい描写や心理描写はほとんどないのです。
つまり、史実だけを淡々と記録しているため、物語として読むには味気なく感じるかもしれません。
しかし、演義に親しんだ後であれば、「あのエピソードは正史ではどうなっているのか」という興味を持って読めますよ。
そして、正史を読む楽しみは、演義との違いを発見することにあります。
「諸葛亮の赤壁での活躍はほとんど書かれていない」「張飛の酒癖の話がない」といった発見は、三国志の理解を深めてくれますね。
さらに、演義に登場しないマイナーな武将の列伝も、正史ならではの魅力です。
おすすめの版本と読む順序
演義のおすすめ版本
- 立間祥介訳(徳間文庫):完訳版で、注釈も充実しています。文庫なので手軽に読めます。
- 小川環樹・金田純一郎訳(岩波文庫):学術的に信頼性が高い訳です。全10巻とやや長いですが、丁寧な訳文が特徴です。
- 吉川英治『三国志』:演義の翻訳ではなく、演義を底本とした創作小説です。日本人には最も読みやすく、入門に最適です。
ちなみに、横山光輝の漫画『三国志』も優れた入門書ですね。
演義を忠実に漫画化しており、全60巻で三国志の全体像をつかめますよ。
また、ビジュアルで理解できるため、活字が苦手な方にもおすすめです。
正史のおすすめ版本
- ちくま学芸文庫版(全8巻):日本で唯一の完訳版です。陳寿の本文だけでなく、裴松之の注も全て訳されています。
- 正史『三国志』英傑伝(徳間書店):主要人物の列伝を抜粋した版です。全部読むのは大変という方には、こちらが手軽です。
そこで、正史を読む順序としては、以下をおすすめしますよ。
- まず「魏書・武帝紀(曹操伝)」「蜀書・先主伝(劉備伝)」「呉書・呉主伝(孫権伝)」を読む
- 次に好きな人物の列伝を読む(諸葛亮、関羽、張飛など)
- 時間があれば全巻通読する
この順序なら、三国の大きな流れを把握した上で、詳細を学べますよ。
ちくま学芸文庫版の特徴と魅力
ちくま学芸文庫版の『正史三国志』(全8巻)は、三国志研究者の間でも定評がありますね。
最大の特徴は、日本で唯一の完訳版であることです。
この本は、陳寿の本文だけでなく、裴松之の膨大な注釈も全て日本語に訳されています。
そして、裴松之の注には、陳寿が省略した多くのエピソードが含まれています。
これらを読めるのは、ちくま学芸文庫版だけなんです。
また、詳しい解説、年表、人名索引も付いており、人名索引では気になる人物をすぐに探せます。
三国志には数百人もの人物が登場するため、索引なしでは目的の人物を見つけるのは困難ですよ。
ちくま学芸文庫版は、文庫サイズなので持ち運びやすく、価格も手頃ですね。
全8巻セットでも、比較的購入しやすい価格設定になっています。
また、気になる巻から読み始められるのも文庫版の利点と言えますね。
例えば、諸葛亮に興味があるなら、諸葛亮が収録されている第5巻から読み始めることも出来ます。
つまり、この本は列伝形式なので、必ずしも1巻から順番に読む必要はないのです。
好きな人物の列伝をつまみ食いする読み方も、正史の楽しみ方になりますよ。



三国志の世界に入る方法は、いくつもあります。演義から入るか、正史から入るか、あるいは漫画やゲームから入るか。どの方法を選んでも構いません。大切なのは、自分に合った方法で三国志を楽しむことなんですから。
まとめ
正史三国志と三国志演義、この二つは対立するものではありません。
それぞれが異なる角度から、三国志の世界を照らし出しているのです。
まず、陳寿の正史ですが、史実を重視した記録として価値があります。
しかし、完全に客観的というわけではなく、陳寿自身の立場や時代背景が反映されているのです。
その一方、羅貫中の演義は創作を含みますが、70%の史実に基づいており、人物の本質を見事に描き出しました。
つまり、正史が骨格なら演義は血肉であり、両方を知ることで三国志の世界は立体的に浮かび上がります。
そして、日本独自の発展も含め、三国志は時代と場所を超えて愛され続けているのです。



「どちらが正しいか」ではなく、「どちらも真実の一面を伝えている」と考えるべきですね。歴史とは、記録された事実だけでなく、それを語り継ぐ人々の思いも含むものです。正史と演義の両方に触れることで、私たちは1800年前の英雄たちの生きた時代を、より深く理解できますよ。
