 歴史探偵女
歴史探偵女三国志とキングダムはどっちが先なの?



三国志とキングダムはそれぞれどんな時代?
この記事では、こんな疑問にお答えしますね。
- 三国志とキングダムはどっちが先なのか?
- キングダムの時代について
- 三国志の時代について
- キングダム~三国志間の時代について


- 歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き


- 歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き
「三国志とキングダム、どっちが先の時代なの?」
漫画やアニメで大人気の両作品ですが、時代の順序で混乱している方も多いのではないでしょうか?
ちなみに、結論から言うとキングダムの方が約400年先の時代です。
キングダムは紀元前3世紀の戦国時代、三国志は紀元後3世紀の出来事なんですよ。
そこで、当記事では両作品の正確な時代と年代、それぞれの時代背景、400年の間に起きた中国史の大きな流れなどについて分かりやすく解説しますね。
【結論】キングダムが約400年先!時代の違いを一目で理解


まずは結論から確認しましょう。キングダムと三国志には、約400年の時間差があります。
時代を比較表で見る
この2つの時代を時系列で整理すると、こうなります。
キングダムの時代:紀元前260年頃~紀元前221年
- 戦国時代の終わり
- 秦による中華統一へ向かう時期
- 始皇帝(しこうてい)の活躍
間の時代:約400年間
- 紀元前206年:秦の滅亡
- 紀元前202年:劉邦(りゅうほう)が漢を建国
- 漢王朝が約400年間繁栄
三国志の時代:西暦184年~280年
- 後漢(ごかん)末期の混乱
- 魏(ぎ)・呉(ご)・蜀(しょく)の三国時代
- 最終的に晋(しん)が統一
つまり、キングダムの主人公・信(しん)が活躍した時代から、三国志の曹操や劉備の時代までは約400年も離れているんです。
これを日本の歴史で例えると、室町時代と現代ほどの時間差がありますね。
それぞれの時代の特徴
この両者の時代には、かなり大きな違いがあるため、この違いを箇条書きで比較してみましょう。
キングダムの時代(戦国時代)の特徴
- 七つの国が覇権(はけん)を争う分裂状態
- 法家思想(ほうかしそう)による厳しい統治
- 富国強兵(ふこくきょうへい)政策の競争
- 始皇帝による中華統一の達成
- 郡県制(ぐんけんせい)など中央集権体制の確立
三国志の時代(後漢末期~三国時代)の特徴
- 統一王朝の崩壊と群雄割拠(ぐんゆうかっきょ)
- 儒教(じゅきょう)が国家理念の中心
- 豪族(ごうぞく)の力が増大
- 魏・呉・蜀の三国鼎立(ていりつ)
- 人口が激減するほどの長期戦乱
どちらも、戦乱の時代という共通点はあります。
でも、キングダムは「分裂から統一へ」、三国志は「統一から分裂へ」という真逆の流れになっているのです。
全く真逆の流れなので、この両者を比較するとかなり面白いと思いますよ。
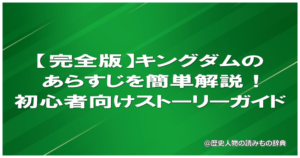
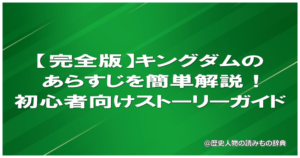



両作品の時間差は約400年。この長い時間の中で中国は統一と分裂を繰り返しましたが、戦乱という共通点が両作品の魅力を生んでいます。歴史のサイクルを感じられる組み合わせと言えるでしょう。
キングダムの時代を知る!秦の統一への道のり
それでは、キングダムの舞台となった時代を詳しく見ていきましょう。
戦国時代とは何か?
キングダムの舞台は、いわゆる「戦国時代」です。
紀元前403年から紀元前221年まで、約180年間続くことになります。
そして、この時代ですが、中国には七つの強国がありました。
秦(しん)・楚(そ)・斉(せい)・燕(えん)・趙(ちょう)・魏(ぎ)・韓(かん)の七国です。
これらを「戦国七雄(せんごくしちゆう)」と呼びます。
そこで、各国は覇権を争い、激しい戦いを繰り返していたように、この時代の特徴は徹底した実力主義です。
自分の身分に関係なく、能力があれば出世できる風潮があったんですね。
また、富国強兵政策の競争も激化しており、結果法家思想に基づく改革を進めた秦が勝利を収めています。
キングダムの主人公たちと史実
キングダムの主人公・信には実在のモデルがいて、それが秦の将軍・李信(りしん)です。
この李信、実は『史記(しき)』に記録が残る実在の人物なんですよ。
史実では、始皇帝の中華統一に貢献した将軍として活躍しています。
そして、もう一人の主人公・嬴政(えいせい)は、後の始皇帝です。
紀元前221年に、秦以外の六国を滅ぼして中華統一を達成した歴史上の偉人ですね。
ちなみに、始皇帝は万里の長城の建設や、兵馬俑(へいばよう)の製作でも有名ですよ。
ただし、史実と漫画には違いもあり、キングダムでは信と政の熱い友情が物語の中心となっていますよね?
しかし、実際の李信と始皇帝の関係性は、詳しい記録が残っていないんです。
そのため、二人が幼い頃からの親友だったという設定は、創作の可能性が高いと言えます。
でも、史実をベースにした感動的なストーリー展開が、キングダムが大人気漫画となっている要因ですね。



キングダムが描く統一への情熱は、混乱の時代を終わらせたいという当時の人々の願いを表していますね。始皇帝の功績は後世に大きな影響を与えており、三国志の時代にもその統治システムは受け継がれたのです。
三国志の時代を知る!英雄たちが駆けた激動の100年


次に、三国志の舞台となった時代を見ていきましょう。
後漢末期から三国時代の流れ
三国志の物語は、西暦184年にとある反乱によって始まります。
この年、黄巾の乱(こうきんのらん)という大規模な農民反乱が起きました。
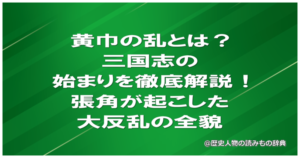
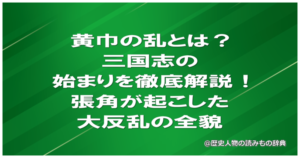
当時、後漢王朝はこの乱を鎮圧できず、急速に衰えていきます。
そして、この混乱の中で、各地の武将たちが力をつけていきました。
曹操(そうそう)や劉備(りゅうび)、孫権(そんけん)の三人が代表的な人物と言えますね。
そこで、西暦208年には、かの有名な赤壁の戦い(せきへきのたたかい)が起こります。
この戦いにより、孫権と劉備の連合軍に曹操が敗れて南下が阻まれたのです。
また、西暦220年には、曹操の息子・曹丕(そうひ)が魏を建国して、400年続いた漢王朝が正式に滅亡することになったのです。
その後、蜀と呉も建国して、魏と合わせた三国時代は西暦280年に晋が統一するまで続きました。
このように、三国志は約100年間にわたる激動の時代だったことが分かりますね。
三国志の魅力と史実の違い
三国志には、二つの重要な書物があり、一つは正史『三国志』、もう一つは小説『三国志演義』です。
まず正史『三国志』ですが、陳寿(ちんじゅ)が西暦3世紀に書いた歴史書です。
この正史では、比較的客観的に史実を記録しています。
一方、『三国志演義』は、羅貫中(らかんちゅう)が14世紀に書いた小説です。
こちらは、劉備陣営を美化した内容になっており、羅貫中の思い(劉備を英雄化する)があったのかも知れませんね。
そして、演義では、諸葛亮(しょかつりょう)が神がかり的な軍師として描かれます。
関羽(かんう)や張飛(ちょうひ)も、超人的な英雄として登場していますね。
特に、張飛の長坂橋で曹操軍を一喝する場面なんて、「張飛やべ~」と思いましたもん。
また、正史と演義での曹操の評価は異なっていますよ。
実際の曹操は、優れた政治家であり文化人でもあって、詩人としても一流で、多くの名作を残しています。
演義では悪役として描かれがちですが、史実の曹操はかなり魅力的な人物なんです。
ちなみに、現代の漫画やゲームの多くは、演義をベースにしています。



三国志の時代は、キングダムで築かれた統一帝国が再び分裂した時期です。約400年前に始皇帝が実現した中華統一の夢が崩れ、再び群雄が覇を競う時代となりました。強大な権力も永遠ではないことを、三国志は教えてくれていますね。
400年の間に何があった?キングダムから三国志への歴史の流れ
キングダムと三国志の間には、約400年の歴史があります。
この間に一体何があったのか、詳しく見ていきましょう。
秦の統一とその後の崩壊
紀元前221年、始皇帝は中華統一を達成。これが、キングダムのクライマックスと言えますね。
この統一後、秦の始皇帝は様々な改革を実行しています。
まずは、度量衡(どりょうこう)を統一し、全国で同じ重さや長さの基準を定めます。
そして、それまで国ごとに違った文字を、篆書(てんしょ)という書体に統一したのです。
また、郡県制(ぐんけんせい)という地方統治制度も確立して、中央集権的な国家体制が整います。
しかし、始皇帝は紀元前210年に亡くなり、その後、秦はわずか15年で滅亡してしまいました。
この原因は、急激な改革による民衆の疲弊があったのです。
厳しすぎる法治主義への反発も大きかった可能性がかなり高そうです。
始皇帝の死後、各地で反乱が起こり、最終的に劉邦という人物が勝利を収めています。
漢の時代400年間
劉邦は、紀元前202年に漢を建国し、前漢と後漢を合わせて、約400年間続きました。
400年間も続いたこの長期政権の秘訣は、何といっても統治方針の転換です。
秦の厳しい法治主義を緩め、儒教を国教化しました。
儒教の「仁(じん)」の思想で、民衆の心をつかんだんですね。
そして、漢の時代は文化的にも繁栄しており、シルクロードを通じた交易が盛んになります。
また、紙の発明など、技術革新も進化。「漢字」「漢民族」という言葉は、この時代に由来しています。
それほど、影響力の大きな漢王朝だったんですね。
しかし、後漢末期の2世紀後半から、いよいよ衰退が始まります。
宦官(かんがん)の専横(せんおう)や、外戚(がいせき)の権力争いが激化したため、農民反乱も多発します。
そして、西暦184年の黄巾の乱をきっかけに、三国志の時代へと突入していくのです。



キングダムと三国志、その間には約400年続いた漢王朝の繁栄がありました。始皇帝が築いた統一の基盤の上に、漢は儒教という新しい理念で長期政権を実現したのです。この歴史を知ると、両作品がより深く理解できますよね。
まとめ
最後に、キングダムと三国志の時代関係をまとめます。
まずは、歴史の流れを整理してみますね。
1. キングダムの時代(紀元前3世紀)
- 戦国七雄の争いが激化
- 秦が他の六国を滅ぼす
- 始皇帝による中華統一達成
2. 秦の滅亡と漢の建国(紀元前2世紀)
- 始皇帝の死後、秦が急速に崩壊
- 劉邦が項羽(こうう)を破り漢を建国
- 儒教を国教化し、安定した統治を実現
3. 漢の繁栄(約400年間)
- 前漢と後漢で長期政権
- シルクロード交易の発展
- 文化・技術の大きな進歩
4. 三国志の時代(紀元後3世紀)
- 後漢の衰退と黄巾の乱
- 群雄割拠の時代へ
- 魏・呉・蜀の三国鼎立
- 最終的に晋が統一
この流れを理解すれば、三国志とキングダム両作品の背景がよく分かります。
また、この2つの時代には約400年の差があり、この間に劉邦による漢の建国がありました。
キングダムは統一への情熱を描き、漢の時代を挟んで三国志では分裂の悲劇が描かれています。
こうしてみると、この2つの時代は中国史において重要な転換点と言えますね。



三国志とキングダム、どっちが先かを知ることで、統一への情熱と分裂の悲劇という歴史の大きな流れが見えてきます。両作品を楽しみながら、歴史の奥深さに触れてくださいね。
