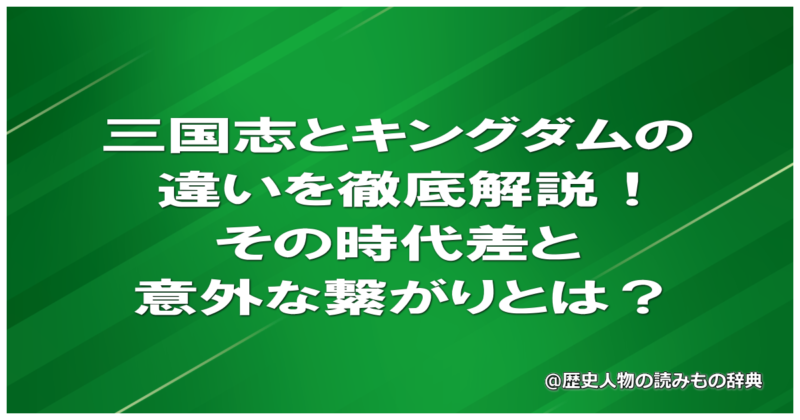歴史探偵女
歴史探偵女三国志とキングダムの違いが良く分からない



三国志とキングダムの繋がりってなに?
この記事では、こんな疑問にお答えしますね。
- 三国志とキングダムの時代の違いと時系列
- 両作品の物語・テーマの根本的な違い
- キングダムの登場人物の子孫が三国志に登場する事例
- 作品としての魅力と特徴の比較
- 史実とフィクションの違いと楽しみ方


- 歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き


- 歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き
「三国志」と「キングダム」、どちらも中国の歴史を舞台にした大人気作品ですよね。
しかし、この2つの作品を見比べていると、ふとこんな疑問が浮かんできませんか?
「あれ、これって同じ時代の話なの?」 「似たような地名や国名が出てくるけど、どういう関係?」
実は、三国志とキングダムには400年という大きな時代の隔たりがあるんです。
そして、驚くべきことに、キングダムで活躍した武将の子孫が三国志の時代に登場しているケースもありますよ。
そこで、この記事では、歴史研究家の視点から、三国志とキングダムの違いを分かりやすく解説していきます。
両作品の時代背景や物語のテーマ、そして意外な繋がりまで、読めば必ず「なるほど!」と納得できる内容をお届けしますね。
三国志とキングダムの時代関係


結論から言うと、キングダムの方が約400年も古い時代を描いています。
つまり、歴史の流れとしては「キングダム→三国志」という順番なんです。
しかし、日本での人気はともかく、知名度は逆だったと思います。
三国志の方が先に広く知られるようになり、キングダムは後から人気を博した作品です。
そのため、時代の前後関係について疑問を持つ方が多いのも無理はありませんね。
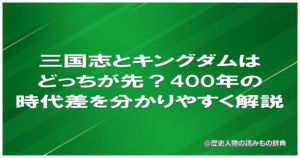
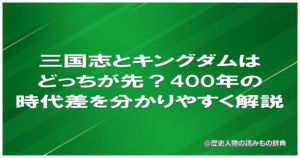
時代の流れを年表で確認
そこで、ここでは具体的な年代を見てみましょう。
物事を視覚的に理解すると、両作品の関係がより明確になりますよ。
キングダムの時代
- 紀元前3世紀(約2,200年前)
- 春秋戦国時代末期(しゅんじゅうせんごくじだいまっき)
- 紀元前221年に秦(しん)が中華統一を達成
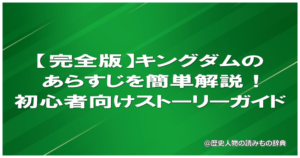
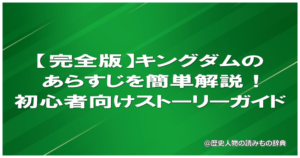
三国志の時代
- 西暦2~3世紀(約1,800年前)
- 後漢末期(ごかんまっき)から三国時代
- 西暦184年の黄巾の乱(こうきんのらん)から始まる
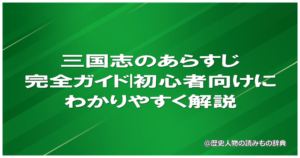
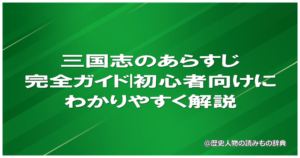
つまり、キングダムで描かれる秦の統一から約400年後に、三国志の時代が訪れるわけですね。
ちなみに、この400年という期間は、日本で例えると江戸時代初期から現代までに相当します。
これは、かなり長い時間ですよね。
そして、この間に中国では、秦の滅亡、劉邦による漢の建国、前漢と後漢という2つの王朝が興亡するという、実に波乱万丈な歴史が展開されていたのです。
なぜ混同されやすいのか
では、なぜこれほど時代が離れているのに混同されやすいのか?その理由は主に3つあります。
キングダムでは戦国七雄(せんごくしちゆう)と呼ばれる7つの大国が争い、三国志では魏・呉・蜀の3つの国が覇権を競います。
これは、どちらも群雄割拠(ぐんゆうかっきょ)の乱世という共通点があるため、似た印象を受けるんですね。
日本では、横山光輝氏の漫画「三国志」や吉川英治氏の小説「三国志」によって、1970年代から三国志ブームが起こりました。
一方、キングダムは2006年に連載が始まった比較的新しい作品ですよね?
そのため、多くの日本人にとって「三国志=先に知った作品」となり、時代の前後関係が分かりにくくなっているんです。
例えば、「秦」「趙」「魏」といった国名は両方の時代に登場します。
ただし、キングダムの時代の戦国七雄の一つである「魏」と、三国志の時代の「魏」は全く別の国なので注意が必要です。
このような名称の重複も、混同の原因になっていると考えられますね。



キングダムの方が400年古い時代ですが、日本では三国志が先に知られたため混同されがちです。しかし時代背景を知ると、両作品の面白さがより深く理解できますよ。
物語としての5つの違い
同じ中国史を舞台にしながら、キングダムと三国志は物語として大きく異なります。
そこで、ここでは両作品の違いを5つの視点から比較してみましょう。
主人公の立場の違い
最も大きな違いは、主人公の立場ですね。
この違いが、物語全体のテイストを大きく変えています。
キングダムの主人公・信
- 立場:下級兵士→将軍
- 出自:戦争孤児で身分が低い
- 目標:「天下の大将軍」になること
- 視点:下から上を見上げる視点
キングダムファンなら分かりますが、信は名もなき下級兵士でした。
しかし、武功を重ねることで少しずつ階級を上げていきます。
そのため、読者は信の目線を通じて、「出世するとはどういうことか」「リーダーシップとは何か」を体験できますよね。
また、これは典型的なサクセスストーリーの構造なんです。
そのため、若い世代や、これから社会で活躍したいと考えている人に強く支持されています。
三国志の主人公たち
- 立場:君主、軍師、将軍
- 出自:劉備は漢の皇族の末裔、曹操は宦官の孫だが名門の養子
- 目標:天下統一、漢王朝の再興
- 視点:トップダウンの視点
三国志では、劉備、曹操、孫権といった君主や、諸葛亮のような軍師が主人公です。
そして、彼らは最初から一定の権力や地位を持っており、「どう組織を運営するか」「どう人材を活用するか」という経営者的な視点で物語が進みます。
そのため、組織のマネジメントに関心がある人や、ビジネスパーソンに人気があるのです。
もっとも、実際に三国志はビジネス書としても多数出版されているほど。
このように、両作品は主人公の立場が全く異なるため、読者が共感するポイントも変わってくるんですね。
物語のテーマの違い
主人公の立場が違えば、当然テーマも異なりますよね?
それでは、両作品のテーマを比較してみましょう。
キングダムのテーマ
- 統一に向かう過程:ゼロから創り上げる
- 仲間との絆と信頼関係:横のつながり
- 下克上のサクセスストーリー:実力主義
- 若者の成長と夢の実現:個人の成長物語
キングダムは、分裂した中国が統一へと向かう「創造のプロセス」を描いているのです。
このキングダムでは、信は仲間たちと共に戦い、信頼関係を築きながら成長していきます。
そして、特に印象的なのが、「仲間」という言葉が頻繁に使われることです。
これは現代的な価値観であり、若い読者層に受け入れられやすい要素だと言えますね。
三国志のテーマ
- 統一の崩壊と再統一:壊れたものを再構築
- 主従関係と忠義:縦のつながり
- 知略と政治的駆け引き:頭脳戦
- 理想と現実のジレンマ:組織運営の難しさ
三国志は、一度達成された統一が崩壊し、再び統一を目指す「再生のプロセス」を描いているのです。
そこで、ここでは「忠義」という価値観が重要です。
関羽が劉備への忠義を貫く姿、諸葛亮が劉備の遺志を継いで北伐を続ける姿などなど。
主君への絶対的な忠誠心が美徳とされており、これは儒教的な価値観に基づいたものです。
また、「天下三分の計」に代表されるような高度な戦略思考も、三国志の大きな魅力です。
単純な武力ではなく、知恵と策略で状況を打開する様子が、読者を引き込みますよね。
フィクション度合いの違い
両作品とも史実をベースにしていますが、フィクションの割合は大きく異なります。
キングダム
- ベース:史記などの史書
- 脚色度:★★★★☆(かなり高い)
- 原作形態:漫画(原泰久・著)
- 特徴:キャラクターの性格や戦闘シーンは創作中心
キングダムは、史実の大きな流れは守っていますが、細かい部分はかなり自由に創作されていますよね?
特に、信をはじめとする主要キャラクターの性格描写は、ほぼオリジナルと言ってよいでしょう。
また、史記にほとんど記録のない人物を魅力的に描くことで、物語を膨らませています。
この発想力や創作力は見事としか言いようがありませんね。
また、これは漫画ならではの表現の自由度を活かした手法です。
三国志
- ベース:正史「三国志」
- 脚色度:★★★☆☆(演義の場合)
- 原作形態:歴史小説(羅貫中・著)
- 特徴:「三分実、七分虚」
三国志演義は、「3割が史実、7割が創作」と言われています。
大きな戦いの勝敗などは史実に基づいていますが、戦闘の描写や人物のエピソードは創作が多いんです。
例えば、「桃園の誓い」(劉備・関羽・張飛が義兄弟の契りを結ぶ有名なシーン)は演義の創作です。
正史には、3人が親しかったという記述はありますが、義兄弟の契りを結んだとは書かれていません。
一方、正史「三国志」は歴史書なので、演義よりもはるかに客観的で信頼性が高いです。
そのため、学術的な観点から三国志を知りたい場合は、正史を読むことをおすすめします。



キングダムは個人の成長、三国志は組織の興亡という異なる視点で描かれています。そのため、読者の年齢や立場によって共感するポイントが変わるのが興味深いですね。
驚きの繋がり!キングダムの人物の子孫が三国志に登場


ここまで読んで、「400年も離れているなら、全く関係ないのでは?」と思われたかもしれませんね。
しかし実は、キングダムの登場人物の子孫が三国志の時代に活躍しているケースがあるんです。
「血脈は時代を超えて繋がっていたとは」
これは、壮大な歴史ロマンですよね。
それでは、具体的に見ていきましょう。
司馬尚の子孫・司馬懿仲達
最も有名なのが、司馬氏(しばし)の血統です。
キングダムの時代:司馬尚(しばしょう)
- 趙国の名将
- 秦の侵攻を何度も退けた防衛の達人
- 史記にもその活躍が記録されている
三国志の時代:司馬懿(しばい)
- 魏の軍師・政治家
- 諸葛亮孔明と五丈原で対峙した知将
- 魏の実権を掌握し、晋建国の基礎を築く
実は、司馬尚から約400年後の子孫が司馬懿なんです。
そして、司馬懿の孫である司馬炎が晋を建国し、三国時代を終わらせました。
つまり、キングダムの時代に趙を守った司馬氏の血統が、三国志の時代を終わらせたという壮大な歴史の流れがあるんです。
いや~これを知ると、両作品を読む楽しみが倍増しますよね。
司馬懿は三国志でも屈指の知将として描かれ、特に演義では諸葛亮の宿敵として重要な役割を果たすのです。
「死せる諸葛、生ける仲達を走らす」という有名な逸話も残されていますね。
王翦の子孫・王允
次に注目したいのが、王氏(おうし)の血統です。
キングダムの時代:王翦(おうせん)
- 秦の六大将軍の一人
- 楚を滅ぼすなど、秦の統一に大きく貢献
- 史記でも「名将」として高く評価される
三国志の時代:王允(おういん)
- 後漢末期の政治家
- 暴君・董卓を倒した功労者
- 太原王氏(たいげんおうし)という名門の出身
王翦の子孫である太原王氏は、漢の時代を通じて名門として続きました。
そして王允は、演義で貂蝉を使った「連環の計(れんかんのけい)」で董卓と呂布を分断し、董卓を暗殺することに成功します。
この一件がなければ、三国志の歴史も大きく変わっていたでしょう。
このように、キングダムで秦の統一に貢献した王翦の血を引く者が、三国志の時代でも重要な役割を果たしているんです。
その他の子孫たち
他にも、興味深い血統の繋がりがあります。
李信(りしん)の子孫たち
- 李広(りこう):前漢時代の名将で「飛将軍(ひしょうぐん)」の異名を持つ
- 李陵(りりょう):李広の孫で、匈奴との戦いで知られる
- その他多数の李氏が漢代に活躍
キングダムの主人公・信のモデルである李信の血統は、前漢の時代に李広という伝説的な武将を輩出しています。
李広は弓の名手で、その矢は岩に突き刺さるほどの威力だったと言われているのです。
ただし、残念ながら李氏は三国志の時代には目立った活躍をしていません。
しかし、後の唐王朝の皇族(李氏)も同じ血統に連なるとされています。
このように、李信の子孫は、中国史を通じて重要な役割を果たし続けたんですね。
趙奢(ちょうしゃ)・趙括(ちょうかつ)の子孫
- 馬服君・趙奢:趙国の名将(キングダム時代)
- 趙括:長平の戦いで王騎に敗れた将軍(キングダムに登場)
- 馬騰(ばとう):後漢末期の武将(三国志時代)
- 馬超(ばちょう):劉備に仕えた「錦馬超(きんばちょう)」(三国志時代)
- 馬岱(ばたい):馬超の従弟(三国志時代)
趙奢は「馬服君(ばふくくん)」という称号を持っていたため、子孫は趙氏から馬氏に姓を変えました。
その子孫が、三国志で活躍する馬騰・馬超・馬岱です。
ちなみに、馬超は「五虎大将軍」の一人に数えられる勇将で、演義では華麗な槍術と立派な容姿から「錦馬超」と称されました。
このように、キングダムで王騎に敗れた趙括の血を引く者が、400年後に名将として活躍しているというのは感慨深いですね。



400年という時を超えて血脈が繋がっている事実は、歴史のロマンを感じさせます。優れた人物の遺伝子や家訓が、時代を超えて受け継がれていくのは興味深い現象ですよね。
どっちが面白い?それぞれの魅力
「結局、キングダムと三国志、どっちが面白いの?」
これは、多くの人が気になる質問だと思います。
しかし、これは「どちらが優れているか」ではなく、「どちらが自分に合っているか」という問題なんですよね。
それは、両作品はそれぞれ異なる魅力を持っているからです。
キングダムの魅力
キングダムの最大の魅力は、熱い友情と分かりやすいサクセスストーリーです。
魅力ポイント
- 主人公・信の成長が分かりやすい
- 仲間との絆が深く描かれる
- スピード感のあるバトルシーン
- 女性キャラクターも将軍として活躍(羌瘣(きょうかい)など)
- 現代的な価値観で描かれているため共感しやすい
信は当初、剣の腕は立つものの戦術眼に欠けるという、単純な性格でした。
しかし、様々な戦いを経験し、仲間と出会い、敗北から学ぶことで、次第に「将軍とは何か」を理解していきます。
そして、この成長過程が丁寧に描かれているため、読者は信と一緒に成長している気分になれるんです。
「俺も頑張ろう」みたいな勇気をもらえる作品と言えますよね?
また、羌瘣(きょうかい)や楊端和(ようたんわ)といった女性武将が重要な役割を果たすのも、魅力的です。
従来の歴史物では男性中心になりがちでしたが、キングダムは幅広い層に支持される工夫がされていることが分かります。
さらに、戦闘シーンも見どころで、漫画ならではの迫力ある描写で、戦場の臨場感が伝わってきます。
王騎将軍の「ンフフフ」という独特の笑い声や、「ココココ」という擬音は、多くのファンの心に残っていますよね。
三国志の魅力
一方、三国志の魅力は、深い知略と複雑な人間ドラマにあります。
魅力ポイント
- 高度な戦略と心理戦
- 複雑に絡み合う人間関係
- 「義」「忠義」といった伝統的価値観
- 多様な登場人物(武将、軍師、君主、それぞれに個性)
- 1800年以上語り継がれてきた普遍性
三国志の戦いは、単なる武力のぶつかり合いではありません。
諸葛亮の「空城の計(くうじょうのけい)」、周瑜の「苦肉の計(くにくのけい)」など、知恵と策略が勝敗を分けるのです。
「相手の心理を読み、数手先を考えて行動する」このチェスのような駆け引きが、三国志の醍醐味と言えますね。
また、人間関係も複雑で、物語をより深くしています。
劉備・関羽・張飛の「桃園の誓い」に代表される義兄弟の絆、諸葛亮が劉備の遺志を継いで北伐を続ける忠義、曹操の冷徹な実力主義など。
このように、三国志では様々な人間ドラマが展開されます。
そして、これは特に印象的ですが、敵同士でありながらも互いを認め合う関係性です。
曹操と劉備、諸葛亮と司馬懿など、敵対しながらも相手の才能を高く評価するシーンは、三国志の深みを感じさせますね。
世代別・タイプ別のおすすめ
最後に、どちらがおすすめかを整理してみましょう。
キングダムがおすすめな人
- 10代~30代の若い世代
- 熱血系・友情物語が好き
- 分かりやすいサクセスストーリーを求めている
- 漫画やアニメから入りたい
- これから社会で活躍したいと考えている
三国志がおすすめな人
- 40代以上の世代(もちろん若い人にも)
- 戦略・知略を重視する
- 複雑な人間ドラマが好き
- ビジネスや組織運営に関心がある
- 歴史の深みを味わいたい
実は、三国志とキングダム、両方読むことで相乗効果が生まれます。
キングダムを読んでから三国志を読むと、「秦が統一した中国がどう変化していったか」という歴史の流れが理解できます。
逆に、三国志から入ってキングダムを読むと、「三国志の400年前はこんな時代だったのか」という発見があるのです。
また、両作品を比較することで、「統一する過程」と「統一を維持する難しさ」という対照的なテーマが見えてきますよ。



どちらが優れているかではなく、異なる魅力を持つ作品です。個人の成長物語を求めるならキングダム、組織の興亡を学びたいなら三国志がおすすめと言えますね。
まとめ
ここまで、三国志とキングダムの違いについて詳しく見てきました。
この両作品は、時代も テーマも異なります。
しかし、どちらも「人間とは何か」「リーダーシップとは何か」「組織とは何か」という普遍的な問いを投げかけているのです。
キングダムからは、夢を持ち続けることの大切さ、仲間を信じる力、失敗から学ぶ姿勢を学べます。
そして、三国志からは、長期的な戦略思考、多様な人材の活用、理想と現実のバランスを学べるのです。
ちなみに、どちらか一方だけでも十分に楽しめますが、両方を読むことで、中国の歴史をより理解できるようになります。
そして何より、2,000年以上前の出来事が、現代の私たちにも深い示唆を与えてくれることが分かると思いますよ。



キングダムと三国志は400年の時を隔てていますが、どちらも人間の本質を描いた物語です。この両作品を読むことで、中国史への理解が深まり、現代にも通じる知恵を得ることが出来ますよ。