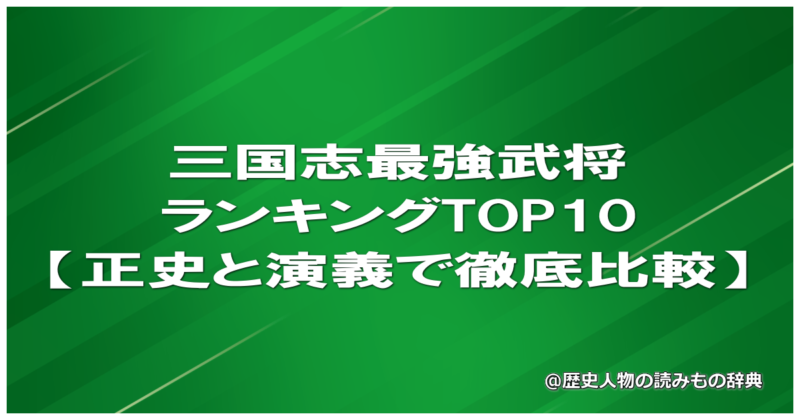歴史探偵女
歴史探偵女三国志で最強の武将って誰なの?



三国志の武将で一騎打ちは誰が強かったの?
この記事では、こんな疑問にお答えしますね。
- 三国志最強武将の総合ランキングトップ10
- 正史と演義での評価の違い
- 一騎打ち特化の最強ランキング
- 各武将の代表的なエピソードと活躍
- 評価軸による強さの違い
- 魏・呉・蜀それぞれの最強武将


- 歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き


- 歴史大好き女
- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上
- 日本史&中国史が得意
- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き
三国志で最強の武将は誰なのか?この永遠のテーマに、歴史研究家の視点から答えますね。
呂布、関羽、張飛といった人気武将はもちろん、張遼や趙雲など名将たちの実力を徹底比較しました。
そして、武力・統率力・知略の3つの視点から総合評価し、さらに正史と演義での評価の違いも解説します。
また、一騎打ち最強ランキングや国別の最強武将も紹介しますので、あなたの推し武将の順位をぜひ確認してくださいね。
三国志最強武将ランキングの評価基準


三国志の武将たちの強さを測るには、いくつかの視点が必要になります。
それでは、どのような基準で評価すべきなのでしょうか?
そこで、まずは3つの重要な評価軸をご紹介しますね。
武力(一騎打ちの強さ)
まず最も分かりやすい基準が「武力」であり、これは一騎打ちでの戦闘能力を指します。
ちなみに、武力とは馬上で槍や剣を振るい、敵将と直接対決する強さのことです。
演義やゲームでは、呂布が一番高い数値で、次に関羽や張飛が続くことが多いです。
しかし、実際の戦場では一騎打ちだけで勝敗が決まるわけではありませんよね?
むしろ、軍全体をどう動かすかが重要だったのです。
統率力(軍を率いる能力)
次に重要なのが「統率力」であり、これは何千、何万もの兵士を率いる指揮能力を意味します。
たとえば、張遼は、わずか800人で10万の呉軍を撃退したことがあります。
これこそ、統率力の賜物(たまもの)といえるでしょう。
また、部下からの信頼も統率力に含まれますね。
関羽は義を重んじる人柄で、多くの将兵が彼のために命を懸けたのです。
知略(戦術・戦略眼)
最後に「知略」も見逃せません。
ちなみに、この知略は戦術を立て、相手の裏をかく能力です。
正史では、関羽は樊城(はんじょう)攻城戦で曹操に遷都を本気で考えさせるほどの脅威を与えました。
そして、これは単なる武力だけでは不可能です。
さらに、状況判断の速さも知略に含まれます。
危機的状況から素早く判断して脱出できるかどうかが、生死を分けたのです。
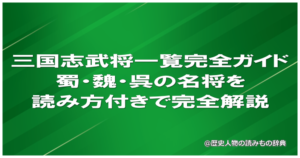
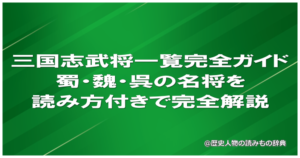



単純な腕力だけでは真の強さは測れません。時代を生き抜いた武将たちは、状況に応じて複数の能力を発揮していたのです。
【総合評価】三国志最強武将ランキングTOP10
それでは、武力・統率力・知略の3つの視点から、総合的な強さランキングを発表します。
なお、このランキングは演義を基本としつつ、正史の記録も考慮していますよ。
第1位〜第3位(呂布・関羽・張飛)
「人中(じんちゅう)の呂布、馬中(ばちゅう)の赤兎(せきと)」と称された、三国志最強の武将ですね。
演義では、虎牢関(ころうかん)の戦いで劉備・関羽・張飛の3人を相手に互角に戦いました。
そして、呂布は弓術・馬術・槍術すべてに長けた万能型の豪傑だったのです。
しかし正史では、裏切りを繰り返した人物として描かれています。
丁原や董卓を斬り、最後は曹操に敗れて処刑されました。
そのため、武力は圧倒的ですが、知略と人望に欠けた点が弱点だったのです。
義を重んじる稀代(きだい)の英雄で、劉備の義兄弟として蜀の建国に尽力しました。
演義では、華雄を一刀のもとに斬り、五関突破(ごかんとっぱ)を成し遂げた豪傑です。
そして、袁紹の武将である顔良や文醜も討ち取りました。
また、正史でも評価は高く、樊城攻城戦では曹操軍を窮地に追い込んでいます。
ただし、最後は呉の計略にかかり、関羽は命を落としました。
「燕人(えんじん)張飛」の異名を持つ、劉備の義弟ですね。
演義での張飛は、長坂橋(ちょうはんきょう)でたった1人で曹操軍を食い止めました。
「この張飛翼徳がいる限り、橋は渡らせぬ」と叫ぶ姿は、三国志屈指の名シーンと言えますよね?
ちなみに、実は正史で意外にも知略もある人物として描かれています。
しかし、酒癖の悪さと部下への厳しさが災いし、最後は部下に斬られてしまうのです。
第4位〜第7位(趙雲・張遼・馬超・典韋)
「常山(じょうざん)の趙雲」として知られ、蜀の五虎大将の一人です。
演義では、長坂坡(ちょうはんは)の戦いで、劉備の息子劉禅を抱えて曹操軍を突破しました。
これは、まさに無双の活躍ですね。
ところが正史では、趙雲の評価はそれほど高くありません。
諡号(しごう)を贈られた順番も12番目で、当時の評価はその程度だったようですね。
このことから、演義と正史で最も評価が異なる武将と言えるでしょう。
魏の五将軍の筆頭で、「遼来遼来(りょうらいりょうらい)」と恐れられた名将です。
合肥(がっぴ)の戦いでは、800の精鋭で10万の呉軍に夜襲をかけました。
そして、孫権をあと一歩まで追い詰めたのです。
ちなみに、この戦いは正史でも記録されており、張遼の強さは史実でも証明されています。
呉の兵士たちは「張遼が来るぞ」と聞くだけで震え上がったそうです。
この張遼という武将、統率力と武力を兼ね備えた、まさに名将だったのです。
「錦馬超(きんばちょう)」の異名を持つ、西涼(せいりょう)のイケメン武将です。
演義では、許褚や張飛と互角に戦いました。
また、騎馬戦の華ともいえるスピード感あふれる戦いぶりは、見る者を魅了することでしょう。
ちなみに正史でも、曹操を何度も窮地に追い込んだ記録が残っています。
ただし、一族を曹操に始末されたことから、復讐心に燃える激情家でもありました。
この馬超という男、武力と速さに優れた、まさに疾風のような武将です。
曹操の親衛隊長で、「悪来(あくらい)」と呼ばれた豪傑です。
演義では許褚と互角に戦い、呂布の猛攻も一歩も引かずに防ぎました。
ちなみに、筋肉ランキングなら文句なしの第1位でしょうね。
そして、宛城(えんじょう)の戦いでは、張繍の反乱から曹操を守るため、命を懸けて戦いました。
しかし、曹操を逃がした後に討ち死にしたのです。
この典韋という男、武力と忠義を兼ね備えた、理想的な護衛武将と言えますね。
第8位〜第10位(許褚・太史慈・黄忠)
曹操の最強ボディガードで、生涯曹操を守り抜きました。
演義では、馬超との一騎打ちで互角に渡り合っています。
また、典韋亡き後は曹操の寝所に出入りできる唯一の武将となりました。
ちなみに、正史でも「容貌は雄壮で、武勇と力量は人並み外れていた」と記されています。
牛の尾を片手で引いて100歩歩いたという逸話も残っているほどです。
呉の猛将で、孫策のライバルでもありました。
演義では、孫策と一騎打ちで引き分けています。
これは正史でも記録されている珍しい一騎打ちですね。
その後、孫策に仕えるようになりました。
しかし、心のどこかで「自分のほうが強い」と思っていたかもしれませんね。
あの曹操も欲しがったほどの武勇の持ち主だったのですから。
ただし、赤壁の戦いの前年に41歳で病死しています。
蜀の五虎大将の一人で、60歳を過ぎても現役だった老将ですね。
演義では、関羽と互角に戦った老将として有名です。
そして、武器は大薙刀(おおなぎなた)と弓で、特に弓は百発百中の腕前でした。
また、定軍山(ていぐんざん)の戦いでは、魏の名将・夏侯淵を討ち取る大功を立てています。
まさに、老いてなお盛んな武将だったようですね。
ただし、夷陵(いりょう)の戦いで亡くなっています。



上位陣は武力だけでなく人格や忠義の面でも優れており、だからこそ後世まで語り継がれる英雄となったのです。
正史と演義で評価が大きく異なる武将たち


三国志には「正史」と「演義」という2つの顔があります。
それでは、どの武将の評価が最も異なるのか?見ていきましょう。
趙雲の実像
趙雲は、演義では大活躍する人気武将です。
しかし、正史での評価は意外にも地味なんですね。
演義では長坂坡の戦いで赤ちゃんを抱えて敵陣突破、一騎打ちでは負けなし、諸葛亮の右腕として活躍しました。
これぞ、まさにスーパーヒーローという活躍ぶりです。
ところが正史では、諡号を贈られた順番が12番目という記録が残っています。
つまり、当時の評価はその程度だったということですね。
また、劉備からの評価も他の五虎大将に比べて低く、官職も低めでした。
この事実は、趙雲ファンにとっては少し残念かもしれませんね。
呂布の評価
呂布は演義では最強の武将として描かれています。
しかし、正史では裏切り者として記録されているんです。
演義での呂布は、虎牢関で劉備・関羽・張飛の3人を相手に互角、方天画戟(ほうてんがげき)を振るう姿は圧巻ですよね?
ところが正史では、丁原を斬った後、今度は董卓も斬っており、信義を守らない人物として描かれています。
そのため、最後は曹操に「この男を信じてはならぬ」と言われ、処刑されました。
もちろん、呂布の武力は本物ですが、人格面での評価は低かったようです。
張飛の意外な一面
張飛といえば、酒好きで粗暴なイメージがありますよね。
しかし、正史では意外な一面が記録されています。
演義での張飛は、猪突猛進型の豪傑といっても過言ではないですよね?
また、長坂橋では1人で曹操軍を食い止めるシーンがあり、これはまさに圧巻の一言です。
ところが正史では、書画をたしなみ、知略も持ち合わせた人物だったとされています。
子の張飛という人物、実は教養人だったんですね。
ただし、部下に厳しすぎた点は正史でも同じです。
そして、最後は部下の范彊(はんきょう)と張達(ちょうたつ)に斬られました。



物語として面白くするため演義では脚色されていますが、正史を読むとまた違った武将の魅力が見えてきますよ。
【武力特化】一騎打ち最強ランキングTOP5
純粋な戦闘能力だけで選ぶなら、ランキングは変わってきますよ。
それでは、一騎打ち特化の最強ランキングを見ていきましょう。
個人戦闘力で選ぶ最強武将
一騎打ちの強さだけに絞ると、以下のようになります。
一騎打ち最強ランキング
- 呂布 – 演義でも正史でも武力は最強クラス
- 関羽 – 華雄や顔良を一刀で斬る圧倒的強さ
- 張飛 – 演義では一騎打ちで負けたことがない
- 馬超 – 許褚と互角、張飛とも引き分け
- 典韋 – 許褚と互角、呂布の攻撃も防ぐ
この5人は、純粋な戦闘能力では群を抜いています。特に呂布は別格ですね。
演義では、呂布と戦えるのは関羽・張飛・馬超くらいで、他の武将は数合で敗れることが多かったのです。
ただし、一騎打ちが強いだけでは戦争には勝てませんよ。
実際、呂布は最後に敗れていますから。
一騎打ちの名勝負エピソード
三国志には、語り継がれる名勝負がいくつもあります。
まず、虎牢関の戦いでは、呂布が劉備・関羽・張飛の3人を相手に戦いました。
これは演義の名シーンで、3人がかりでようやく互角だったのです。
そして、長坂橋の戦いでは、張飛が1人で曹操軍を食い止めました。
正史でもこのエピソードは記録されており、張飛の度胸が伺えますね。
また、関羽千里行では、関羽が曹操の配下の将軍たちを次々と斬りました。
五関を突破する姿は、まさに無双でしたね。
つまり、これらの一騎打ちが、三国志の魅力を何倍にも高めているのです。



一騎打ちは戦場の華ですが、実際の戦では軍全体を動かす力こそが勝敗を分けた点も忘れてはなりませんね。
魏・呉・蜀それぞれの国別最強武将
魏・呉・蜀の三国それぞれに、特色のある強豪武将がいました。
それでは、国別の最強武将を見ていきましょうか。
魏の最強武将(張遼・典韋・許褚)
魏は実力主義の国で、実務能力に優れた武将が多かったですね。
張遼は合肥の戦いで800人で10万の呉軍を撃退しました。
彼は、統率力と武力を兼ね備えた、魏随一の名将ですね。
そして、典韋は曹操の護衛として、宛城の戦いで命を懸けて主君を守りました。
数いる曹操軍の武将の中でも、忠義と武力の象徴といえる人物です。
また、許褚は典韋亡き後、曹操の最強ボディガードとなりました。
演義で描かれている、馬超と互角に戦った武力は本物です。
このように、魏の武将たちは、主君への忠義と実務能力が重視されていました。
呉の最強武将(太史慈・甘寧・孫策)
呉は水軍に強く、みんなに合わせるというよりは、個性的な武将が多い国でした。
太史慈は孫策と一騎打ちで引き分けた実力者なんです。
このことは、正史でも記録されており、彼の数少ない一騎打ちでしたね。
そして、甘寧は元海賊という異色の経歴を持っていました。
夜襲が得意で、「鐘を鳴らして奇襲」という独特の戦法を使っています。
また、孫策は「小覇王(しょうはおう)」と呼ばれた若き英雄です。
呉武将の実力者、太史慈と互角に戦う武力を持っていました。
このように、呉の武将たちは、型破りで独創的な戦術を好んでいたようです。
蜀の最強武将(関羽・張飛・趙雲・馬超・黄忠)
蜀は義を重んじる国で、五虎大将というツワモノがいました。
関羽は義の化身として、敵味方問わず尊敬されており、武力&知力は高いレベルにありました。
そして、張飛は長坂橋で見せた度胸が有名であり、圧倒的な強さを誇りました。
また、趙雲は演義では無双の活躍を見せており、冷静沈着で諸葛亮の右腕として活躍しています。
それと、馬超は西涼の若き英雄で、騎馬戦に優れており、スピードと破壊力を兼ね備えた武将です。
最後に、黄忠は60歳を過ぎても現役で、弓の名手として知られており、老いてなお盛んな豪傑でした。
ちなみに、蜀の武将たちは、義と忠義を何よりも大切にしていました。



各国の特色が武将の戦い方にも表れており、魏は実務型、呉は海戦巧者、蜀は義を重んじる豪傑が多い傾向があることが分かりますね。
まとめ
三国志最強武将ランキングを見てきましたが、いかがでしたか。
総合ランキングでは呂布・関羽・張飛がトップ3となりました。
また、一騎打ちに特化したランキングでも同様の結果となっています。
そして、正史と演義では評価が大きく異なる武将もいました。
趙雲は演義では大活躍しますが、正史では地味な評価です。
さらに、魏・呉・蜀それぞれに、特色のある強豪武将がいました。
魏は実務型、呉は個性派、蜀は義を重んじる豪傑が多かったで印象です。
つまり、「最強」を決めることは非常に難しいんですよね。
なぜなら、評価軸によって順位が変わるからです。
武力だけなら呂布、統率力なら張遼、バランスなら関羽、忠義なら典韋というように、それぞれの武将に輝く部分があります。
そのため、三国志の魅力は、こうした多様な「強さ」を持つ武将たちが、それぞれの信念のために戦ったことにありますよ。



三国志の最強を決めることは難しく、それは武将それぞれに異なる輝きがあるからです。だからこそ、1800年経った今も三国志は世界中で愛され続けているのです。